 階段
階段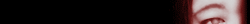
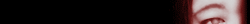 |
 |
GUZZLING All good children go to heaven. |
 すべての過去ログ
すべての過去ログ
ふと、このビルの階段を登ってみようと思った。最上階は25階、きついかもしれないけど無理な高さではないだろう。地下2階から8階までは店舗、9階から14階までは賃貸オフィス、15階から25階がホテルになっている、すべて一般人が入ることができるフロアだ。すべての階段が利用可能に違いない。
8階までは楽勝、9階から先もちょっと迷ったり掃除の人に睨まれたりしたけど大丈夫。心配だったホテルの階段も怪しまれる事なく登ることができた。かなり疲れたけどあと3フロアだ。最上階にはレストランがあるはず。ビールでも飲もう。 へとへとになりながらも何とか25階についた。やっとビールだ。とドアに手を掛けたんだけど、あれ?開かない。くそ、お約束どおりじゃないか。さあどうしよう、ひとつ降りて24階から入るか、それとももう1フロア登って…、登って?登り階段がまだあるな。そっか屋上に出るんだ、それともエレベータ室かもしれないな。せっかくここまで来たんだ、最後まで登ってやろうじゃないか。 何故だろう?まだ階段を登っている。壁には32Fて書いてある。ここもドアは開かない。いくらなんでも多すぎる、ここって35階建てだったっけ。そんな気もしてきたぞ。よし35階まで登って駄目だったらあきらめて降りることにしよう。 そうじゃないかと思ってたけどやっぱりガッカリだ。35階のドアも思ったとおりびくともしない。残念だけど降りることにしよう。次こそ入れるような気もするけど…。おっ「37階まではドアの利用はできません」て書いてんじゃん。あと2つだ行ってみよう。 汚えな。さっきから36Fばっかだよ。これで5個目だ。てことは、この36Fは本当は40階てことか?そんなのありかよ。そもそも、ここは一体何階建てなんだ?意地で登ってきたけどもうさすがに限界、自分の足じゃ無いみたいだもん。俺だって仕舞いには怒るよ。次37階じゃなかったら今度こそ降りる、降りるったら降りるもんね。 あれっ、37階だ。次で降りるって言ったとたんこうだ。タイミング良過ぎるぞ。ひょっとしてドッキリか?そうだドッキリだろこれ、じゃなかったら変だもん。25階しか無いはずなのに40以上もフロアもあるし、いちいちドアに鍵かかってるし、36階ばかり続くし、もう降りるって思ったとたんに37階が出てきたし、ドッキリだよこれ。ドアの鍵も…、ほら開いてるよおい。居るんだろうなこのドアの向こうにヘルメット被ってプラカード持った人が。俺、何てリアクションすれば良いんだろう。知ってたよって顔したら白けるだろうしなあ。やっぱ間抜け面しなきゃ駄目かな。まあいいや、さあ開けるぞ。
烏が鳴いている。随分と甲高い声で鳴く烏だ。誰かの話し方に似ている。同じ部署の佐伯だ。そういえばあいつは烏みたいな顔をしてるな。妙にずる賢いところも烏のようだ。佐伯は烏だ。俺が些細な間違いをしたからどうだと言うのだ。烏め。しかも丁寧な口調で話しつつも結局は俺がいかに悪かったかを事細かに説明しやがって。烏め。
また烏が鳴いた。馬鹿かお前は、鳴いてどうしようと言うのだ。そんな事だからいつまでたっても烏のままなのだ。お前の目つきが気になると木村も中島も花田も言っていたぞ。お前の話し方が気になると佐々木も今岡も新谷も言っていたぞ。何か気の利いた事をしてみろ。いやお前が気の利いた事をしたら余計腹が立つ。 烏が俺の方を見ている。笑ってやがる。笑い方まで佐伯に似ている。おい佐伯、お前はなぜ笑ってるんだ?ちっ、また笑った。何が 「立花さんはこういった子供っぽいことは興味無いでしょうから」 だ。俺が無趣味でつまらなくて面白味がなくて頭が固いと言いたいんだろう。畜生、何故俺が烏に馬鹿にされなければならないんだ。 まだ烏は俺を見ている。俺を見下している。ふざけるな佐伯、烏のくせになに見下してるんだよ。頭が良いからか?後輩に信頼されているからか?それともスタイルが良いからか?美人だからか?……好きだ、佐伯。
いきなり後ろから首を切られた。今まさに地面に追突しようとしている俺。一瞬だけ胴が見えた。うわあ、首から血を吹いてるぞ。と思ったと同時に俺は地面に落ちた。胴体の行く末が気になるが、残念ながら地面しか見えない。頭だけの俺は振り返ることすらできないのだ。あれ、何故だろう?不思議と痛くない。痛いのは胴の方なのか?いやいや、首だって切られてるんだし地面に思いっきりぶつかってるんだから頭だって痛い筈じゃないか。いやいやいや、待て待て、そんな問題じゃない。その前に普通死ぬだろう。どうして意識があるんだ?そっか、もう死んでるのかもしれないな。死んだこと無いから解らないけどこの状態が死ではないという保障はどこにもない。そうか死んだらこうなるのか、案外冷静だな俺って。
と思ってたらいきなり髪の毛をつかまれて持ち上げられた。回転しながら上昇する俺の視点。目が回る。実際は頭が回ってるわけだが。持ち上げてるのは誰だろう。俺の首を切った奴か?うわっ俺の胴じゃないか。目もないのによく頭の場所がわかったな。いやいや、それ以前に何故動いてるんだ?俺の胴よ。これはさすがに変だぞ。首を切断されたら死ぬ、これは当たり前。切断された首に意識があるような気がするけど実際は死んでる、これはかなり怪しいが誰も死んだことないので仮にありとしよう。でも同じく死んでる筈の胴が動いて首を持ち上げるってのはどうなの?これはいくら何でもなしだろう。 あ、そうか。夢だろこれ、夢オチってやつだな。もうちょっとしたら飛び起きて「あたま、あたま」とか言いながら頭を触ってほっとするんだろ?「あ、あった。何だ夢か」とか言って汗びっしょりなんだろうな。明日、小暮に話してやろう。あいつホラーとか好きだから受けるぞ、きっと。さあそろそろ良いだろ、目を覚まそう。 あれ?まだ続くのか。長くてメタな夢だな。俺の胴は何してる?俺を、というか頭を乗っけようとしてるみたいだけど。あ、落としやがった。畜生、また目が回るじゃないか。馬鹿か俺の胴、頭悪いなあ。いや俺がその頭か。で、また髪の毛つかんで持ち上げるし、よせよ抜けるって。しかもまた首に乗っけるつもりか?無理だって切れてんだから。あきらめろよ。そうそう、しっかり両手で抱えてくれよ。 ところで俺の首を切った奴は誰なんだろう?夢とは言っても気になるな。知ってる?俺の胴よ。知らないだろうな、俺が見てないんだから。なかなか目も覚めないみたいだし、探しに行くとするか。行くぞ俺の胴、付いて来い。いや違うな、持って行ってくれ。 こうして俺と俺の胴は、俺の首を切った奴を探し回る旅に出た。そろそろ一ヶ月になるが、俺の首を切った奴はまだ見つかっていない。目も覚めていない。とても嫌な予感がする。これは夢じゃないのかもしれない。
まだ五月だというのにやけに暑い。それにしても静かな街だ。こんな静かなところに住むような奴だとは思わなかったな。お、ここか。結構立派な家じゃないか。こんな良い家に住んでるとは、薄汚れたマンションで暮らす私とは大違いだ。
「おう、早かったな」 呼び鈴を押すと三年前と変わらぬダミ声がインターホンから聞こえてきた。そして厚くて大きなドアが開きやはり三年前と変わらぬ顔をした佐藤が出てきた。 「場所、すぐ解ったか?」 「ああ、地図が正確だったからな」 田中と会うのは三年ぶりだが相変わらず神経質そうな顔をしている。こんな表情でも上機嫌なのだと解るまで半年かかったのを思い出した。奴にしては珍しく汗をかいているところを見ると外は暑いのかもしれない。 「外は暑いのか?」 「5月だというのに、摂氏30度はあるぞ」 いちいち摂氏と付けるところなんか全然変わって無い。まあ三年くらいで話し方が変わるわけないか。 「まあ、入ってくれ。話はそれからだ」 「食べ物は用意してるって言ってたから、ビールしか持ってこなかったぞ」 本当はワインを買おうと思ったのだが、コンビニしか見当たらなかったので、ワインはあきらめてビールにした。幸いコンビニにはエビスがあったのでたくさん買ってきた。「15歳からずっとエビス党」を自認する佐藤にはちょうど良い土産だろう。 「悪いな、手ぶらで良かったのに」 そうは言いながらも、佐藤はもう一本目に手を伸ばしている。田中もしょうがないなと言いながら三年ぶりの乾杯となった。あれ、これは誰の視点だろう。 「最初から、何の説明もなく視点がぶれている上に、謎の視点まで増やされたら読みにくくてたまらないんだけど」 俺もそう思う、俺ってのは佐藤だけど。ところで今しゃべったのは誰だ?視点だけじゃなくて台詞も混乱してるんじゃないのか? 「こんなことが、あって良いのだろうか。ここには私と佐藤しか居ないというのに。話をしている人がどうして何人もいるのだ?私は疲れているのかもしれない。それとも佐藤の家が立派だと言うことに対して卑屈になっているのだろうか。うわっ、これは台詞だったのか!」 台詞と心理描写の区別が付かなくなった俺を見て田中も激しく混乱しているようだ。あれ、田中は私じゃないか。混乱してるのは私の筈だぞ。 「おいおい、もう一回ちゃんと整理してから書いた方が良いんじゃないのか?それから視点は俺か田中のどちらか、またはいわゆる神の視点に統一しなきゃ駄目だろ。まずは落ち着いて考えようぜ」 気が付けば佐藤は冷静さを取り戻しつつある。がさつな分だけ立ち直りが早いのかもしれない。昔からこういうときは私と違って頼りになる奴だ。一方、田中の方はと言えばまだ呆然としてる。あれ?だからこれは誰の視点なんだよ。 そして混乱は果てしなく続く。
うわぁ、魔球を発明しちまったよ、どうしよう。野球なんか全然やったことないのになあ。でもやっぱこれって魔球だよな、絶対打てそうにないもん。この球で松岡を三振にしとめたら、高木もちっとは俺を見直すかな。いや高木のことだから「結局、君はそういう卑怯な手でしか勝てないんだね」とか言いそうだな。マッチョな勝負じゃなきゃ認めないって感じだもんな、あの女は。まあいいや、不純な動機で作り始めたとは言え苦労して考えた魔球だ、なんか愛着も出てきた。この球が野球部に通用するかどうかの方が面白くなってきたぞ。
こんなに通用するとは思わなかったな。自称「次期エースで四番候補」の松岡だけじゃなくて、現四番の岡田さんも三振だったし、ミートが巧いと評判の島谷さんなんか最後はプライドを捨てて3バントまでしたけど打てなかった。高木も予想に反して俺のこと見直してたみたいだし悪くない気分だ。ただ、野球部の連中が入部しろとしつこく言ってきたのは計算外だった。冗談じゃない「俺みたいな虚弱児が野球なんかやったら干からびて死んじゃいます」って必死で断って今日は帰ってきたけど、明日もまた誘われたら嫌だなあ。 ちょっとは覚悟してたけど、あんなにしつこいとは思わなかった。今日なんか昼休みと放課後と帰宅途中の地下鉄とで合わせて三時間勧誘されちゃったよ。その球があれば確実に甲子園行けるって言われても、あんな暑そうなところ行きたくないしなあ。それに甲子園に出るためには市の予選で3試合、県大会で4試合勝たなきゃいけないらしい。無理無理、もう絶対無理、7試合なんて投げるどころかグランドに出るだけで絶対死んじゃう。 どうして、連中はあんなに熱心なんだろうね。今日で5日連続の勧誘だ。そんなに熱心に勧誘する暇があったら練習すれば良いのに。岡田さんなんか「君が投げ抜く体力がないのは解った。その点については僕たちが君の体力アップの手伝いをしよう」と言い出した。野球やってる人ってどこか変だぞ。そうかと思えば誰に丸め込まれたか知らないけど高木が妙に親しく話しかけてくる。そりゃ最初は嬉しかったけど、というか今も嬉しいんだけど、どうも俺を野球部に入れたがってるような気もするなあ。 ようやく勧誘が収まったと思ったら今度は「あの球の投げ方を教えて欲しい」と言い出した。誰がそんな都合の良い要求を聞きますかって。だいたい、エースの井村さんは物理で赤点なんだから投げ方を理解するのは無理に決まってる。と言ったことをオブラートに包んで遠まわしに言ったんだけど、岡田さんは「今は報酬を払えないけど必ずお礼はする。井村じゃ投げるのは無理だというなら僕が投手に転向しよう」とあくまでも引き下がらない。これだけ真面目な秀才がどうして野球をやってるかって事の方が魔球よりよっぽど不思議な気もするんだけど。そのことは口に出さず、ひたすら謝りながら逃げてきた。そろそろ他の気の荒い連中が俺を脅しに来そうな気もする、今は岡田さんが抑えててくれるけど。 結局、勧誘は三年の春まで続いた。野球部は県大会のいいところまでは行ったんだけど結局一度も全国大会には行けなかった。そのたびにいろんな人から嫌味を言われたけど「じゃあ生活を一生保障してくれますか」と言うと誰も文句を言わなくなった。最初からこう言っておけば良かったな。高木とは付き合うこともないままフェイドアウトしてしまったのが一番の心残りだけど、野球をしない俺に興味がないのなら未練なんか無いや。いや、ちょっとあるけど。 大学に入ってからも、野球部が噂を聞きつけて誘いに来たが、こちらも断固として断りつづけたら、最初からあまり信用はしてなかったらしく二度と勧誘にはこなかった。やはり実際に球を見てない人が相手だとこっちも楽だな。これでやっと魔球から開放されそうだ。せっかく作った魔球が日の目を見れないのはちょっと可哀想だなと思うけど、そもそも高木の気を引こうとして作った魔球だ。もう出番はないだろう。 と思ったら今度はプロが破格の条件で誘いに来た。プロ入りした岡田さんがチームのスカウト部門を焚きつけてしまったのだ。なんてしつこい人なんだろう。とは言え俺も馬鹿だった。酔って気が大きくなったせいで、魔球の威力を偵察にきたプロのスカウトだとは知らずにうっかりあの球を投げてしまったのだ。さすがにプロのスカウトは巧妙で、俺に体力が無い事を充分に知ってて「チームの練習に参加しなくて良い」「一試合に最大で1イニング以上投げる必要はない」と俺にも呑むことができそうな条件を付けてきた。岡田さんも「君の夢を実現するために、ちょっと遠回りして資金を稼ぐと思えば良いじゃないか」と説得にきた。プロになっても岡田さんは相変わらず真面目だなあ。 もう俺も限界かも。メディアに直結したプロ集団と一個人じゃ勝負にならない。これ以上断り続けたら悪者として世間に晒されるかもしれない。俺は入団する代わりにそのチームのリリーフエースの年俸の10%に相当する金額にインセンティブを付けるという条件で、三島という若手投手に投げ方を伝授することにした。どうせ2、3年もしたら打ち方も研究されて価値はなくなるだろう。投げ方だってそのうち盗まれるに決まってる。 あれから5年、俺が投げ方を教えた三島投手は今や球界を代表するクローザーとなり毎年リリーフ記録を更新している。きっと自分なりにいろいろ工夫して磨きをかけて来たのだろう、もうあの球は彼の物だ。ちょっと意地悪して他のチームの投手にも投げ方を教えてやろうかと思うこともあるけど、それも大人げないしな。それに俺は俺であのときの報酬を元手に仕事を始めて順調に暮らしてるんだ。 その三島投手が何でも随分と綺麗な女性と結婚したらしい。さすがに、こんなときはちょっと羨ましいと思う。おっ、テレビでもそのニュースをやってるぞ。さすが世界のクローザー三島、すごい美人を見つけたなあ。…って畜生、高木だよ。
6月、今年最初の虫弾警報が出た。ほとんどの市民は既に半月前から強化タイヤに履き替え、保護ネットを取り付けた車に乗っていたので、さほど混乱も無いものの嫌な季節がやってきたことに変わりは無く、緊張感とあきらめが街を覆っている。外を歩く人もほとんど居ない。たまに居るのはのろのろと歩き回っている重装備の警察官くらいのものだ。車から乗り降りするときにうっかりと虫弾にやられた人が倒れていないか街をパトロールするのが彼らの重要な仕事だ。どうやら虫弾当番は新人の役割らしくみな一様に慣れない動作で、不機嫌な顔をしている。
虫弾は黒くて異常に固い殻を持つ大きさが5mm-10mmの甲虫の一種だ。一度聞いたら二度と思い出せないような正式名称も付いているのだが、その名前で呼ぶ人は居ない。そしてこの虫弾、通常6月中旬から8月にかけて地上30cmから120cmくらいの範囲を時速100km以上の速さで飛ぶという迷惑な習性を持っている。連中は前を全く見てないのか、行く手をふさがれても止まったり除けたりするということを一切行わない。飛んでる姿を肉眼で捉えることはまず不可能と言っていいだろう。もちろん石のように固い物が高速でぶつかって、場合によっては体を貫通するのだから痛くないわけは無い。拳銃の弾丸と虫弾の両方に足を撃たれた事があるという物騒で不幸な体験をした男によると着弾のショックだけなら拳銃の方がはるかに大きく、虫弾は小口径の拳銃で遠くから撃たれたくらいの威力だと言う ただ、虫弾の本当の恐ろしさはこれだけではない。この虫の体液は、人間には神経毒として作用するため、体に入っておよそ1分後にとてつもない痛みがやってくるのだ。子供の場合、背が低いこともあって頭や心臓に当たることもあり着弾の威力だけで命を落とすことも珍しくはないのだが、それでも神経毒の傷みを知っている人は、着弾のショックで即死した人の方がまだ幸運だと言う。腿を貫通した瞬間ですら気絶しそうな痛みなのに、その後襲ってくる体液毒による痛みで気絶することすらできない。痛みは3日ほど持続するため、耐え切れず自ら命を絶ったり、暴れ過ぎて頭を打ち死亡してしまうケースも少なくはない。 虫弾は10年ほど前からこの街で発生したと言われている。最初の発生が確認されてから2年後にカナダの田舎町で、更に次の年にニュージーランドでと全部で6つの地域で虫弾が発生が確認されている。なぜ急に発生したかはまだ解っていない。突然変異の新しい甲虫であるという説と、環境の変化により以前から居る虫の隠れた習性が現れたという2つの説が今のところ有力だ。何せ虫弾は捕獲しようとしても自らの勢いで潰れてしまうので飼って観察することができないため、その習性がほとんど解っていないのだ。それでも毒の成分や行動を起こす条件は少しずつ明らかになって来ている。特に気候と日照時間に密接な関係があるという事が解ってからはかなり正確に発生を予想できるようになった。虫弾警報が発令できるようになったのもそのおかげと言って良いだろう。 珍しく大勢の人が外を歩いている。全員が警官以上の重装備で身を守っているのだが、警官と違ってどこか浮かれた印象を与える集団だ。先頭の人が持っているプラカードにはその一行を連れて来た旅行代理店の名前が隣の国の言葉で書いてあった。今年から虫弾を体験するというツアーが隣国で企画され、先週あたりから少しずつ観光客が訪れ始めたのだ。虫弾の被害に悩む市民の中からは不謹慎なので止めてもらいたいという声も上がったが、ここ数年初夏の観光シーズンが事実上消滅していた事もあり、背に腹は変えられないと一応は歓迎されている。観光好きな隣国の人たちは、多くの観光収入をもたらしてくれるからだ。 虫弾体験ツアーの一行は防護服への着弾のショックに驚いたり、強化アクリルカバーで頭を覆い、文字通り目の前まで飛んでくる虫弾の恐怖を楽しんでいた。そんな中、観光客の一人が防御服の上から肩に掛けていたかばんの中身を道路にぶちまけてしまった。どうやら留め金に虫弾が命中したらしい。この街の人なら誰でも知っている「荷物をむき出しにして歩くのは危険だ」という常識を旅行代理店は徹底していなかったのかもしれない。次の瞬間、爆音と共に黒く濃い霧が猛スピードで観光客を襲った。今まで誰も見たことがない規模の虫弾の群れだ。どの虫も荷物がこぼれたあたりに向っている。防御服に守られてるとはいえ無数に飛んでくる虫弾が相手ではいつまで持つか解らない。観光客は恐怖に駆られ重い防護服でどたどたとバスに向うものの、転んだ際に手袋が脱げて手のひらに穴が開いた者や、うっかり頭の覆いを外してしまったために苦しむことなく亡くなる者もいる。結局、無傷でバスに戻ることが出来たのは20人中14名、着弾した6名のうち2名はその場で息絶えた。 虫弾の異常発生が収まった後、虫弾のターゲットとなった場所には虫弾の死骸で出来た高さ80cmほどの小山が残されていた。小山を書き分け虫弾の中心にあるものを探ってみると、そこには香水の瓶が発見された。隣国で発売されたばかりのその香水に含まれる成分が虫弾を強烈に引き寄せるようだ。直ちに虫弾をおびき寄せるためにその香水を取り寄せたところその効果は素晴らしく、わずかな量で数多くの虫弾を引き寄せることが判明した。この効果を利用して警報が発令された日にあちこちで同時に香水を塗りつけた金属板を置いただけで何百万匹もの虫弾を始末することができた。これを何度か繰り返すと虫弾の発生量は目に見えて減っていった。このまま行けば来年中には撲滅も不可能ではないとまで言われるようになり、沈みがちだった街にも活気が戻ってきた。 虫弾の大量の死骸はこれまでと同様に埋立地に捨てられた。体液の毒が環境に与える影響を心配する声もあったが、人間以外の生き物に与える効果が発見されていないことと、土壌にしみこんだ場合もすぐに中和され人体への害がなくなるという実験結果を理由に押し切られてしまった。山に捨てて飲み水が汚染されることに比べればましという理由でそれ以上反対する人も少なかった。 異変はその年の秋に始まった。虫弾の死骸を好んで食べる鳩が大量に発生したのだ。しかも虫弾の死骸を食べた鳩は虫弾と同様にとてつもない速さで上から飛んでくるという厄介な習性を持ってしまった。もちろん当たったときの被害は虫の比ではない。性質の悪い事に鳩はその街だけではなく瞬く間に世界中に被害をもたらした。それだけではない、鳥弾化した鳩の糞には虫弾の卵がしっかりと生きていたため、鳩により虫弾の卵は世界中にばら撒かれたのだ。鳩がばら撒いた卵から孵った虫弾は確実に生息地を広げ街を襲い、虫弾の死骸を食べた鳩もまた鳥弾となり街を襲った。 もう世界中どこに行っても屋外に安全な場所はない。人々は地下や屋内で植物を育て細々と命をつないで行くしかなかった。絶望に覆われた世界に非情な最後の一撃が待っていた。地面や人に激突して死んだ鳩を食べた鼠までもが高速で走る鼠弾となり街を襲い始めたのだ。もはや地下も室内も安全ではない。本当の絶望は始まったばかりだ。
「こんにちは。私はタイムトラベラーです」
ああ、どうしてこの店には変な奴ばかりやって来るんだろう。今日のこいつなんか特に危ないぞ、目つきも何だか変だし。だいたい何だよ、よりによってタイムトラベラーってのは。 「あ、私がイカレた人だと思ってますね。みんな同じ反応をするんだ。昔の人って素朴で面白いなあ」 いやだ、いやだ、いやだ、どうしてこんな奴の相手をして貴重な時間を無駄に過ごさなくてはいけないんだ。店番なんか引き受けるんじゃなかった。どうせバイト代なんかくれないんだし断れば良かった。 「私は、はるか未来から来たんですよ。ほら」 そういって危ない人は、昔の漫画に出てきそうな未来風デザインの時計を差し出した。しかもでかくてアナログじゃん。その時計のカレンダーには2003年て書いてある。 「ふーん未来からねえ、ってそれ今年じゃない」 しまった思わず突っ込んでしまったよ、悪い癖だ。どうして私はこんな危ない人を相手にしたときまで笑いを取ろうとするのだろう。 「あれ、行き先間違ったかな?今何年?」 「だから2003年だって。」 もう完全に危ない人ペースで話は進んでる。もういいや、どうせ暇なんだし、この人も危害を加えるつもりも無さそうだからつきあうよ。 「そんなはずはないよ。2003年って何暦で?」 「何暦って言われても、いわゆる西暦だけど」 「西暦ってグレゴリオ暦のこと?ひょっとして」 「あ、それそれ」 「うわあ、何を間違ったんだろう。全然違うところに付いたよ。怒られんだろうなあ」 やばい、演技に引き込まれつつあるぞ。どこに行きたかったと言う設定なんだろう?気になるなあ。 「てことは、ええと」 電卓を取り出しながら計算し始めた。何で電卓なんだよ。とにかく突っ込みどころが多くて飽きさせない人だ。 「紀元前342年かあ、凄いなあ。原始人じゃん」 原始人とは失礼な奴だと思ったけど、反応が見たくなってちょっとふざけてみた。 「そう、原始人です。うっほ、うっほ」 「うひゃひゃひゃ、原始人だ原始人だ」 危ない人は笑い転げている。こんなに受けるとは思わなかった。 「てことは、この原始人の私の使ってるグレゴリオ暦からみると、あんたは4348年から来たってこと?」 「え?そうかな、ちょっと待って」 また電卓を叩き始めた。 「すごいな、原始人て暗算が得意なんだ。自分で計算しなきゃいけないからな。でも1年違ってたよ。多分、紀元0年を入れ忘れてるんだろうけど」 どうやらこいつらの暦には0年があるという設定らしい。 「悪かったな、こっちの暦では紀元1年の前の年は紀元前1年なんだよ」 「あ、やっぱそうなんだ。古代史で習ったもん。そういう非合理的なシステムってあこがれちゃうな」 電卓を叩かないと簡単な足し算もできない奴に数字の合理性についてコメントされたくない。 「ところでそのタイムトラベラー君は、こんなところに何しに来たの?」 「いや、ただの観光ていうか本当はパックのツアーはずなんだけど、はぐれちゃったんだよね」 危ない人にありがちなご都合主義だ。ここに来た経緯と話がつながって無いじゃん。そろそろ相手をするのも疲れてきたので追い返すとするか。 「それは気の毒だと思うんだけど、私は原始人なんであなたのお役に立てそうもないよ。帰ってくれないかな」 「それもそうだね。でも昔の人と話ができて楽しかったよ」 思ったよりすんなり帰って行った。ここには変な奴がたくさん来るけど、今日のは群を抜いて変な奴だったなあ。 「どうでしたか?例の…」 「全然変化なし。相変わらず歴史の世界に閉じこもってるな。でもひとつ発見があったよ」 「へえ、どんな?」 「ただ闇雲に古い時代じゃなくて、今がグレゴリオ暦で2003年だっと思ってる。数字だけ合ってるってことだね。この辺が鍵じゃないかな」 後にグレゴリオ症候群と呼ばれる疾患の存在は、このような経緯で確認されたと言われている。
トゥルルルル トゥルルルル トゥルルルル
8, 9, 10。 うーん出ないな。どっか出かけてるのかなあ。でも午前3時に出かけてるってのも変な話だな。家に居ると思うんだけどなあ。 トゥルルルル トゥルルルル トゥルルルル 28, 29, 30。 もう寝てるのかもしれない。明日は出張だから5時起きのはずだし。きっと寝てるんだろう。寝てるときに電話するのもまずいか。家族の人も朝が早い仕事のようだし、これ以上鳴らすと迷惑がかかるかもしれないな。マナー違反になる前にそろそろ切った方が良いかも。 トゥルルルル トゥルルルル トゥルルルル 58, 59, 60。 もしかしたら今出ようとしてるところかもしれないぞ。大急ぎで電話機に向ってる途中だよきっと。だったらここで切るのも何だか悪いなあ。意地悪してるみたいだ。もうちょっとだけ待って見るか。 トゥルルルル トゥルルルル トゥルルルル 98, 99, 100。 あ、確か弟さんが受験生なんだよな。今でも受験生って深夜放送聴いてるのかな。聴取者が参加するコーナーに葉書を書いたりしてるかも知れない。ラジオ局からかかってきた電話だと思って弟さんが出たらちょっと嫌だな。何て言おう「始めまして、未来の義理の兄です」と言ったら引くかな。 トゥルルルル トゥルルルル トゥルルルル 148, 149, 150。 さすがにそろそろ切らないと迷惑がかかるかもしれない。家族に迷惑かけると、弓子さんに嫌われるかな。でも僕だって夜中に眠れなくて大変なんだし、話相手が欲しい時だってあるんだから家族の人もちょっとは我慢してもらわないとね。これって、ちょっと自分勝手なのかなあ。 トゥルルルル トゥルルルル トゥルルルル 198, 199, 200。 じゃあ今日も300まで待って出なかったら諦めよう。話が出来なかったのは残念だけど、弓子さんと弓子さんの家族のことをいろいろ想像するのは楽しかったな。弓子さんだって僕が深夜でも弓子さんのことを考えてるって知ったら嬉しい筈だよ。 トゥルルルル トゥルルルル トゥルルルル 278, 279, 280。 ふう、今日も駄目かもしれないな。最近つながらない事が多いし。まあ良いさ、明日は新幹線のホームでも出張先の駅でも昼ごはんのときにも、とにかくいろんな場所で弓子さんを見ることが出来るんだ。と思ったらこんな時間だ、僕も明日は5時に起きなくちゃ。今日の「弓子さん観察日記」を書いて弓子さんに送ったら寝るとしよう。298, 299, 300。 ガチャン
「つまり、佐々木常務は会長派から全面協力とは行かないまでも、ある程度のバックアップを受けたい訳です」
「ふうん、ある程度ねえ」 「三村様もご存知かとは思いますが、会長派は一応常に中立である事が売りというか存在理由みたいなものですから、露骨に常務の味方をする訳には行かないのです」 「なるほどねえ」 「ところが、それだと面白くないのがメ研です。連中はとにかく外からの注目を浴びてますからとにかく声が大きい。それが正論である場合も多いのですが周りが彼らについて行けない事が多く軋轢が生じ始めています」 「確かメ研の連中って若いんだよね?」 「ええ、平均年齢は30後半です。確かにメンバは若いのですが、それを束ねる御大吉川氏が彼らをわざと自由に発言させているきらいがあります」 「あ、まだあの爺さんの影響力ってまだ大きいんだ」 「影響力どころか現役バリバリで成果を出されてますので、一度へそを曲げると厄介なのです」 「元気な爺さんだなあ」 「佐々木常務としては、吉川氏にはフロントラインで良い物を作る出してるだけの人であって欲しい訳です」 「なんか嫌な人なんじゃないの?その佐々木常務って人」 「そう言ってしまえば元も子も無いのですが、会長もその辺を充分ご承知で、どちらかと言えば汚れ役を佐々木常務に押し付けて吉川氏を汚い部分から遠ざけたいという意向がおありのようです」 「あ、すでに会長が噛んでるの」 「もちろんです。私も会長のご指示で動いております」 「そうか、田中君は今は会長に直付きなんだったね。ごめんね最近その辺の事情に疎くって」 「いいえ、私の説明不足です。申し訳ございません」 「会長の意向とあっては断るわけには行かないな。田中君の言うとおりにするよ。で、どうすればいいの?」 「恐れ入ります。三村様は相談役という立場上、あからさまに佐々木常務に肩入れして頂くわけにも行きませんので、会長派を常務サイドに向うよう後押しするというよりは、佐々木常務と会長派の間に信頼関係が既に築かれているという雰囲気を広めるのにご協力いただきたいのです」 「なるほど」 「そこで、三村様には会長とのラインが今でも健在であることをそれとなくアピールしていただくとともにメ研の動向については組織としてではなくプロダクツとして関心を持っていることを表明していただき、また佐々木常務に関しては好感を持っているように振舞って頂くようお願いしたいのですが」 「了解、そうさせてもらうよ」 「ありがとうございます。三村様にご協力いただけるとこちらと致しましても大変に助かります。それでは失礼致します」 「おーい、木村ぁ。今の聞いてただろ?結局俺は何をどうすれば良いんだ?」 「明日の朝食会で会長と佐々木常務の間に座ってにこやかにしていてください。あとは田中さんがメ研の話題を振りますので『そうだね』って言えば良いですから」
時々左足だけが短くなっている夢をみる。どんどん短くなるといった不思議な現象の夢ではなく、最初から左足の短い自分が出てくる夢だ。夢の中の私は昔からそうなのか、左足が短いということを当たり前のこととして受け入れているようだ。
短いといっても、日常生活に支障がある訳ではない。夢の中なので正確には把握できないが、おそらく4から5cmといったところだろう。夢の中の私は普通に立っているときに右足の膝をいつも軽く曲げている。歩くときは、いつも少し体を傾けている。ちょっとぼんやりして歩くとどんどん左に曲がってしまうのでいつも正面を見て歩くようにしている。夢の中の私は日常生活には全然支障はないけど、ちょっと不自由な体を巧く操りながらなんとか暮らしているようだ。 不思議だなと思うのは、左足が短いことで夢の中の私が感じてる少し不自由な感触を私が実感できているという事だ。夢の中で感じた、左足だけ少し背伸びする感触、曲げながら体重を支えるので右足の前腿が疲れる感触、小走りするときのスタッカートの感触などなど実際にそうなって見なければ解らないんじゃないかということまでリアルに覚えているのだ。 ひょっとしたら夢の中の私が本物かもしれないなどと子供じみた妄想が浮かんだ。少し照れくさい。仮にそうだとしても、今両足の長さが等しいこともしっかりとリアルに実感しているのだから問題は解決していないのだ。 一方、夢の中の自分が持つ左足が短いという感触がリアルであるという保障はどこにもないのだということに気付いた。勝手にリアルな感触だと思っているだけで、実際には全然違うのかもしれない。左足が短いということを経験したことがあるわけでもないのだ。 本当にリアルな感触なのか気になるので、左足を4cmほど短くしてみた。短くしてみて解ったが、夢の中で感じた感触はやはり正しかった。初めて体験した気がしない、それくらいリアルな感触だったのだ。夢と言うのは不思議なものだと思う。 左足が短くなっている夢も見なくなった。
ワタナベ先生が壊れた。僕のクラスは学級崩壊なので先生はそのことを毎日悩んでいたのだ。だから先生は壊れたに違いない。ワタナベ先生が壊れた時はみんなはどうして良いか解らなくなった。こんなときだけ女子は「先生がこんな風になったのは、あなたたちのせいだ」なんて言う。自分たちだって学級崩壊をやってたじゃないかと文句を言うと「私たちはそんなにやってない、私たちのせいじゃない」とか言い出す。そうやって喧嘩をしている間にも先生は黒板にみんなの似顔絵を描いたり、水槽のメダカの数を数えたり、タカシ君のドリルに勝手に答えを書いたりしている。
喧嘩なんかしてる場合じゃない。アベ先生に言いに行こうとクワノが言った。アベ先生は僕のクラスと隣のクラスの副担任だ。何しに来てるのか解らない先生だ。アベ先生に言ってもワタナベ先生が元に戻るとは思わないけど、誰かに言わなければいけない。するとコニシが、アベ先生に言ったらどうしてワタナベ先生が壊れたのか聞かれるぞと言った。それは困る、僕達のせいにされるに決まってる。それだけは嫌だ。みんなで相談した結果このままにしようということになった。どうせ授業はやってなかったんだし、先生が壊れても僕たちが教室ですることはおんなじだ。頭の良いヨシダは職員室に戻ったらばれるんだから隠さない方が良いと言ったけど、みんなはそのときはそのときだと反対した。 みんなの考えは正しかった。ワタナベ先生が壊れてから一週間たったけどまだばれていない。先生は壊れたままだし僕のクラスは学級崩壊したままだ。どうしてばれてないのか、誰にも解らなかった。他の先生に聞いたらばれそうな気がしたので聞くこともできなかった。ある日ヨシダが変なことを言い出した。先生は壊れたふりをしてるだけなんじゃないかというのだ。学級崩壊が嫌になって壊れたふりをしたらみんな静かになるんじゃないかと思って壊れたふりをしてるんだと。でも僕らのクラスは先生が壊れたあとも学級崩壊をしたままなんだからこのまま壊れ続けてるのはおかしいと僕が言うとクワノは大人は引っ込みがつかなくなるときがあるんだと言う。良くわからないけど恥ずかしくていまさら止めるわけにいかないということらしい。 どうしてワタナベ先生が壊れたことがばれていないか解った。実はもうばれていたのだ。職員室でもワタナベ先生は壊れてたんだけど先生方もワタナベ先生を学級崩壊のことで毎日いじめていたのでそのせいで壊れたと思って、見てみぬふりをしていたらしい。僕らがわざと黙っていることも知っていたみたいだ。それだけじゃない、ワタナベ先生以外にも壊れてる先生がたくさんいて、それもみんな見てみぬふりをしているらしい。そう言えば僕らのクラスも半分くらいは壊れてるし、僕のうちも兄ちゃんと婆ちゃんと犬のジョンと知らないおじさんが壊れてる。僕ももうちょっとで壊れるのだと思う。
「ペンギンにも人権を」と主張するホームページを作った。もちろん冗談で作ったのだけど、こういう冗談はふざけてやっても面白くないので、デザインも文言も慎重に検討して、あたかも本気で真面目で切実に「ペンギンにも人権を」と主張しているかのように書いた。可愛らしいマスコットキャラクタも作った。
ありがたいことに雑誌で紹介されたり、いろいろなところからリンクされて多くの人が僕の作ったホームページを見にきてくれているようになり、メールもたくさんの届いた。「面白い最高だ」と言ってくれるとやはり嬉しい。中には「もっと冗談だと解るように書けば良いですよ」という助言もあったけど、そういう人のホームページは大抵つまらなかった。驚いたのは「ペンギンに人権なんかあるわけないだろ、馬鹿」という意見が意外と多かったことだ。中には人権について真面目な講釈を書いてくる人までいた。僕より暇な人が大勢居るって事かもしれない。冗談というのはなかなか難しいものだ。 そのうちもっと驚くメールが届いた。「ご意見に感銘しました。私も微力ながらお手伝いさせてください」というものだ。最初はもちろん冗談だと思った。なかなかセンスのある人だとすら思った。そのうち同じ人から「支部を作りましたリンクしてください」「動物園に抗議に行きました」というメールが来るようになり初めてこの人が本気だということに気づいた。本気にするのは勝手だが、行動に出られると僕のホームページが原因だと言われるかもしれない。何か対策をしなければ。 信じられないことに「ペンギンにも人権を」に同調する人は日増しに増えている。いつの間にか数ヶ国語に翻訳され、海外にも支部ができているらしい。毎日ものすごい数のメールが世界中から届くようになったが、もう誰も僕のページを面白いとは言ってくれない。「ペンギンにも人権を」に賛同する人と反対する人のメールしか来ないのだ。僕は怖くなってホームページを閉鎖した。メールアドレスも削除したのでもう馬鹿騒ぎに巻き込まれることはないだろう。 確かに僕は馬鹿騒ぎの中心から逃れることができた。でも、既にそんなことはどうでも良い段階になっていたらしく「ペンギンにも人権を」運動は世界的な規模で着実に参加者を増やしている。閉鎖した僕のホームページも既にバイブルと化していて複製があちこちに置かれている。マスコミも最初は頭のおかしい人たちの変な運動として扱っていたが、運動が大きくなるにつれ同調するようになってきた。何かが狂っている。 ついに幾つかの国でペンギンに人権が認められてしまった。数年以内にすべての国で認められるようになるだろうと言われている。南極を独立国にしてペンギンのための国家を作ろうという運動も起きている。「ペンギンにも人権を」運動発祥の地であるこの国でも法整備が急ピッチで進められていて、事実上ペンギンは市民として扱われている。ペンギンはもう人なのだ。 ときどき、あのページを作ったのは僕なんですとカミングアウトしようかという衝動に駆られることがある。カリスマ扱いされるだろうか、それとも余計なことしやがってと袋叩きに会うか。いや多分、嘘だと思われるだけだろう。
料理をするロボットを作った。故障した。
修理したが失敗した。ロボットは限りなく料理を作り続けるようになった。 やがて冷蔵庫が空になった。ロボットは外に飛び出した。 隣の家のドアを破壊し、進入し、奥さんを押し除け料理を始めた。 やはり冷蔵庫が空になるまで料理を作り続けた。 マンションのすべての冷蔵庫が空になり3000人前のおいしい料理が残った。 ロボットは場所を変えて次々と料理を作り続けた。 料理はたくさんあるが食べきれない。保存してもロボットが見つけて焼却。 ご都合主義の設定で悪いがこのロボットは最強の戦闘能力も持っている。 誰も止めることができない。 更にご都合主義。 そのロボットの自己修復能力が暴走し、自らのコピーを作り始めた。 世界中にそのロボットのコピーが広まっていった。 あれから3年、ロボット達はまだ料理を作り続けている。 ご都合主義的な事情があって誰も止められなかったのだ。 材料がどこにも見つからなくなるとロボットは自ら材料を調達し始めた。 畑から野菜を抜き、動物を捕らえ、海をさらい、鳥を撃ち落し、虫を穿り返した。 それも尽きるとまあ予想通りお約束の結末が待っていた。 困ったことにこれが結構いける。
資産家の老人が自宅で殺害された。
当日、家にいた人たちのアリバイはどれも曖昧だった。 誰が犯人でもおかしくない状況の中、捜査は難航すると思われた。 事件の翌日、容疑者の中の特に怪しい3人が次々と自首してきた。 どの容疑者の証言も現場の状況と矛盾はなく、誰かを庇っている様子もない。 そして、それぞれもっともらしい動機を語っている。 捜査に行き詰った蟹丸警部は家に帰り息子に事件の事を話した。 (推理作家だか何だか知らないけど、事件の捜査過程を一般人に話して良いのかという疑問は忘れて欲しい) 「解りました、父さん。僕がその3人と麻雀をしてみましょう」 「そんなことで犯人が解るのか?」 「ええ、多分大丈夫です」 翌日、自首してきた3人の容疑者と蟹丸警部の息子の4人で麻雀が行われた。 結果は息子の一人勝ちで、3人の容疑者から大金を巻き上げた。 「それで犯人はわかったのか?」 「もちろんです。犯人は一番負けたやつです」 蟹丸警部は根拠を求めたが、息子は頑として答えなかった。 「まずは、他の2人に証言が嘘だと解ったら、どういう罪に問われるのかをじっくりと説明してあげてください。多少誇張しても構いません」 脅しならお手の物だと蟹丸警部は息子の言うとおりにした。 2人は泣きながら自分の証言が嘘であることを認めた。 「そろそろ種明かしをしてくれても良いだろう?」蟹丸警部は息子に尋ねた。 「この事件は犯人じゃない2人を当てるのがポイントだったんだろう?」 「まあ良いじゃないですか。事件は解決したのですから」 息子は相変わらず、その根拠を語ろうとはしなかった。 もちろん息子はあてずっぽうで言っただけで、最初から麻雀が目的だった。 こいつらなら事件で動揺してるから良いカモだと思ったのだ。
あの日、天からの啓示を受けて僕は殺し屋になることにした。なぜ殺し屋なのかは解らない。ただ、僕には殺し屋の才能があるらしいという点には薄々気付いていた。だからって殺し屋になれと言うのも何だか安易で不条理な啓示だなあと思ったが、啓示というのは大抵不条理なものなのでその点については深く追求しないことにしている。そういえば以前、うっかり知人に「俺って殺し屋の才能があるみたいなんだけど、使い道無くって」 と漏らしたら 「それはどんな才能なんだ?それが殺し屋の才能だと何故わかったのだ?」 としつこく絡まれた事がある。面倒なので殺した。そのときはなんて無駄な才能だろうと思ったのだけど、殺し屋になってしまえばこの才能も無駄じゃなくなるってわけだ。
ところが、さあ殺し屋さんを開業するぞと思ってみたものの早くもこの職業には重大な欠陥があることに気付いた。お客様からの依頼をどうやって頂けば良いのだろう?仕事の内容を明かしてしまっては後ろに手が回るし、伏せてしまっては依頼人だって殺し屋さん営業中ですって解らないじゃないか。いろいろと迷った挙句、お悩み相談所のふりをして広告を出すことにした。まず「殺したい人は居ませんか」とちょっとドキッとするキャッチで煽って「現代人を脅かすストレスが…」「話すことで悩みの8割は解決」「どんなに憎い人でも殺すなんてわけには行きませんよね(笑)」「まずはお電話で(初回ご相談無料)」といった言葉を散りばめ、気さくに相談できる雰囲気を演出してみた。世間には悩みを持っている人はたくさんいるらしく、僕の予想に反して初日からたくさんの電話がかかって来た。 大半の悩み相談は本当に殺したいほど憎んでいるとは思えないものばかりで、話を30分ほど聞いてちょっとだけアドバイスをするとほとんどの人はそれっきり二度とかかってこなかった。二回目からは有料にしたのが効いてるのかもしれない。でもごくごくたまに、そいつは殺した方が良いよと思うケースもあった(僕なら殺してるだろう)。そんなときは「あなたのストレス解消のためにその人を殺して差し上げましょうか?」と言ってみる。本気とも冗談ともとれるトーンで話すのがコツだ。そこですぐ飛びついてくる場合もあるが、2,3日後に思いつめた声でかかってくる場合もある。相手が怖がったり怒ったりした場合は誠意を込めて「冗談がきつくて申し訳ありませんでした」と謝ればそれ以上のトラブルになることはなかった。 おかげさまで仕事は繁盛している。僕は仕事が速くてミスがないし、ちょっとした軽自動車が買える程度という殺し屋さんにしては手ごろな料金も好評のようだ。最初は秘密が漏れることを心配したのだけど「秘密が漏れた場合は真っ先に依頼人を殺します。"疑わしきは罰する"が当方の基本方針ですので、ちょっとでも、疑わしいことがあれば、事実関係を調べる前に始末します。そのつもりで」と最初に釘を刺してるので今のところ依頼者が誰かに秘密を漏らしている様子はない。それに依頼者達は罪の意識が薄いらしく殺人を依頼したことをあまり気にも留めていないようだ。世も末だねと思ったけど実際に殺してるのは僕なので文句は言わないでおこう。 ところで、カモフラージュで始めた悩み相談所の方は先月から探偵事務所に鞍替えした。こちらの方が本業の依頼を取りやすいと気付いたからだ。もちろん、表向きは悩み相談の延長線上で始めた事業ということにしてある。秘密の漏洩が少し心配だったけど事務担当の助手も雇った。助手は元依頼人の一人で、弱みもたっぷり握ってる上に一度怖い目に遭わせてあるのでそう簡単に裏切られることはないだろう。毎日文句を言いながらもちゃんと働いてくれている。この小さくて商売熱心と言えない探偵事務所にも、たまに犯罪絡みの調査依頼なんてのが入ってくることがある。こちらは僕が純粋に楽しむために道楽で首を突っ込んでるのだけど、なかなか面白くて本業がおろそかになってしまいそうなのがちょっと心配だ。 そんな僕のところに持ち込まれた奇妙な事件の数々を綴った「殺し屋探偵の後悔 〜先生また依頼人殺しちゃったんですかぁ?〜」が来月からスタートします。お楽しみに。(この予告編はフィクションです)
歩行者天国の真ん中に二人の剣豪が突如として現れた。一人は道場の若い師範代といった雰囲気の知的な風貌を持ち、もう一人は在野の天才を思わせる野武士然とした初老の男だ。二人とも周囲の視線を全く意に介することなく、一礼したかと思うと剣を抜き決闘が始まった。最初は何かのイベントかと思い興味深げに二人を取り囲んでいた見物人の輪も二人の目付きや迫力に圧倒され次第に外へと広がっていった。重苦しい緊張感、焼き殺されそうな鋭い視線、やはり本当の真剣勝負は違う。あたりは静まりかえり二人の息遣いだけが聞こえていた。
決闘の雰囲気が見えなかったのか馬鹿なのかあるいはその両方であろう、見物人の輪の外から誰かが野次を飛ばした。師範代が一瞬その野次に気を取られた瞬間に野武士が師範代に斬り込んだ。師範代もわざと隙を作ったのであろう、斬りかかって来た刀をかわし野武士の脇腹を狙って水平に刀を振った。野武士は当然のようにその太刀を左脇腹で受け止め上から更に斬りつけた。無防備に見えた脇腹には防具が仕込んであったようだ。降りかかった太刀を師範代は自らの刀で防いだ。物凄い大きさの金属音が響き渡り火花が飛ぶ。 見物人はその恐ろしい勝負に惹きつけられると共に恐怖のあまり足がすくんでしまい誰一人その場から逃げることができなかった。決闘は更に続く。師範代は力を込めて野武士を跳ね飛ばした。細い体のどこにこれほどの力があるのだろうか、野武士はごろごろと5mほど後ろに転がり見物人の中に突っ込んでいった。野獣のような叫びをあげると野武士は自らを鼓舞するかのように刀を二度三度と振り回す。刀に当たった見物人が三人声も立てることなく倒れた。師範代はその隙を見逃さず野武士を突き刺すかのように直進したが、直前でかわされてそのまま見物人に向って突き進んでいった。綺麗に串刺しになった二人の見物人から刀を抜こうと師範代がもたついている間に野武士は後ろに回りこみ、低く飛び上がったかと思うと真下に向って斬りかかる。師範代は一度刀から手を離し見物人の襟首をつかみ野武士に投げつけた。 サイレンが聞こえた。誰かが通報したようだ。見物人たちはここで初めて我に返りその場から狂ったように逃げ出した。ポリカーボネートの盾で身を固め銃で武装した警官が剣豪達を取り囲んだ。二人には警官の姿や拡声器から聞こえてくる警告を無視して勝負を続けている。ついに警官隊は剣豪達の足を狙って発砲した。野武士を狙った弾は左足の太ももを貫通したが、師範代を狙った弾は逸れ二発目が撃たれる前にうずくまる野武士の首を師範代が刎ね落とした。警官隊は再度師範代の足を狙って発砲した。今度は失敗することなく師範代はその場に崩れ落ち警官隊によって捕らえられた。 師範代は警察の取調べに対して一切口を開かなかった。また師範代、野武士共に身元を示すものは何一つ身につけている筈もなく、死者九名、重軽傷者十四名を出したこの真昼の決闘の真相を知ることは誰もできなかった。テレビや雑誌では色々な人が彼らの正体を推測し、勝手な予想をしていた。「狂信的なカルト教団の信者説」「現実と仮想世界の区別が付かないゲーム型の犯罪者説」「剣の道を究めすぎておかしくなった人たち説」「催眠術で操られた人たち説」などがテレビやネットで飛び交い、中には「タイムスリップ説」「レプリカント説」を唱える人まで現れ始めた。 真昼の決闘への関心が薄れ始め、各地で中止されていた歩行者天国も再開し人々が別の事件に興味を持ち始めた頃、再び剣豪達が現れた。剣豪達の風貌は前回とは違っていたが、周囲を全く気にせずに決闘に没入する点や捉えられても口を開かない点に変わりは無かった。その後も剣豪達は次々と現れ、出現頻度は高くなり出現場所は全国へと広がっていった。政府は市民の安全を守るために剣豪達を人間と見做さないという法案を可決した。この法案により警察や民間人は剣豪に対して何をしても構わない事が保障された。 何をしても構わないと保障されたとは言え、市民が剣豪より強くなった訳ではない。それでも人々は気が大きくなり集団で剣豪を退治するしようという機運が高まり始めた。最初は敵討ちのためや自分の家族を守るためといった動機が強かったが、そのうち命がけのゲームとして剣豪を倒そうという人が増え始めた。剣豪を退治する事は法律で許可されているが、街中で猟銃や刀剣を使うのはもちろん処罰の対象となるため、剣豪を退治する際はもっぱら集団で丈夫な盾やネットを使って剣豪を取り囲み体の自由を奪ってから棒で殴り倒すという方法が取られた。真剣を持った剣豪達の強さは桁違いだが彼らは自分達の勝負以外は眼中にないため、勝負をじっくりと見て隙を突けば一般人でも剣豪達を捕らえることは不可能ではなかった。 剣豪退治は次第に剣豪狩りと呼ばれ、今ではスポーツとして定着している。安全に捕らえる方法が確立したため出現と同時に眠らせて刀を安全なものに取り替えて決闘させることが可能になり、ジュニアの愛好者も増えている。また海外からも競技を楽しもうと来日する人も多く立派な観光資源となっている。昨年より無傷のまま生け捕りにした剣豪を眠らせて海外に輸出することが認められ、輸出資源としての利用方法にも注目され始めた。海外では剣豪狩りだけではなくコロッセウムで戦わせて勝敗を予想する剣豪トトカルチョも行われている。 このように剣豪は戦って死ぬことで多くの人に役に立っている。まさに武士道とは死ぬことと見つけたりと言ったところか。
「お、お前は5年前私がまだ17歳で県立高校に通うしがない高校生だった頃、平凡なサラリーマンの父が同僚と上司の悪口を言いながらやけ酒を飲んでた居酒屋を爆破したナイフ使いの名手にして格闘のプロ、自称左右両翼ゲリラの黒虎こと黒木雅虎だな!」
「いかにも俺はハーバード大学に15歳で入学し天才の名をほしいままにしたものの刺激を求めて裏の世界に飛び込み今では裏世界で支配的立場を手に入れようとしているナイフ使いの名手にして格闘のプロで左右両翼ゲリラの黒虎こと黒木雅虎だ」 「貴様の歪んだ醜い野望のせいで、歴史と音楽が苦手で英語と美術が得意なしがない高校生だった俺は、平凡な商社に勤める日本ハムファンでかたせ梨乃が好きだった父親を失い、奨学金を貰いながらも駅前にある酔っ払い客が多くて弁当を従業員が毎日持ち帰る汚いコンビニでバイトをしながら、苦労して中堅どころの国立大学の文学部英米文学科を優秀な成績でこの春卒業する破目になったんだぞ!」 「それがどうした。薄汚い大衆どもが苦痛に顔を歪める姿を見たいという歪んだ欲望のためには、女の子と話すと緊張して何言ってるか解らなくなるもてない高校生やクマッターズという腐った名前の草野球チームで7番レフトのサラリーマンがどうなろうと知ったことではない。俺は今、中国最大の商工業都市上海で2001年3月26日から進めていた狡猾で汚い計画が苦労の末やっと成功したという知らせを俺の片腕とも言える優秀な部下から先週買い換えたJ-Phone改めボーダフォンの携帯で聞いたばかりで機嫌が良いんだ。黙って見逃してやるから、運行本数の少ない東豊線に乗って築5年で恥ずかしい名前のワンルームマンションに帰りな」 「そうは行くか。ブリジストン製3段変速の自転車で30分かけて県立高校に通うしがない高校生のころに、バスとJRと南北線を乗り継いで平凡な商社に通う父親が自称左右両翼ゲリラの黒虎こと黒木雅虎に殺された無念を晴らすべく、中堅どころの国立大学で18世紀の英文学を学ぶ傍ら、北陸地方の山奥にある名前を言うわけには行かないがある省庁直属のこれまた名前を言うわけには行かない機関に入り、性格の悪い40代後半のグリーンベレー上がりと称する角刈りの教官の厳しい訓練に耐え、ナイフや銃器はもちろん爆発物の扱い方のエキスパートになり、対テロリスト専門の特殊部隊のメンバーとなったのだ」 「何、すると貴様あの湾岸戦争でも影で暗躍していた、性格の悪くて角刈りが似合ってないグリーンベレー上がりの通称ガラガラ蛇こと唐木熊雄の弟子か。面白い、奴にナイフの使い方を教えたのは、週末には会員制高級テニスクラブでウィンブルドンを制したプロを相手に互角の勝負をする左右両翼ゲリラの黒虎こと黒木雅虎だ。音楽が苦手で英語と美術が得意で将棋部に半年だけ所属していたしがない高校生だったお前にこの俺が倒せるかな?」 デビュー作「静かだが知的とはお世辞にも言えない俺達は回りくどい説明が多すぎるかもしれないが、これを読んでいる君はどう思う?」が第32回講文舎坂之上田村麻呂賞を受賞した、新進気鋭の美人作家の樋口三葉虫が原作を書いている、先週から毎週金曜の午後9時から13回放送の予定で始まった「しがない高校生だった俺は平凡な商社に勤める父親の無念を晴らすべく格闘技のプロにしてナイフ使いの名手の黒虎を倒す」と言うテレビ東洋のドラマは面白いなあ。
地面に四角い穴が開いている、一辺が3メートルくらいの正方形の穴だ。僕は穴の傍に這いつくばって中を覗き込んだ。穴の深さはどのくらいあるのか判らない。底が見えないので10メートル以上は楽にあるだろう。試しに石ころを転がしてみた。何度か壁にぶつかる音がしてたが、やがて聞こえなくなった。かなり深い10メートルなんてもんじゃないだろう。いつの間にこんな穴ができたのだろう?昨日ここを通りかかったときはこんな穴など無かった。一日でこんなに深い穴が掘れるとは思えない。仮に掘れるとしても土木機器があたりにやって来たらわかるはずだ。きっと元からあった穴が今まで塞がれていたのだろう。
穴の中をしばらく覗き込んでいるうちに僕はちょっと変な気持ちになってきた。何か生き物を落としてみたい。とりあえず落としても罪悪感の薄い生き物を落としてみよう。ちょうどネズミ捕りに一匹ドブネズミが掛かっているのを思い出し、哀れなネズミを穴の中に落としてみた。残念ながらネズミは小さいし落としてもリアクションに乏しいので僕のいけない欲望は満たされなかった。やはり大きな反応のある生き物じゃないとだめだ。ある程度大きくて可愛くなくてリアクションも期待できる生き物は無いだろうか?ここで、じゃあ人間にしようなんて言い出すほど僕は人でなしじゃない。そっかニワトリがいるじゃないか。僕は裏の家のニワトリ小屋からニワトリを一羽盗み出した。ニワトリはたくさんいるのでばれないだろう。 さすがにニワトリは楽しい。リアクションも鳴き声も大きいので長い時間落ちる音を楽しむことができた。それにしても深い穴だ。僕はあるお話を思い出して思わず空を見上げた。大丈夫何も落ちてこない。青空を見ているうちにニワトリを落とすことで少し晴れかけていた僕のどす黒い気持ちが再びよみがえってきた。もっと大きいものを落としたい。僕は牧場に行き羊を攫ってきた。ちょっと苦労したけど、僕は羊を穴の傍まで連れて来ることができた。ただ、羊を落とすとなると抵抗も大きいことが予想される。巻き添えをくわないよう体にロープを巻きつけ丈夫な柵にしっかり結んでから羊を落とすことにした。さすがに羊の抵抗は激しく落とすのに苦労したが見事に成功。やはり羊くらいの大きさになると反応も最高だ。 まだまだ欲望は満たされなかったけど、このままエスカレートすると僕は人でなしになってしまいそうなので、ここで止めることにしよう。と思い穴から立ち去ろうと言うそのとき、羊の飼い主が物凄い形相で僕に向って走って来た。大事な羊を盗まれたのだから当然だろう。謝らなければいけない、そしてちゃんと損害に対して賠償しなくては。ところが、僕が謝る前に飼い主は僕めがけて飛び掛って来きた。僕が悪いとは言え暴力で解決しようと言うのは納得できない。悪いけど僕は横に飛び退いて攻撃を避けることにした。運の悪いことに飼い主はバランスを崩し穴に向ってつんのめって行く。危ない!ここで彼を見捨てたら僕は本当の人でなしだ。助けなくては。 僕は人でなしになってしまった。羊の飼い主を助けようと手を出したところまでは良いのだけど、命綱のせいで手が届かず、今一歩のところで及ばなかったのだ。恐ろしい声を上げ飼い主は落ちて行った。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、そしてさっきの羊によろしく。僕は罪悪感で一杯になった。と同時にどす黒い気持ちがどんどんと晴れやかになって行くのに気付いた。人でなしになってしまったんだからもう正直に言おう、とてもすっきりした。生まれて初めて体験する爽快感だ。これは止められそうも無い。 次に何を落とそうか僕は悩んでいると向こうからヘルメットを被って図面を持った人たちがやって来きた。この穴の関係者に違いない。作業服を着た人が2人、背広の人が2人だ。さすがに大人4人を相手にするのは無理なのでここは大人しくしていよう。作業服を着た若い人が僕の方へ駆け寄って来る。僕は何事もなかったかのように、この穴の目的って聞いちゃ駄目ですか?あ、何か駄目っぽいですね…と軽口をたたきながら一行の様子を伺った。彼らの演技が巧いのか、それとも本当に何もまずいことはないのか解らないが、意外にもあっさりとこの穴の目的を話してくれた。10年ほど前までここの地下に石切り場があり、採算が合わなくなるまでかなりの量の良質な石を切り出していたらしい。今立っているこの場所の100メートル下にはその石切り場の廃坑があるとのことだ。廃坑と言ってもただひたすら巨大な空間になっているらしい。その巨大な空間を貯水槽として利用できないか試験を行うため、この辺りにいくつか穴が掘られているらしい。 そんなことよりも彼らは穴が開いたままになっていることの方が問題のようだ。昨日調査をした後、確かに塞いだはずなのに何故か蓋がなくなってしまったと言っている。3メートルの穴を塞ぐ蓋など簡単に持ち去ることができるわけも無い。一行は、何らかの事故か悪意ある操作で蓋が中に落とされたのであろうという結論に達した。山を少し下ったところに廃坑への入り口があるのでそちらから中に入ってみることにしますと言い残して彼らは去っていった。 彼らは廃坑の中で穴の蓋を見つけるかもしれない。それと同時にネズミとニワトリと羊とその飼い主の無残な姿を見ることになるだろう。と思いながら僕は次に落とすものを探し行くことにした。この辺には羊だけじゃなくて牛も馬もいる。彼らは喜んで受け取ってくれるだろうか。そうだ、タイヤとかバイクを落とすのも良いかもしれない。どうせ捕まるんだ、気が済むまでいろんなものを落とそう。
黒いマントの人達が北に向って黙々と歩いていた。年代はまちまちで、男性もいれば女性もいる。皆一様に無表情でフードつきの同じマントを被っている。マントの下の衣装は同じではないが黒系統の服を着ているようだ。だが、彼らは集団で歩いてるわけではない。何かを主張したりとか周囲に痕跡を残すわけでもなく、それぞれ勝手に同じ格好で同じ道を通って北に向っているのだ。実際彼らが2人以上固まって歩いているのを見たことはない。
最先端を歩く人が青森に到達した。意地の悪い人達はレミングのように竜飛岬から海に飛び込むことを想像していたようだが、その期待を裏切り彼はそのまま南下を始めた。本州の周囲をひたすらあるいて周ろうとしているに違いない。多くの人が何故かそう直感しただろう、私もそう思った。大衆の直感は大抵当たるもので、黒マントの集団は日本海側を通って南下しそのまま東北、北陸を通りついに山口まで到着すると今度は瀬戸内海沿いを歩き始めた。彼らは死ぬまで本州の周りをぐるぐると周るのだろう。 これも容易に予想できたことだが、九州、四国、北海道でも同様の現象が発生した。メンバーも確実に増えている。学校や職場である日突然来なくなる人が続出し始めているらしい。うちのゼミでも助手とドクターがいなくなった。隣の講座では教授がいなくなって大騒ぎになっている。 今日私の家にも黒マントが届いた。なるほど、こうやって始まるのか。不思議と今の生活に未練はない。むしろやっと参加できるという喜びの方が大きい。一生の進路がやっと決まったのだ。楽しくて仕方がない。さあ出かけることにしよう。
「え?250ですか。うわっ失礼しました。ほんと申し訳ありません。そんな大変な方と知らずに」
「いやいや、そう仰らずに。今はシニアクラスでたまに楽しむ程度ですから」 「最初にお見かけした時点でかなりの上級の方だという事は私でもすぐ解ったのですけど、オーバー100ですかなどと失礼な事を訊いて、まったく恥ずかしい限りです」 「250といっても半分は貢献ポイントみたいなものですから、実力はあなたの見たとおり100そこそこですよ。ま、こんな事は気にしないでもっと楽しみながら続けましょう」 「ありがとうございます。そういって頂けると肩の荷が降ります。それにしても鮮やかで無駄のない動作、素晴らしい限りです」 「いいえ、動作や手付きをあまり重視しては良くありません。大事なのは出来ばえです」 「なるほど、出来ばえを追及していった結果として動作が付いてくるのですね」 「そうです。主人公は自分ではなくてあくまで皿なのです」 「勉強になります」 私が趣味の皿洗いを始めて半年になる。先月アマ検定を受けて48ポイントの判定を貰った。半年で50近い判定を貰う人はそれほどいないらしく、少し天狗に成りかかっていた。今日も近所の洗い場で賭け洗いでもしようかと思っていた矢先、この老人に出くわしたのだ。最初は丁寧なだけで特に見るべきところもない洗いだと思ったのだが、それが大間違いであることに気付くまでそれほど時間は掛からなかった。まず動作が優雅で無駄が無い、そのくせ洗い上がりが速いのだ。皿だけが早回しで動く中、老人の手だけがゆっくりと流れているかのような錯覚に捉われる。思わず隣の洗い場に入り声を掛けてしまったが、まさかこれ程の大物とは。 「少々雑なので見落とすところでしたが、あなたは中々良い筋をしていますね。いや、大変珍しいタイプです」 「いいえ、お恥ずかしい限りで。何せ自己流なもので」 「失礼ですが最近になって始めたばかりではありませんか」 「ええ、そのとおりです。流行に背を向けるのが格好良いのだと変な気取りがあったのです。半年前にふと始めるようになってから、今まで避けてきたことを後悔しています」 「実に惜しいことです。もっとお若い頃から正式に習っていれば、古伊万里を洗えるくらいの素質をお持ちなのに」 古伊万里を洗えるのは300ポイント以上と言われているので、老人の言葉は半分社交辞令だろう。それでも実力が認められたのは嬉しかった。聞けば老人は孫に会いに初めてこの町に来て時間が空いたので飛び入りでこの洗い場に来たらしい。おそらく普段はこのようなところで洗う人ではないのだろう。 「それでは、そろそろ迎えが来るので失礼致します」 「お付き合い頂きありがとうございました。大変勉強になりました」 帰り際に老人は見事な手付きで小皿を一枚洗って私にプレゼントしてくれた。いや、手付きなどまるで見えなかった。この一枚は次元が違う。これまでも確かに素晴らしい洗いだったのにそれでも実力の半分も出していなかった事が解った。私が驚きと感動で碌にお礼も言えないでいるうちに老人は洗い場を後にした。 この一枚は今からでも遅くないという老人からのメッセージだろうか、それとも単に興が乗ったので戯れにくれたのだろうか。今、この世界にもっと踏み込むべきかとても迷っている。
職場で大きな仕事が終わり、久しぶりに打ち上げの飲み会が開かれた。一次会もそろそろ終わろうとする頃、僕がトイレに行こうとすると大橋さんが後ろから僕を追い越し、ポケットにメモをねじ込んで行った。僕はトイレの個室でどきどきしながらメモを見た。嘘だ 「次、ばっくれて二人で飲みに行こう」 と書いてある。2年先輩の大橋さんは口は悪いけどさっぱりした性格にすっきりとした容姿で密かにファンが多い。僕もその一人だ。その大橋さんが僕を誘ってる?落ち着け何かの間違いじゃないか、どこかに「これを田中に渡せ」って書いて無いか?僕はメモの裏表を何十回も見直した。大丈夫だ、メモにはさっきのお誘いの言葉とショットバーの名前しか書いてない。こんなことがあって良いのだろうか。
打ち上げの一次会が終わり二次会に引っ張られそうになるのを振り切って、僕はいそいそとご指定のショットバーに向った。僕とほとんど同時に大橋さんも到着、ちょっといたずらっぽい目つきに心臓が高鳴る。でも幸せはここまでだった。ショッキングな一言はモスコミュールとジンライムで乾杯した直後に飛び出した。 「ごめん。実は立花君に教えて欲しいことがあって呼んだんだ」 うわ、大橋さんそりゃないですよ、なんか耳の奥がジーンと鳴っている。何も期待してなかった振りをしようか、とも思ったけど、すぐ表情に出てしまうのは目に見えてる。諦めて正直に話すことにした。「ちょっと待ってください。正直すごくショックなんで、まずこれ空けちゃいますね」僕はジンライムに手を伸ばした。「駄目」 僕のジンライムを速攻で脇に追いやられた。厳しい人だ。「悪いけど、やけ酒は話が済んでからにして」 騙して誘い出したという自覚はあるみたいだ。よく考えてみるとひどい目にあってないか僕は?不満を言おうと思ったけど大橋さんはちょっと怖い目で僕の顔を覗き込む。白旗だ。「解りました。僕が知ってることで良ければ何でも話します」 「ありがとう。じゃあ遠慮なく聞くよ。立花君て田中君と仲良いよね」 結局そういうオチでしたか。田中の情報を聞き出すために僕を利用したってことですね。がっかりする僕とは対照的に大橋さんは冷静を装いつつも照れたような顔をしている。羨ましさと悔しさで頭がおかしくなりそうだ。「ええ、そりゃもう」 せめてもの抵抗として僕と田中の間に濃厚な関係があるような雰囲気を匂わせてみた。「一応確認しておくけど、そっち方面じゃないよね?」 大橋さんの目が険しい、抵抗した甲斐があったというものだ。僕はもう少し抵抗したほうが良いのかちょっと考えてみた。「言っとくけど、こっちは真剣なんだからね。茶化したり騙そうとしたら殴るよ」 とても僕を騙して誘い出した人の言葉とは思えない。「解りました。ちゃんと答えます。そういう関係はありません」 あっても困る。「OK。じゃあ協力して」大橋さんはその後2時間かけて水とジンジャーエールとウーロン茶しか飲ませてもらえない哀れな僕から田中に関するあらゆる情報を聞き出した。 「ありがとう。とても参考になった。そのうちなんかお礼するよ」 「では、早速で悪いんですけど教えてください。誰なんですか?」 「何が?」 大橋さんは何を聞いてるのか解らないって顔をしている。僕がどこまで気付いたかを探っているのかもしれない。 「田中のことを知りたがってるのは大橋さんじゃありませんね。いくら大好きな大橋さんでも2時間も話をすれば、いろんな事が見えます。僕を素面にしたのは失敗でしたね」 さりげなく告白したつもりだが声がうわずってしまった。みっともない。 「何のことかわからないけど、いろいろ見えたってのがどんなことか教えて欲しいな」 僕がちょっと押したくらいでは大橋さんのポーカーフェイスは崩れない。告白も無視された。 「まず質問が整理されすぎてました。誰かと協力して質問をリストアップして効率良く聞きだせるよう整理されているかのようです」 「私は興味の幅が広くて、質問も予め綿密に準備をしたのかもしれないよ。現にこうやって立花君を騙して誘い出したことから解るように、とても計画的に物事を進めるタイプだと思わない?」 やはり役者が上か、次のが効かなかったら僕には打つ手はない。 「それにもう一つ、僕の回答の内容にはあまり興味が無さそうでしたね。ひとつの答えから次の質問に発展することもほとんどありませんでした。好きな人のことを聞きだしてるというよりは、調査を楽しんでいるかのような印象です」 さあ、どうだ?大橋さんの表情からはどちらとも読み取ることができない。 「うーん。確かに今言った事は全部当たってるけど、大事なポイントを見落としてるから、65点ってとこかな」 厳しい採点だ。大橋さんは続けた。「どうして田中君に直接聞かなかったんだろうって思わなかった?」 もちろんその答は解っている。大橋さんも僕がわざと言わなかった事に気付いているに違いない。 「もうお分りですね。田中君は大橋がお気に入りの後輩を誘い出す口実に利用されただけだったんですねえ」 大橋さんはそう言って今日始めて笑った。
ある自動車メーカーのイメージキャラクター発表のニュースを見て驚いた。半年前、僕は大きな鎌を持った小さな子供の絵を描きそれに皆殺しちゃんという名前をつけて自分のホームページのキャラクターにしたのだが、その落書きのようなイラストが勝手に使われているのだ。自動車メーカーのイメージキャラクターとの違いは大鎌が魔法使いのホウキになっている点と名前がエンジェルちゃんになっている点だけだ。他は全く同じ、これは誰が見ても盗作だと認めてくれるだろう。思うに、この自動車メーカーのキャラクターは公募で選ばれたのだろう。そして誰かがまさか選ばれると思わずに、僕のサイトの絵を持っていったに違いない。僕はそう推理した。何か詳しい情報が判るかもしれないと思ってメーカーのサイトを見てみたら、僕の予想に反してキャラクターデザイナーとして有名なイラストレーターの名前が記されていた。出鱈目にも程がある。そのイラストレーターは細かい線で描かれた緻密な絵が特徴の筈だ。僕はその自動車メーカーに抗議のメールを送った。幸い僕は有料のファイルバックアップサービスに入会していて自分のホームページのファイル一式を保存している。そこに保存されているファイルのタイムスタンプを見れば僕の方が先に描いたことは明らかだろう。
自動車メーカーは僕の抗議を黙殺した。エンジェルちゃんは何故か人気者になり、関連グッズが売り出されている。エンジェルちゃんのファンと称する人たちからは「大人気ないパロディーだ」「子供の夢を壊すようなみっともない真似は止めた方が良い」といった抗議のメールが届き始めた。僕が作った皆殺しちゃんなのに酷い言われようだ。多分メーカーはこのまま黙殺を続けるか、下手したらプロバイダーに削除依頼を出すだろう。出るところに出れば勝ち目はあるのかもしれないが、僕はこういうときは泣き寝入りをすることに決めている。僕に入ったかもしれない使用料のことを考えながら悪酔いするのが似合っている。名残惜しいけど皆殺しちゃんもそのうち消してしまおう。 そう思っていたらメーカーとイラストレーターは盗作を認める発表をしてしまった。しかも彼らは「国民的アイドルとなる素材が発案者の手によって過酷な扱いを受けているので発案者の持つ著作権を侵害してでも救い出したかった」という理由を前面に押し出してきた。あまりに馬鹿げている、こんな世間を馬鹿にした理由が通用するわけないだろう。とにかく厄介なことが起きるのは確実だ何か対策をしなければ。 何より最初に野次馬の攻撃を避けなければいけない。会見からまだ1時間と経っていないと言うのにもうメールが30通ほど届いてる。僕はまず、脱会の届けを出してサイトのファイルを削除をしようとした。ところがファイルの削除権限は停止されていて、何度試してもファイルを消すことができない。改めてメールを見てみるとプロバイダーから「お客様のサイトにファイル固定依頼が来ていて特別処置として受理しました」との案内が届いていた。世間はエンジェルちゃんを可愛がるあまり、僕の想像以上に馬鹿になってるのかもしれない。メーカーは法律以外の部分で僕と徹底的に戦うつもりなのだろう。泣き寝入りもさせてもらえないようだ。 知らないうちに僕はメーカーに対して著作権侵害の訴えを出すことにされていた。メーカーは喜んで受けて立ち、そして喜んで敗訴し、敗訴が決まると同時に皆殺しちゃんに関するあらゆる権利を故意に高価な金額で僕から買い取った。その代償として、僕のサイト、バックアップサービス、僕の所有するパソコンから皆殺しちゃんのデータを削除したという宣誓文を書かされた。告訴から判決までマスコミは常にメーカーの味方に立った報道をした。盗作したイラストレーターと自動車メーカーの企画担当はちょっとしたヒーローとしてもてはやされている。あるニュースキャスターは「メーカーは確かに著作権違反という罪を犯しましたが、その罪は充分過ぎるくらい償いました。そればかりか子供達の夢を卑劣でわがままな守銭奴から守ったのです」とまで言った。僕と皆殺しちゃんに味方は一人もいない。 判決から一ヶ月が経過したある日、皆殺しちゃんが現れてイラストレーターとメーカーの企画担当の首を刎ねた。今ちょうどテレビ局に向っている姿が生中継されている。多分あのニュースキャスターの首を刎ねるのだろう。誰も皆殺しちゃんを止めることは出来ない。あはは、止めようとした奴の首が次々と刎ねられている。「遅かったじゃない、皆殺しちゃん」ブラウン管に向って僕がつぶやくと、皆殺しちゃんはカメラのほうをちょっとだけ見て「悪りぃ」と言った。愉快な奴だ。
「社長、これ絶対行けますって」
「君がそう言って持ってきた話がものになったことが一度でもあるかね?」 「そんな人聞きの悪い。まあ、ひとまず話だけでも聞いてくださいよ」 「どうせ断っても話すんだろう」 「そうこなくっちゃ。今回のご提案は、長期滞在リゾート型テーマパークその名も『ありがちランド』です。どうです?」 「どうですって言われても解らないなあ。とにかく名前はどうにかしなきゃいけないとは思うけど。それでどんなテーマパークなの?」 「それがですね社長、このテーマパークでは、お客様が数日間ある街に滞在していただくわけですけど…」 「ちょっと待って、リゾートと言っておきながら、街で過ごすのかい?」 「そこが、このテーマパークの新しいところなんですよ。お客様はその街の住民として過ごすわけなんです。そしてその街では、マンガやドラマの中でありがちな事が次々と起きるという趣向になってるんですよ」 「ミステリーツアー見たいなものかね?」 「似てなくもないですが、ちょっと違います。ミステリーツアーと違って決められたストーリーはありませんし、お客様はその世界の住民としてしっかりと参加していただくことになります」 「なんだか解ったような解らないような…。それでそのありがちな事というのは?」 「まず、お客様が朝家を出ると隣の家の女の子がトーストをくわえて『遅刻遅刻』といいながら走ってきます」 「ありがちだな」 「そう、そこがポイントなんです。ありがちランドはお客様が『フィクションでおなじみの光景』をいつもご覧いただけるのです」 「そうか、街の住民はスタッフとか役者なのだな」 「そうです。ただ、一人のお客様をあまり大勢のスタッフでお相手するのは限界がありますから、何名かのお客様が同時に滞在することになりますが」 「なるほど、なんとなく解って来たぞ。他にはどんなありがちなイベントがあるのかね?」 「例えばお客様が学校に行けば転校生が来て隣の席に座りますし、その転校生は数年ぶりにこちらに戻ってきた幼なじみだったりします」 「恥ずかしくなるくらいありがちだな」 「会社に出勤したらしたで、屋上でバレーボールをしたり、破天荒な新人が入ってきたり、帰りには屋台で一杯飲んでから帰ったりします」 「学生だったり社会人だったり忙しいな」 「一方さっきの幼なじみは隣の家に引っ越してきます。幼なじみとは二階の部屋が向かい合ってて屋根伝いにやってきて窓から入ってきます」 「それまた古典的な話だ」 「他にも拳銃で撃たれたけど胸ポケットのコインに当たって助かるといったイベントもオプションでお付けすることができます」 「あれはないのかね?雪山で遭難して体を冷やさないように、なんと言うかそのあれだ」 「さすが社長。それいただきですよ。雪山を用意するのは難しいので街中で何か適当な理由をつけることにしましょう」 「いや、私は特に興味はないのだけどお客様が喜ぶかと思ってな」 「そりゃもう解ってますって。他にもですね…」 ありがちランドの話はまだまだ続いている。この男は私と昔から付き合いがあるらしいがどうも記憶が曖昧で思い出せない。私はどうやら社長らしいが何の会社の社長なんだろう?いや、それ以前に私が誰なのかも良く解らなくなってきた。まあどうでも良いことだ。それにしても社長のところに直に胡散臭い話を持ってくるC調の企画屋とそいつに簡単に騙されつつある社長というパターンというのもフィクションの中ではありがちな光景だ。私もこの男も既にありがちランドの住民なのだろう。
海底に人間一人がなんとか生活できる住居を10個用意しました。この住居は海底地震があったり鮫に襲われてもびくともしない丈夫な建物です。住居と外とをつなぐのは緊急連絡と定期的な生存確認のための専用線だけで外部との連絡はシャットアウトされています。住居は互い距離を置いて設置されますので、他の住居を見ることもできません。また水、食料、空気は充分に用意されています。
ただし、この住居の壁には一つ小さなスイッチが付いています。このスイッチを押すと住居の扉が開き、内部は海水で満たされてしまいます。もちろん中の人は助かりません。スイッチは直径3cmほどのボタン型スイッチでカバーはなく、入居者が簡単に手の届く高さに取り付けられます。 この住居の中で20代から40代の男女10名にそれぞれ2週間生活してもらうという実験を行います。2週間の実験期間を通じて何人の被験者がスイッチを押してしまうでしょう? - - - - - * - - - - - 高額な報酬に釣られて妙な実験に参加してしまった。今日で開始から一週間になるが、あと7日間耐えられる自信がない。ボタンを押してみたくてたまらない。いまここで選択可能な道は3つある。一つはあと7日間ボタンを押さずに耐え切ること、二つめはリタイアすること、最後はボタンを押すことだ。一つめに関してはもう自信がない。どうしてこんなただのプラスティックの赤いボタンがこんなにも押してみたいのだろう。しかも押したら確実に死ぬというのに。いやだからこそ試しに押してみたいのかもしれない。 あと、5日だ。今日中に決めよう、リタイアするかボタンを押すかだ。リタイアするなら、ホットラインで係の人を呼び出してリタイアしますと言うだけで完了だ。とても簡単じゃないか。報酬はもちろん貰えないが、このままだと気が変になりそうだ。とは言えボタンを押すことも魅力的だ。係の人は「押したら1秒以内に扉が開き、次の瞬間確実にぺしゃんこになります」と言っていた。自分には自殺願望など無いと思っていたし今でも無いと思っている。にも関わらずボタンを押せば1秒後に苦しむ間もなく死んでしまうという強力なスリルにどうしようもなく惹かれてしまう。 それにしても死亡者が出るかもしれない実験なんてものが出来るだろうか?それにこの住居だってボタンを押せば確実に使い物にならなくなるわけだ。損失は被験者に払われる報酬の比じゃ無いだろう。実はボタンを押しても何も起きないのではないだろうか?扉は開かないでホットラインに連絡が入ってリタイアとなるのかもしれない。本当に人が死ぬような実験をやってることがばれたらまずいだろうし。 今日決めようと思い続けることで何とか生き延びている。あと3日だ。そういえばここに入るときに誓約書とか書かなかったな。あれば地上に戻ったときに危険な実験をしていたという証拠になったのに。逆に地上に戻れなかった場合も危険な実験をしていたという証拠はないのか、事故だった言えば済むって訳だ。それどころか実験を終えて帰宅したはずだともみ消すことも出来るわけだ。やはりボタンは本物かな。いや、だとしたら馬鹿みたいに費用をかけてこの実験をする理由が解らない。ボタンを押したら解るだろうか…。 この馬鹿げた実験も明日の正午で終わりだ。結局、ボタンを押すことに魅力を感じるとか言いながらもそれほど破滅志向がある訳でもないことが良くわかった。やはり死ぬのは怖い、無事に地上に戻って報酬をいただくとしよう。 実験は終わった。海底に沈められた住居がゆっくりと引き上げられ2週間ぶりに地上に出ることができた。今朝の定期連絡で「引き上げ終わってから外に出るまでの間にボタンを押したらそのまま海中に戻す」と言われた。そんなことするつもりは元から無かったんだけど、いろんな可能性を考えてあるんだなと感心した。 帰り際に高額の報酬と共に記念品を渡された。家に帰って開けてみると例のボタンのレプリカだった。「このボタンは押しても何も起きません、気の済むまで押してください(笑)」とメモが添えられている。馬鹿馬鹿しい何が「気の済むまで」だと、ボタンを押そうとした。…押せない、確実に安全だと解っているのに怖ろしくて押せないのだ。こんなもの捨ててしまおうと思うのだが、誰かが押すかもしれないと思うと捨てることも出来ない、誰も押さなかったとしてもゴミ処理場でボタンが押されてしまう可能性は0ではない。そう思うと怖ろしくて捨てられない。 以来、そのボタンから離れるのが怖くなった。どんなきっかけで押されないとも限らないので、家の中では常に近くに置くようにしている。外出するときはボタンを常に持ち歩いている。家に置いてたら泥棒が押すかも知れないからだ。一生このボタンから離れられそうもない。
「四人がかりとは、ずいぶんと私の力を高く評価してくれましたね」
「あんたにゃ、これでも少ないくらいだ」 少なすぎだ馬鹿、と思ったが黙ってることにした。「私も怪我をしたくないので何とか話し合いで解決させてもらえませんか?」 「珍しいな。だが俺の腹の虫は話し合いなんかじゃ収まりそうもないんだ。それに怪我で済むと思ってるってのも気に食わねえな」 お前ら相手に怪我なんかするかタコ、と思ったがやっぱり黙ってることにした。「そう言わずに、私だって問題は起こしたくないんですよ…」 そろそろかかってくる頃だな。可哀想だけどちょっとだけ相手をしてあげるかと思ったとき背後から子供の大声が聞こえてきた。 「お姉ちゃん!お姉ちゃん!あそこ、弱そうなお兄ちゃんがバカな顔した四人組にからまれてるよ。ねえいいでしょ、こんなときはやっちゃっても。いいことだから、やっつけてもいいんだよね」 振り返ると小学校低学年と思われる男の子が、早く遊びたくてたまらないって顔で喚いていた。その後ろには妙に落ち着いた女の子が立っている。こちらは小学校の高学年か中学生といったところだろう。 「ケンちゃん。そのお兄ちゃんは弱そうだけど、そいつらが相手なら十人くらいまでは全然大丈夫なんだから邪魔しないの」 まあ的確な見積だ。もっとも、この子だったら何人まで相手にできるか私には全然見積れないので大きなことは言えないけど。 「えーずるいそんなの。このお兄ちゃんめんどくさいからやだって言ってるよ。だから僕が手伝ってあげてもいいでしょ」 当たってるけど嘘はいけないぞケンちゃん。女の子はケンちゃんを無視して、私に謝った。 「すいません。甘やかされて育ったので、わがままばかり言って」 身近なところに子供が居ないので比べようがないけど、子供はたいていこんなもんだろう。それよりも、この女の子が妙に世慣れてて大人びた話し方をする事の方が不思議だ。 「いやいや、元気があってなにより。ケンちゃん、じゃあこっちの半分あげるからね。その代わり大きな怪我をさせちゃ駄目だよ」 「お兄ちゃんありがとう!全治2ヶ月以内だったら良いよね」 「ケンちゃん!1ヶ月以内にしなさい」 甘やかしてると言ってる割には厳しく躾けてるじゃないか。 「はーい。じゃあ、お兄ちゃん。よーいどんで競争しようね」 私は甘かったようだ。ケンちゃんは私に負けまいと夢中になり言いつけを守ることが出来なかったのだ。お姉さんにこっぴどく怒られたケンちゃんと馬鹿四人組には悪いことした。いや故人に馬鹿は失礼か。
「ガム捨てる奴、ぐちゃダセぇ」 今風の若者が怒り顔でこちらを睨んだ写真に今ひとつ意味が解りにくいメッセージが上手なのか下手なのか解らない毛筆で大書されたポスターが駅の壁に何枚も貼られている。半年前、歩道に貼り付いたガムを踏んでバランスを崩して倒れた子供が、打ち所が悪く重体になるという痛ましい事故をきっかけに始まった「ガムのポイ捨て防止キャンペーン」のポスターだ。こちらを睨んでいる若者はハラモトの愛称で親しまれている人気タレントの原島基次、メッセージに書かれている「ぐちゃダセぇ」は彼が主演しているドラマの主人公の口癖で「滅茶苦茶ダサい」という意味らしい。合同スポンサーとなっている4社の菓子メーカーにしてみれば「一応義務は果たしましたよ」というポーズのためのキャンペーンだったのだろう。商品の宣伝のためのCMには出ないと公言しているハラモトを起用することが出来たという点で話題にはなったが、それ以外は取り立てて特徴のないポスターだった。
このポスターが貼られてから、ガムが捨てられることが極端に少なくなったことに最初に気付いたのは駅や地下街の清掃員達だった。彼らによるとキャンペーンによってポイ捨てが減ることはあったが、ここまで短期間で大きな効果をもたらしたことは今まで無かったという。メディアはこの現象を当初、若者のモラル向上として好意的に受け入れると共に、ハラモトが持つ若者に対する影響力を再確認した。その一方でこれは一時的な現象であってキャンペーンが終わればまた元に戻るだろうと悲観的な見方をする人も多かった。 ところが、モラルが向上したのかと言うとそんなことはなく、路上に捨てられるガム以外のゴミが以前と比べて減ることはなかった。ただ、不思議なことに大方の人の悲観的な予想を裏切りキャンペーンが終了してポスターが消えた後もガムを捨てる人が増えることは無かった。人々はハラモトのポスターによって強力な暗示を掛けられたのかもしれない。 翌年もハラモト効果はまだ持続していた。税率アップによる売り上げダウンに悩んでいた日本たばこはイメージアップを図るべく「タバコのポイ捨て防止キャンペーン」にやはりハラモトを起用した。今回も主演を勤める映画の登場人物に併せて「吸殻を捨てる奴が許せんのじゃあ」とストレートなコピーが添えられた。この安易な二番煎じに対して人々の反応は冷ややかだったが、予想に反してこのキャンペーンも絶大な効果を上げてしまった。吸殻のポイ捨てにしかキャンペーンの効果が及んでいないこと、キャンペーンが終わっても効果が持続しているところまでガムのときと同じ結果となった。とにかくガムと吸殻が路上から消えたことに対して不満を持つ人が居る訳も無くハラモト効果は世間に歓迎されていた。 こうなるとCM業界がハラモトを放っておくはずもなく、あらゆる商品のCM出演依頼ががハラモトに持ち込まれた。これに対し、無頼というポーズを取り続けているハラモトは自費で「ハラモトは商品の宣伝をしません」という新聞広告を出すことで対抗した。ハラモトの思惑どおり翌日から出演依頼を持ち込む者は居なくなった。これはCM業界がハラモト効果にやられたことに加えて、ハラモトを怒らせたメーカーに対して不買を求める広告を出されることを恐れたためでもある。後日、効果を利用しようとしたある政治家に圧力を掛けられた事をハラモトが公表し、その政治家が一週間で完全に失脚したことでCM業界の判断は正しかったことが証明された。 ハラモトは他にも「覚せい剤撲滅」や「脱税防止」といったキャンペーンに出演し、そのたびに暴力団関係者が泣き、税務署員が泣いた(税収と仕事が一気に増えて)。今やハラモトは「モラルの最終兵器」と呼ばれるようになった。 ハラモトが飛行機事故で死んだ。それは同時にハラモト効果だけで守られていたモラルの死を意味するであろうと思われていた。ところがハラモトの死後もモラルの崩壊が起きる気配はどこにもなかった。それどころか人々は新たなキャンペーンを求めるようになった。「やってはいけないことをやらない」と言うことが快楽となってしまったのかもしれない。加えて人々はハラモトに変わる新たな「モラルの最終兵器」を求めた。すぐに明るくて親しみやすい40代の女優がその役を担うようになったが実際のところ誰でも良かったのかもしれない。 人々は今日も血走った目で清く正しく暮らしている。
27歳ブームがやってきた。早く27歳になりたい、27歳になれば何でもできそうな気がする。27歳を契機に結婚、旅行、出産、卒業、脱サラ…などなどいろいろなことに挑戦する人も増えている。すばらしい27歳の一年間。そして、27歳が終わると抜け殻のような日々が待っている。もう私は27歳じゃない。一生27歳になれない。とてもとても長い余生だけが残されている。毎年あのすばらしい27歳から遠ざかる…。
面白くないのは27歳ブームが始まったときにはすでに27歳を過ぎていた人たちだ。ほとんどの人はくだらない流行だと馬鹿にしていたが、私の27歳の一年間も確かに素晴らしかった輝いていたと言い出す人も現れ始めた。中にはどうして自分は素晴らしい一年間を無為に過ごしてしまったんだろうと後悔する人も少なくなかった。マスコミやメーカーは「37歳、47歳、57歳…も素晴らしい」「54歳は二度目の27歳」という強引なこじつけをブームにしようとしたが、どれも不発に終わった。逆にどんな年齢も27歳には到底及ばないという印象を植え付けることになってしまった。 ブームは留まることなく続いた。27歳の一年間は特権意識を持つ人が増えだし、何故か社会はそれを受け入れてしまった。税金が免除される、色々なものが安く買える、借金の金利が減らされるなどの特典が与えられるようになった。海外の旅行会社はこの点に目をつけ、27歳の一年間だけの滞在プランを提供し始めた。冷静な人たちは海外からの旅行者にまで特典を与える事に異議を唱えたが、人種・性別・国籍に関係なく27歳であることは素晴らしいという意見に押され、海外からも多くの27歳が素晴らしい一年間を過ごしに訪れるようになった。 ただし、年齢を詐称した場合は市民によるリンチが当たり前のように行われ、法も詐称した者には厳しく、事故死として扱われるのが通例となった。このため海外からの滞在プランでは詐称が発覚した場合の生命の保証はしないという条件が付けられるようになった。 日本での27歳ブームをきっかけに他の国では違う年齢がブームが人為的に始められた。既に27歳ブームに浸かっていた日本では他の年齢はブームになることは無理だったが、ブーム未体験の国では他の年齢の方が受け入れられやすかった。国同士の対抗意識が働いたのかもしれない。ブームは世界中に広がり15歳から70歳までのすべての年齢がどこかの国や地域でブームになり他の年齢に関してもほとんどカバーされるようになった。以来、多くの人たちが一生かけて毎年に自分の年齢がブームの国に移り住むスタイルを取るようになった。 - - - - - * - - - - - このように現在の世界ボヘミアン化現象は、日本の27歳ブームがきっかけで始まったのである。
「立花、身長を伸ばす機械、要らない?安くしとくよ」
「うわあ、佐橋さん大きくなりましたねえ」 「いいだろ、ノビールって言う機械なんだけど、もう俺は使う必要ないから安く売ってやるよ」 「また思いっきり安直な商品名ですね」 「いいんだよ、名前なんて。実際に背が伸びるんだから」 「機械で背を伸ばすのって痛くないですか?」 「うーん。痛いっちゃ痛いかな」 「それは、いやだなあ」 「機械を使ってまで背を伸ばそうと言う俺の考えが痛い」 「そういう痛さですか」 「実のところ、高見盛みたいな顔したおばさんのマッサージ師が気合入れてマッサージしてきたときくらいは痛い」 「高見盛はともかくそれくらいなら耐えられそうです。どうやって使うんですか?」 「寝そべって頭と足にベルトを取り付けてスイッチを入れるとぐいぐいと引っ張られるんだ。それを毎日1時間やると最初の1ヶ月で5cmは伸びるね」 「嫌になるくらい単純な原理ですねえ。佐橋さん10cm以上は伸びてますけど、そこまで伸ばすのにどのくらいかかりました?」 「俺はだいたい4ヶ月やって12cm伸びた。ほらお前よりかなりでかくなったぞ」 「でも僕がこれ使ったらまた追い越しますよ」 「それは面白くないから、7cm伸びたら誰かに売ること」 「勝手だなあ」 僕がノビールを使いはじめて1ヶ月が経過したころ、この機械の使用方法を誤り首を痛めた人や急激に身長が伸びたため体に異常をきたす人が続出し、ノビールは生産中止となってしまった。僕はちょっと怖くなって使用を止めようかと思ったけどマニュアルどおりに時間を守って(あと佐橋さんとの約束も守って)使えば問題は無さそうなので、あと2cm伸びるまで続けることにした。 「立花、あれまだ使ってるか?」 「ええ、あと2cm伸びたらやめようと思ってます」 「別に強制はしないけどな、早いうちにやめた方が良いぞ」 「またまたぁ、追い抜かれるのが嫌だからって。ちゃんと佐橋さんの身長を越える前にやめますって」 「いや、そうじゃないんだ。だいたい俺の身長を追い越すのは多分無理だと思うぞ」 「あれ?そう言えば、あれからまた大きくなってませんか?」 「うん。この前より3cmは伸びた」 「またノビール買ったんですか?」 「いや、あれはもう売ってない」 「店にはなくてもヤフオクで買ったとか?解った、ニセモノを買ったんですね、ノビーレとか」 「馬鹿か。そんなものないよ」 「じゃあどうしたんですか?」 「何もしてない。勝手に伸びたんだ」 「え?」 「伸び癖が付いたんだと思う」 「伸び癖って、もしかしたら僕も既に…」 「あれから1ヶ月だっけ?」 「そうです。ちょうど30日、5cm伸びました」 「じゃあまだ俺ほどは使ってないから大丈夫かもしれないぞ」 「もう遅いかもしれないけど使うの止めます」 僕はその日からノビールを使うのを止めたけど既に遅く、月に2cmの割合で背は延び続けた。それから一年間、僕の身長は伸び続け2mを超えようかという辺りでやっと成長が止まった。佐橋先輩は210cmまで伸びた。ただ、幸いにも急に伸びた割には体調に大きな変化はなく、いたって健康に暮らしている。頭を何度もぶつけたり服がすべて着れなくなったのが辛いけど。街に出れば、僕と同様にノビールを使って背を伸ばした人がひょろひょろと歩いている。何が辛いって「ノビール族」などという恥ずかしい名前で呼ばれるのが一番辛い。 「立花、ノビール族生活には慣れたか?」 「慣れましたよ。それはともかくノビール族って言うのやめましょうよ」 「慣れたとは言っても、もう少し日常生活に支障のない大きさに戻りたいと思わないか?」 「そうですね。戻れるなら180cmくらいが良いなあ」 「あのな、ネットでチヂームって機械を見つけたんだけど…」
「助けてください」
「お困りのようですね。お力になれるか解んないけどできるだけのことはしますよ」 「ありがとうございます。私は魔法使いによって醜い人間の姿に変えられてしまったのです」 「醜いって失礼だなあ」 「はっ。申し訳ありません。醜いと言うのはあくまでも私達の価値観です。大変失礼致しました」 「そうだね。例えば人間はオコゼを見て醜いと思うけど、オコゼにしてみれば人間なんて気持ち悪いと思うだろうからそれと一緒だ」 「どうぞお許しください」 「いえいえ、こちらこそ。それで、僕はどうすれば良いの?僕に出来ることでしたらお手伝いしますよ」 「ありがとうございます。それでは魔法を解く薬を作るので材料と場所をご用意願えないでしょうか?」 「えーと、僕は魔法とか良く知らないんだけどそれってどこに行けば手に入るのかな?」 「材料を言いますので、手に入るかお教えください。食塩、水、酢酸、鉛、エタノール。以上です」 「あれ?そんなので良いんだ。それならスーパーと薬局と釣具屋を周ればすぐに手に入るよ。大量にと言われると困るけど」 「材料に拠りますが、一番多い物でも約500g程です」 「なら大丈夫。あと道具は何か必要?」 「加熱するための設備が必要です。無ければ焚き火でも可能です」 「そのくらいの火力で良いならうちの台所でできるね。それで全部?」 「はい。これで全部です」 「了解。じゃあ材料を揃えて僕のうちに行きましょう」 「ありがとうございます」 こうして、僕は醜い人間に姿を変えられた気の毒な青年を家に連れてきた。材料をすべて並べ、要らない鍋を駄目にしても良いからと言って渡し、ガスコンロの使い方を教え、後は邪魔をしないで居間でテレビを見ていることにした。途中ペットボトルの開け方と火の消し方を訊かれた以外は特に問題は発生しなかったようだ。薬を作り始めて90分後、台所から青年が出てきた。 「ありがとうございます。おかげさまで魔法を解く薬を作ることができました」 「お役に立ててなによりです。これで醜い人間の姿ともおさらばですね」 「勘弁してくださいよ。もう言いませんから」 「ごめんごめん。もし嫌じゃなかったら元の姿も見せてもらえるかな?」 「多分人間から見たら醜いと思いますよ。でもそれでお互い様になりますね。お世話になったお礼と言っては失礼ですが、話の種にはなると思いますので元の姿をお見せしましょう」 僕は人間と美意識の異なるその生き物が何であるか知りたかった。悪趣味かもしれないが「僕が醜い○○に変えられたときは助けてくださいね」とその生き物を小馬鹿にしてやろうとも思っていた。青年は元に戻るには5分ほどかかりますのでその間は手を出さないでください言って、出来たての薬を一気に飲み干すとその場にしゃがみこみ動かなくなった。 5分後に立ち上がったのは今まで見たことのない美しい生き物だった。他の何にも喩えようの無い絶対的な美。美が相対的なものだなんて言ったやつを殺しに行きたくなるような美しさ。完璧という言葉を二度と使いたくなくなる本当の完璧。醜い人間に変えられて正気でいられたこと尊敬の念すら覚えた。 「どうですか?人間から見たらやはり醜い生き物でしょう」 「……」 「そうでもなかったようですね」 醜い私への哀れみと慈悲を含んだ視線を投げ、美は僕の部屋から出て行った。
「お前ら全員殺されても仕方ないことしてるんだからな」
「すごいね、ここに居る13人より自分の命の方が価値があるって言ってるんですよ」 「いやいや、それどころじゃありませんよ。この人生きてるんですから。この人がちょっと苦労したり嫌な目にあった事による損失がここに居る13人全ての命や業績や将来よりも価値があると言ってる訳です」 「自信家ですねえ」 「立派な人なんでしょう」 「お前らなんかに何が解るって言うんだ。お前らのせいで俺ばかりじゃない女房と娘がどれだけ苦労したと思ってるんだ」 「おやおや、家族を持ち出しましたよ。私は妻と息子2人と私の母を扶養してますけど、その4人を足してもこの方のご家族の方の2年間の苦労を思うと路頭に迷っても仕方ないと言うんでしょうなあ」 「うちは弟が難病と戦っていて弟自身も私もなかなか大変なんですけどこの方とご家族の苦労とは比較にならないんでしょうな」 「ならないんでしょうよ」 「さっきからうるせえな。てめえらみたいな社会のクズにそんなこと言われる筋合いなんか無いんだよ」 「私なんかは税金を結構納めてるし地域のために無報酬で働いてるんですけど社会のクズなんでしょうな」 「私は寄付をしたり、学資に困っている学生さんを援助したりしてるのですが、この方のお子さんの未来に比べたら微々たる物なのでしょうな」 「うるせえ」 ズドン 「うわあ、鈴木さん。お気の毒に」 「お子さんも可愛い盛りだと言うのに」 「足の悪いお父様を毎日病院に送り迎えしていたのに」 「そうまでして自分の悔しさを晴らしたかったんでしょうな」 「元はと言えばこの方がギャンブルで作った借金が返せなかったことが原因なんですけど、私たち社会のクズでは伺い知れない事情が他にもあるんでしょうな」 「ここに居る13人とその家族42人の命や生活と引き換えに晴らされる無念が高々ギャンブルで作った借金が返せなかったことが原因な訳ないでしょう」 「うるせえ」 犯人はその直後に逮捕された。犯人は拘束され毎日被害者やその家族、警察官、報道関係者、加害者の家族に毎日耳元で叱責され嫌味を言われ軽蔑の言葉を投げられている。終身刑が確定したあとも拘束は解かれることなく、色々な人が録音した犯人への言葉や掲示板のログの自動読み上げによる音声が24時間ヘッドフォンから流れつづけている。 とっくにその男には意味など解らなくなっているが。
「立花子さん結婚してください」
僕はやっとの思いでプロポーズした。いや待てこの変な名前の女性は誰だ?そもそも何で僕は知らない人にプロポーズしてるんだ?混乱する僕とはまったく無関係に事態は展開して行く。変わった名前の立花子さんは一瞬驚いたような表情を見せてから、小さく微笑み返事をしようとしたその瞬間 「ハイ、カットぉ」 の声が響く。どうやらドラマか映画の撮影のようだ。僕は役者なのかもしれない。今のが今日最後のシーンだったらしくスタッフはセットを撤収し始めた。それにしても随分と大胆に片付けていくものだ。店の内部から始まってついには建物まで片付けてしまった。こんなに片付けたら明日からの撮影が面倒なんじゃないだろうか?と呑気に構えてたら、建物だけじゃなくて街も国も地球も撤収されてしまった。 「…という恥ずかしい夢を見たんです」 「うーん。かなり陳腐だなあ。唯一オリジナリティがあるとしたら立花子さんという名前くらいかな」 「実は、立花子さんは前原さんにそっくりだったんですよ」 「私?立花君たらもしかして、あららら」 「ええ、実はずっと前原さんのことが…」 「ハイ、カットぉ」
じゃりじゃりと音を立てて道を歩く。柔らかい貝殻が潰れる感触と中身を踏みつける感触とを同時に味わいながら。この靴もそろそろ駄目だな。ナイキから貝路でも歩きやすい靴が出たらしいがあれは効くのだろうか。道が歩きにくくてやたらと喉が渇く。コイン投入口とボタンに貼り付いた貝を百円玉で払い除けてコーラを買う。ゴトンという音にすら貝が潰れる音が混じる。赤い缶を急いで取り出し青い貝を取り除く。つり銭はあきらめた。飲み口のところだけ丁寧に拭いてからリングプルを開けて慎重に飲む。やっと生き返った。だが、立ち止まっては居られない。すでに5匹ほどズボンにまで登ってきた。慌てて振り払いながら再び歩き始めた。本当は走り出したいところだが、道がぬるぬると滑るのでそれもままならない。自転車で走れた頃が懐かしい。
去年までは10分で帰って来れた道を30分かけてやっと帰宅。じゃりじゃりと音を立ててドアを開け家に入り靴とズボンとコートとメットと鞄についた貝を落としに風呂場へ向う。今日は31匹。すべて落とし終えてから風呂場に殺貝剤を撒き、室内のチェックをするのが日課になっている。子貝が小さな隙間から入ってくると後で苦労するので慎重に探す。貝センサが出たおかげでチェックはかなり楽になった。通気口に3匹、トイレに1匹、殺貝剤で念入りに退治して貝除けを塗っておく。 これでやっと休むことができる。通勤時に体力を使うし、屋内に入るたびに貝を落とさなければいけないのでとにかく疲れる。自分の部屋にいても常に貝の進入に気をつけなければいけないので、なかなか疲労も回復しない。気温が上がってくれると貝も半分以上いなくなるので少しは気が楽になるだろう。予報では明日は久しぶりに晴れそうだと言っていたが窓ガラスにびっしりと貼り付いた貝のせいで外は見えない。 もうつまらない意地を張るのはやめて貝になってしまおう。今月に入ってからそのことばかり考えている。酒をたくさん飲んでぶっ倒れる直前にドアを開けるのが一番楽な方法らしい。明日も雨だったらそうしようか。
「なっちゃんは誰にも渡さん」
「うるさい。勝手なこと言うな。俺だって誰にも渡さないぞ」 「なんだと。なっちゃんは俺のものだ」 「いや俺のものだ」 コーヒースタンドで遅い昼食を取っていたら、奥の席からふた昔前の青春ドラマのような言い争いが聞こえてきた。ただ、ふた昔前と違って言い争っている二人からは体育会系の空気が全く感じられない。いや、最大の違いはこの場になっちゃんらしき女性がいないことかもしれない。 「だいいち、お前は後からやって来たんじゃないか」 「それがどうした。お前は俺が出てくるまでほとんど黙っていたようなものだろう」 「そんなことが理由になるか。黙っていたか積極的に話してたかなんてのは客観的に判断できるものでもないだろう」 「じゃあ、俺が出てこなかったらどうするつもりだったんだ?俺が出てきたから、なっちゃんに執着するようになったくせに」 「推測で勝手なことを言うな」 「事実だからそうむきになっているんだろう」 喧嘩のパターンというのは昔からあまり変わってないようだ。ふた昔前ならここで何か勝負を始めるところだが、この二人はどうするのだろう。 「これ以上争っても埒が明かない。コイントスで決めないか」 「釈然としないが、仕方ないだろう」 「じゃあ、俺が投げるから当ててくれ」 「裏」 「くそ、負けたか」 「約束どおり、なっちゃんは俺のものだ」 「しかたがない。俺は別のハンドル名を使うことにする」 この国は一度滅んだほうが良いと思った。
うかつだった。子供だと思ってなめてたが、トモちゃんと私ではレベルが違いすぎて相手にならない。
「気付くのが遅すぎます」 私をもっと手ごたえのある奴だと期待していたのだろうか?理不尽にも私の鈍さに対して怒っているようだ。 「私が負けを全面的に認めて命乞いをしたら助けてくれるかな?」 子供相手の交渉としてはあまり良くなかったかもと思いつつ相手の腹を探ってみた。 「交換条件というのはすべて嘘だと習いました。だから聞く気はありません」 実に正しい教えだ。そんな正しいことをこんな凄い子供に教えるのはもう少し待ってほしかった。 「これは交換条件じゃないよ。泣きながら命だけは助けてくださいって情に訴えようと思ってるんだけど、だめかな?」 これは、まったく本当。お望みとあらばこの場で大泣きしても構わない。 「情に流されることは詐欺に会うことと同じだとも教えられています」 誰だか知らないけど、そんな先生がいたら私も少しは違った一生を送ってたかもしれない。 泣くのは次の機会までとっておくことにして、もう少し交渉を続けて見ることにしよう。「私が助かる方法は何かないのかな?」 「あなたのお話は全然面白くありません。私も忙しいのでそろそろ終りにしたいのですが」 交渉の余地はなさそうだ。「あ、それから何か勘違いしてるようですけど、私それほど物騒なことするつもりありませんから。あなたが人並みだったら多分死んだりはしないでしょう」 ありがたい御指摘だが全然気が楽にならない。 トモちゃんは無表情で軽く握った両手を低く構える。右手の人差し指が小さく動いた。と同時に鋭い音が聞こえコートの裾に軽い衝撃を感じた。穴が空いている。 「珍しいな、指弾を使うんだ」必死に動揺を隠しながら私は続けた「でもこの状況にふさわしい方法じゃないと思うけどな」 他に攻撃方法を知らないという可能性を探ってみる。あり得ないとは思うが。 「…」 トモちゃんは声を出さずにため息をついた。「あなたがそこまで未熟な人だとは知りませんでした。正直言ってこのまま帰りたい気分です」 「そうしていただけると、二人ともハッピーに丸く収まるんだけど。どう?」 トモちゃんはそれには答えず「あなたは、これが指弾だと思ったのですか?」 と言って右手を少し上げた。また空気を切り裂く音。帽子が前に飛ぶ。…前に? 「普通はコートに当たった段階でどちらから飛んできたか解るはずですし、方向がわかればこれが何であるかなど簡単に解るはずなのですが…。まだ解らないのなら次は胴に当てますよ」 トモちゃんは本気で怒っているようだ。何故、私が怒られなければいけないんだ? 「答えが無いのは解らないからだと判断しますが」 もう答えは解った。帽子が飛ぶまでまったく思いつきもしなかったのは恥ずかしい限りだが、そんなマイナーな物を知らなかったからって怒ることは無いと思うのだが。 トモちゃんの左手が動きかけた。「解った、答える。答えますって。だから手を下げて。君が使ったのは虫弾だね」 話には聞いていたけど虫弾を使う人が実際に居るとは知らなかった。通常は、虫弾が劇的に好むフェロモンを相手に塗布するか、虫弾を仕込んだ場所からの経路上に相手が来るよう虫弾フェロモンを置くという方法が一般的だが、外した場合に次の攻撃ができないというデメリットがあるため、トモちゃんの場合は特定種にだけ作用するフェロモン何種類か用意して何度も攻撃できるようにしているようだ。この方法の場合、どこにどのフェロモンに反応する虫弾を仕込んで置いたかを覚えていないと使えないし、自分に当たらないようにするには相当の訓練が必要だ。 「そもそも、私がこれを覚えさせられたのはあなたに原因があるのですよ」 「何でも他人のせいにするのは良くないよ。私のどこに原因があるの?」 「あなたが調子に乗って私の弟にあんなことをさせたせいで、私は家に帰って、監督不行き届きだと怒られました。そして罰としてこんな使い道の無いおもちゃを覚えることになったのです」 罰ゲームで覚えるような技じゃないと思うのだが。それよりあれから3ヶ月しか経ってないというのに虫弾をマスターしてることに驚いた。 「その件については君にもケンちゃんにも何度も謝ってるじゃないか。だいたいトモちゃんだってあんとき見てるだけで止めなかったじゃん」 「確かにあなたの実力を見誤ったのはミスでした。危なくなったら止めることができる人だと思ったものですから。こんなに未熟な人だと知ってたら最初から止めさせてました」 「そんなに未熟かな?」 「ええ。最初の評価は50点でしたが、今は15点くらいだと見ています」 とても恐ろしくて採点基準は訊けない。 「それはかなり大きなミスだね。だったら、少しは折れてくれてもいいんじゃない?そんな危ないもの持ち出さないでさ」 未熟でも何でも良い、ここは何とか口先で逃げ切らなければ。虫弾なんかを当てられることを思えば何だってできる。 「では、こうしましょう。神経毒の作用を抑える内服薬をここに置きます。弾は腿に当てますから這って来ればなんとかなるでしょう」 そう言ってトモちゃんはつま先で地面を掘り、小瓶を置いて上から土をかけた。微妙に意地悪だ。瓶を埋める動作に少し隙が見えた。私はやけくそでトモちゃんに飛びつき押さえ込んだ。「せめてもの抵抗をさせてもらおう。さあどうする?」 「最低ですね。子供に対する性的嫌がらせですか」 いや、そうじゃなくて。 「その話はまた5年後にでも。それより、このまま虫弾が私の足を貫いたら確実にトモちゃんにも当たるよ」 「一つ間違いを訂正させてください、さっきの15点は誤りでした。あなたはせいぜい5点と言ったところです」 私の評価は3ヶ月で10分の1に大暴落したようだ。「何のプロテクトもなしで、こんなおもちゃを使うと思いますか?」 と言い終わる前に左足の腿に激痛が走った。トモちゃんのジーンズの上で私の左腿を貫いた虫が潰れている。だが痛さにのた打ち回っている暇はない。1分以内にさっきの小瓶を掘り出さないと大変なことになる。 「私を押し倒したときに瓶が割れてないと良いですね」 トモちゃんはつまらなそうにそう言って哀れな5点男を残し去って行った。
「いやあ、暑いな。頭が焦げそうだ」
「お疲れ様です。麦茶でいいですか?」 「お、ありがと。田中は昨日から来てたの?」 「ええ、昨日です。立花さんバスで?」 「うんバス。あれだろ?あのお婆さん」 「あ、やっぱり見ましたか。私も昨日見ました」 「悪い人じゃないんだろうけどやっぱり気になるよな」 「上品そうなところがかえって怖いんですよね」 「これで4年連続ですか?」 「いやいや、そんなもんじゃないぞ。去年差し入れ持っ来た木ノ内さん、俺の5代前の、あの人も見てるって言うから最低でも10年前からああやっているらしい」 「うわっ。余計怖くなりました」 「多分何かショックなことがあったんだと思うぞ」 「お年寄りなんで解りにくいのかもしれませんが毎年全然変わってないですよね」 「ああ、木ノ内さんは10年間まったく年取ってないみたいだって言ってた」 「いつも和服をびしっと着こなしてますし」 「高そうな着物だったから、そこそこのお金持ちじゃないのかな」 「いつも横に綺麗な風呂敷包みを置いてますよね」 「うん。そしていつも可愛い赤ちゃんを抱えて…」 「あっ」
「次の話だけどね 【通称『人形』と呼ばれる精巧なロボットを作る人形師が主人公】 と言うのはどうかな?」
「うーん、今ひとつ何か映えるものが無いかな」 「そいつはいつも肩にマスコットを乗せているんだけど、それがまた精巧にできてて良くしゃべるんだ。それで、実は…」 「あ、もうそれ解っちゃった。人形師の正体は実は…てやつでしょ。そのパターン結構あるよ」 「え?他にあるのか。だったら駄目かな」 「ここから、もう二捻り半くらい欲しいところだ」 「捻りまくりだな」 「それ知ってるってところに一捻り入れて、驚いたところでもう一捻り半入れてやれば驚きも大きいと思う」 「じゃあ 【人形師もマスコットも実は『人形』で、人形師の工房で見習いをしてる子供がすべて作ってた】 というのはどうだ?」 「それだと、一捻りってところかなあ」 「厳しい評価だな。だったら 【人形師の工房に居る人も含めて、街の人たちはすべて『人形』。ただ、ある一人だけが人間でそいつがすべての『人形』を作った】 というのは?」 「なんかどんどん大げさになっていくけど悪くないな。その『人形』達は自分達が作り物だと言う自覚はあるわけ?」 「ある。でそいつらは街の中に一人だけ自分達の造物主がいるということも知ってるんだけど、それが誰であるかは知らされていない訳だ」 「でも人間である当人は知ってるんだから別に問題はないだろ」 「ところが、そいつが事故で記憶を失ってしまって、ここが『人形』だけの街だということもそれを作ったのが自分だということも忘れてしまうのだ」 「でも自分は人間だと思ってるんだろう?」 「もちろん」 「だったら周りの『人形』達から浮くのではないか?結果として自分だけが人間だということに気付くと思うけど」 「まず、『人形』達は普段から人間と同じように過ごしてる。次に人間は一人で暮らしているのでロボットの普段の生活は解らない。それに『人形』達の世界は閉じているのでわざわざ自分達がロボットであるという話をする事がない。こういった理由で記憶を失った造物主はここが人間の社会だと思ってしまう訳だ」 「そうか。『人形』しかいない世界であるがために自分達が『人形』であることが話題に登らない、その結果逆に異分子である人間は自分が異分子であることに気付かないという事だな」 「そういうこと。ただ、その造物主である人間がしていた仕事がなされなくなっているので、このまま放っておくと街は停止してしまう危険性がある」 「そこで主人公はどんな役割を?」 「主人公はこの『人形』社会の中でこういったトラブル時に問題を解決する役割を与えられていて、記憶を失った自分達の造物主を探して、記憶を取り戻してやらなければいけない」 「つまり、人間のようなロボットばかりの街の中で、ロボットがロボットの視線で人間を探す訳だ」 「うん。人間が異分子であるという『人形』側の視点を上手に描くことができれば面白くなると思うな」 「何だか面白そうだ。よし、それで行こうよ」 「いや、その必要ハナイ。発見シマシタ。捕獲シマス。応援ヲ頼ミマス」
知り合いに頼まれ教育問題のシンポジウムのサクラをやる羽目になった。普段は縁の無い場でだったので一度断ったのだが、会場に出向いて聴衆として参加するだけだからと押し切られてしまった。興味の無い話を長時間にわたって聴いたせいか、途中からは睡魔との闘いになったが(ときどき敗れた)、それでもなんとか苦境を乗り切り、シンポジウムは教育評論家による講演を残すのみとなった。
司会者に紹介され出てきたのは、この場にはちょっと似合わない風貌の男性だった。教育評論家と言うよりはインチキな青年実業家といった肩書きが似合いそうな男だ。聴衆の好奇の目が注がれる中「いじめ問題の本質を考える」と名付けられた講演が始まった。 「現代においていじめ問題の本質的な原因は100%いじめられる側にあります」 客席が少しざわつく。それぞれ意見はあるのかもしれないが、少なくてもこの場ではかなりの暴言と言って良いだろう。「いじめる側」の言い間違いじゃないのか?そんなつぶやきがあちこちから聞こえてきた。 「繰り返します。現代においていじめ問題の本質的な原因は100%いじめられる側にあるのです」 男は「られる」を強調して話した。どうやら言い間違いではないようだ。意外にも聴衆は冷静に次の言葉を静かに待っている。私もこの男が何かのレトリックとしてこのような事を逆説的に言ってるのではないかと思っていた。 「いじめる側の子供達は、元はと言えばそのようなことをする子ではないのです。いじめられっ子さえ現れなければ、普通に楽しい学校生活を送ることが出来た筈のいい子ばかりです」 さすがにこれはまずいだろう。普段いじめ問題には無関心な私にはそんな資格は無いのかもしれないけど、さすがにこの男の意見には文句を言いたくなった。聴衆から野次が飛びまくるのではないかと思ったのだが、まだ誰も声を上げない。 「いじめられっ子は話し方やその振る舞いで、普通の子供達の健全な心を蝕み、暴力を振るったり酷いことを言ったりするような子供に変えてしまうのです」 ここまで無茶苦茶な事を言っているのに誰も文句を言わないのはどういうことだろう?私はこの男だけでなく他の聴衆に対しても苛立ちを覚え始めた。 「いじめられっ子はそうすることで、普通の子供達の豊かな心が失われて行く様子を見るのが大好きなのです。そのためだったら何をされても我慢する、いや我慢することすらも楽しみにしている、そんな悪魔のような子供たち、それがいじめられっ子です」 もう限界だ、聞くに堪えない。この場で講演者に抗議する勇気を持ち合わせていないのは恥ずかしい限りだけど、ささやかな抗議の意味を込めて私は会場から抜け出すことにした。 「例えばほら!今ここを去ろうとしているあの人を見てください」 男が私を指差して叫んだ。ご丁寧にピン・スポットまで当たる。 「彼を見てると皆さんの優しい心が少しずつ失われて行くのが解りませんか?酷い目に合わせたいという悪い感情が沸き起こってくるでしょう」 聴衆は一斉に私を見た。皆、私に敵意を向けている。私にいじめられっ子の素養があったのだろうか。まずいことになってきた。 「ここで、その悪い感情に負けてしまっては卑劣ないじめられっ子の思う壺です。皆さんのお子さんや生徒さんも、いじめられっ子の前では今の皆さんと同じように純粋な心を蝕まれます。この気持ちに打ち克つ方法を今日は是非とも体で覚えて子供たちに教えてあげてください」 いろいろと酷いことを言われて最低な気分だが、どうやら命だけは助かりそうだ。どうやるのかは知らないが悪い感情というやつに打ち克ってくれ。私は一刻も早くここから逃げ出すとしよう。 「悪の感情に負けないよう、心を無にして悪を征伐しましょう。そうすれば皆さんの心は綺麗なまま、いじめられっ子の悪魔のような楽しみも奪うことができます」 無表情な集団が私に迫ってきた。
「少々変わったお願いなのですが、聞いていただけますか?」 疲れきった顔の依頼人はゆっくりと話を切り出した。
「ええ、ここにいらっしゃる方でありふれた依頼の方はいらっしゃいませんよ。どうぞご安心ください」 得意のマダムキラースマイルで私は答えた。依頼人にはあまり効果がないようだ。安藤が後ろで笑いをこらえてる。 「実は」 ここで小声になる、どの依頼人も一緒だ。「殺して欲しい人がいるのです」 視線を逸らすところも皆同じだ。 「解りました。それではご依頼の前にこちらのルールをお伝えします」 以前は一度はぐらかしたり何のことか解らないと惚けて反応を見るようにしていたのだが、最近は間を置かずに交渉をすることにしている。「ルールに納得していただけたらご依頼をお聞きすることにします」 「解りました。おっしゃる通りにします」 この段階でどのくらい本気で依頼しているかがなんとなく解る。具体的にどう違うと訊かれると困るのだが。 「ルールはとてもシンプルです。"一度依頼したらキャンセルはできない", "依頼内容が漏れたら依頼人に責任を取ってもらう" この2つだけ。いかがですか?」 録音されたときに備えて物騒な言葉は使わないようにしてある。 依頼人が少しだけ笑った。「安心しました。それなら必ず守れます」 ルールその2について質問してこないとは珍しい。 「それでは、ご依頼内容をお聞かせください」 休み明け最初の仕事はすんなりと決まりそうだ。 「はい、殺していただきたいのは…、私です」 依頼人は消えそうな声で依頼内容を告げた。ありがちな依頼だけど実際に受けるのは初めてだ。 「実行の日時は?」 「できるだけ早く」 「方法のご指定はありますか?」 「お任せします」 ズドン 「あ、馬鹿。じゃなくて、えーと、なんてことするんですか!」 安藤がどたどたと駆け寄って来た。 「安藤ちゃん、拳銃持った人に馬鹿って言ったね。言ったよね」 せっかくシンプルに片付いた仕事にケチを着けられて私は気分が良くない。 「そんなことより、どうするんですか?この人。」 安藤は銃口を避けながら泣きそうな顔をしている。 「どうするって、またいつものようにちゃちゃっと片付けちゃってよ」 後片付けは見習いの重要な仕事だ。未来の巨匠を目指して頑張れ。 「そうじゃなくて。お金ですよ、お・か・ね。取りっぱぐれちゃったじゃないですか」 そういいながら安藤は依頼人の所持品をあさり始めている。 「やばっ。安藤ちゃん言ってくれないんだもん」 安藤が鞄を探っている間に衣服をチェックしたが現金は一切出てこなかった。 「言う暇なんか無かったじゃないですか」 泣きをいれながらも、鞄に入っていた財布を探っている。 「何かでてきた?」 「財布には現金が2万ちょっと。キャッシュカードとクレジットカード、免許証、あとはいろんなポイントカード類ですね」 「2万しか持たないで来るか普通。あ、一応指輪とかもチェックしてね」 ときどき物納しようとする人がいる。そういう人には自力で現金に換えてから来るよう言ってるのだが、今回はそうも行かない。 「先生。被害者の周りにカメオの割れたやつみたいのが落ちてるんですけど」 「被害者とはなんだ。依頼人と言いなさいよ」 まったくデリカシーの無い奴だ。 「これ。撃たれたときに砕けたんじゃないですか?多分凄く高いものですよ」 安藤が言うのだからきっとそうなのだろう。欠片を見ただけで私にも露骨に高価なものと解る。これなら物納でも受けてたかもしれない。 「しゃーない。依頼人が払ってくれないなら関係者から頂くとするか。安藤ちゃん、こちらさんを丁寧にお送りしたら身辺を調べてみて」 「払ってくれないのは先生のせいでしょうに。まったく」 安藤は依頼人を送り出す準備をしながらもまだぶつぶつ言ってる。 「うるさいなあ。ブランクがあったんでまだ頭が冴えないんだよ。安藤ちゃんも虫弾食らってみろっての」 復帰後の最初の仕事はこうして始まった。
「霊感とか強いほうですか?」
「霊感?存在しないものに強いも弱いも無いな」 「そんなことありませんよ。私なんかめっちゃ霊感強いんですから」 「馬鹿か注目されたいだけの目立ちたがりか詐欺師のいずれかなんだろう」 「酷いこと言いますね」 「もしくはその全部か」 「こういった話が嫌いなのは解りましたよ。だからってそんな言い方しなくても…」 「悪いけどオカルトを全否定しない馬鹿と議論する気はないんだ」 「あんまり酷いことばかり言うと呪いますよ」 「呪うというのは人対人の関係だけだよ。君が私を呪っているという行為が私の気分を害して悪影響を与えるという効果があることは認めよう。それが呪いなのだと定義すれば呪いというのは確かに存在するだろうね」 「難しいことを言ってるつもりかもしれないけど、要は心理的な効果しかないって言ってるだけじゃありませんか。もう頭に来た呪ってやる」 「私にはそれを止める権利はない。君が私を呪うことによって私はとても傷つくがそれは仕方がないことなのだろう」 「あんたみたいな人でも私に憎まれると傷つくの?」 「そりゃそうだ。美しいご婦人から憎まれるというのは、その人がいくら馬鹿で目立ちたがりで詐欺師であっても辛いことだ」 「あったまきた。絶対呪ってやる」 「ご自由にどうぞ」 「じゃあ今ここで呪うね。『あなたが大嫌いです。二度と会いたくありません』」 …呪われた。
深夜の海岸を散歩していたら、子供たちが亀を虐めていた。
「無防備にやってきてこんなところで卵を産むなんて」 「掘り返してくださいと言ってるようなもんだ」 「自分達は保護してもらえるという甘えがあるんだろう」 「大仕事を終えたような顔なんかするんじゃない」 「保護センターのおじさんがこれから卵を保護するんだぞ」 「気付けよ」 酷い言われようだ。この子達と口論しても勝てる気はしないが、俺も一応大人なんでたしなめることにした。 「はいはい。君達、亀を虐めるのはやめなさい」 「虐めてなんかいませんよ。助言を与えているだけです」 「生きることの厳しさを教えてるんです」 予想していたとは言えこいつら手ごわい。ここで尻尾巻いて逃げるのも面白くないので何て言い返してやろうかと考えていたら、 「そうです。大いに参考になりました。僕の邪魔しないで下さい」 生意気にも亀が力強く反抗してきた。 「助けようとしている俺になんてこと言うんだこの爬虫類め。しかも卵産んでたのに僕って不思議ちゃんかお前は。だいたいしゃべるってのが気に食わねえな」 俺が甲羅を蹴り付けると亀が泣き出した。 「やっぱり、人間て酷い」 子供たちが俺を取り囲む。 「生き物の種類で差別するなんて」 「一人称に対する認識がステレオタイプすぎる」 「他の亀より優れていることがどうしていけないんだ」 気がつけば子供たちも泣いている。俺は逃げるようにその場を後にした。 竜宮城が経営不振に陥っているとしたら俺のせいです。
タクシーがウインカーを出さずに左折してきた。自転車が巻き込まれそうになったが間一髪のところで避けた。
「気をつけろ、このヘタクソ」 自転車に乗った少年が叫ぶ。高校生、いや中学生くらいだろうか。声を張り上げてはいるが結構冷静な顔をしている。 「ヘタクソとはなんだガキ」 よせばいいのにタクシー運転手が言い返した。 「ヘタクソだからヘタクソと言ったんだ。このど素人、サンデードライバ、1.5種免許」 少年の方は口喧嘩に慣れているようだ。 「てめえみたいなガキに運転が解るかってんだ」 運転手の方はただ怒鳴るだけで芸がない。私は少年に加勢しようと思ったがその必要はなさそうだ。 「ウインカーも出さないで、後ろも見ないで曲がるドライバがヘタクソでなくてなんだって言うんだ?」 脅しになるような事を言わないところが狡猾だ。 「屁理屈抜かすな、ぶっ殺すぞ」 運転手は自らを負けに追い込んでいる。 「副産交通さんはウインカーも出さないで左折して関係ない人を危ない目に合わせた上に殺すとまで言って来るんだ。ユニークな経営方針ですねえ」 少年は追い込みに入った。面白いからもう少し見てることにしよう。 「会社は関係ないだろうが、死にたいのかボケ」 運転手も自分がまずい立場にいることに気付いているのだろう。声が上ずっている。 「あれ、僕は副産交通さんの車両に轢かれそうになったんだけど。君は業務中じゃなかったのかな?」 勝利はとうに決まっているので、少年は運転手をいたぶり始めている。運転手が降りてきて手を出すのを待っているのだろう。 「うるせー、ぶっ殺してやる」 運転手がぶち切れた。自転車に乗ったまま挑発している少年を轢き殺そうと車を発進させたのだ。だが所詮頭に血が上った運転手の行動など充分に予想していたらしく、少年はすばやく反対側に避けた。 タクシーは歩道を超え郵便局に突っ込んで大破した。私と少年はタクシーの窓を叩き割りドアをこじ開け運転手を救出した。 「意外だね。君は助けないで黙ってみてるかと思ったよ」 と運転手を乗せた救急車を見送りながら私は言った。 「死なれたら困りますからね。たっぷりと敗北感を味わってもらわなきゃ」
義理で出席した展覧会のレセプション会場で人が殺され、私達は足止めをくらってしまった。本当についてない。予定が変わってしまったのが気に入らないのか、先生もかなりご機嫌斜めのようだ。私は努めて何気なく話しかけてみた。「それにしても、田岡さん、密室で死にたいって言ってたとおりになっちゃいましたね」
「何だって?」 この人、機嫌が悪いときは小声でも無駄に迫力がある。 私はびびってるのを悟られないよう平静を装いながら説明した。「田岡さんてミステリマニアとしても有名だったんですよ。本業の他にミステリの評論も書いててクラシックな本格好きの硬派な書評をする人として知られてるんです」 「で、密室で死にたいってのはどういうこと?」 先生はまだ怒っているみたいだ。話しかけるんじゃなかった。 「田岡さんが色紙にサインするときに添える言葉ですよ。ちょっと悪趣味ですけどね」 「なるほどね。なんとなく解ったような気がするな」 「え?密室のトリックが解っ、んぐぐ」 思わず大声をあげてしまったので、口を塞がれる。先生が睨んでいる、物凄く怖い。顎も痛い。 「だからさあ、そういうの止めようよ。いい年して恥ずかしくないの?人が一人死んでるんだよ。密室とかトリックとかふざけたこと言わない。解った?」 先生は周囲の人を刺激しないよう小声で、でも厳しい口調で私を責めた。顎を持つ手に更に力が入る。 「……」 私が必死に頷くとようやく手を離してくれた。ふう、死ぬかと思った。 今度は大声を出さないよう慎重に尋ねてみる。「あの、今、犯人が解ったって言いましたよね。誰なんですか?」 「話を良く聞けよ。解ったような気がするとしか言ってないよ。それに解ったのは誰かじゃなくてどんな人かって事だけだよ」 今度はそれほど怒っていない。 「だったら、その条件に合う人を探しましょうよ。犯人を見つければ事務所の宣伝にもなるかもしれないし」 「あのな、さっき言っただろう。警察の人が仕事してるのにどうして邪魔しようとするんだ?警察にも遺族にも失礼だろう」 どうして、こう変なところで筋を通すんだろうこの人は。「それに、事務所の宣伝になんかならないよ。却ってお客さんが減るだけだ」 仕方がないので、犯人が解れば早く帰れるかもしれないって方向で責めてみることにした。「でもこのまま黙って待ってるんですか?下手したら明日も帰れませんよ」 「じゃあ念のため、ちょっとだけ雑談でもしてくるか」 先生が渋々立ち上がる。私も慌てて後を追った。 私達から事情聴取をした刑事は、会場の隅の喫煙コーナーに居た。 「進藤さん。ご休憩中のところすいません。まだ掛かりますよね」 先生の声が営業モードに変わっている。 「ええ。ご迷惑をお掛けいたしますが、殺人事件ですのでご協力をお願いします。ほんとすいませんねえ」 進藤さんは口調は丁寧で明るく話すが、どうも油断のならない人のような気がする。 「はい、それはもちろん解ってるんですけど。帰りの飛行機をキャンセルしたり予約の都合もありますので。おおよその目安だけでも教えていただけませんか?」 「いつと言われましても私の判断では何とも決められませんので、後ほど皆様には公式にお知らせいたしますからもうちょっと待ってください」 それじゃ何も答えてないのと同じじゃないかと思ったけど私は黙って見ていた。先生も別に解放される時間を聞くのが目的じゃないのでそれ以上深追いはしないようだ。 「ええと、素人考えで申し訳ないんですけど、ちょっとだけ参考意見として聞いていただけませんか?」 先生はあくまでも下手に出て進藤さんに負けないくらい丁寧な口調を維持してる。 「ええ、良いですよ。どんな些細なことでも参考になるかもしれませんから」 ポケットに入れた手が少し動いた。録音しているのだろう。やはり抜け目ない人だ。 「田岡さんと普段からプライベートな付き合いがあった方がこの会場には大勢いらっしゃいますよね」 「そりゃもう沢山いますよ」 いつのまにか進藤さんの部下と思しき目つきの悪い男が、とぼけた顔をして聞き耳を立てている。 「その中で、進藤さんの印象で良いですから、頭が良くて遊び好きでちょっと世間を小馬鹿にしたような感じの人は居ますか?」 「ああ、一人居ますね。田岡氏と同じ…」 進藤さんは伏せるほどのことじゃないと思ったのだろう。あるいは先生が知りたがっていると思ったのかもしれない。 「おおっと。あまり深くかかわりたくないので具体的な名前は言わないでください。仮に太郎さんとしましょうよ。その方が女の人だとしても黙っててくださいね。その太郎さん、どっちかと言うとブラックユーモアが好きで子供っぽくないですか?」 「いや、まさにそんな感じですね。見てきたかのようです」 楽しそうに話してはいるけれど進藤さんの目は相変わらず笑っていない。元々こんな人なのかもしれない。 「あの、これが名誉既存になるんだったら聞かなかったことにして欲しいんですけど、やったのはその太郎さんだと思いますよ」 私は思わず声を出しそうになった。先生、根拠なさすぎますって。 「やっぱり」 意外にも進藤さんは即答した。既に雑談モードではない。 「なんだ、進藤さん、解ってたんですね」 先生は嬉しそうに言った。この人の場合は演技ではなく単に早く開放されるかもしれないという喜びだろう。 「いや、全然。ただ一番怪しいと思ってた者が私を含めて何人かいます」 「そうでしたか。余計なこと言ってすいませんでした。お恥ずかしい限りです。それでは失礼します」 先生はそそくさとこの場から去ろうとした。この辺の気の揉ませ方は、テクニックなのかそんなつもりなど最初からないのか一度訊いてみたいけど怖くて訊けないでいる。 「いや、ちょっとちょっと。せっかくだから何故あなたがそう思ったか話していってくださいよ」 進藤さんが慌てて先生を引きとめた。ちょっと素に戻ったのかもしれないなと思ったが、先生の退路をさっきの部下が絶妙に塞いでいる。慌てる必要などなかったのだ。これも油断させるための演技だろう。 「じゃあ、恥をかいたついでに荒唐無稽なこと言いますけど笑わないで下さいね」 先生は照れた態度を維持しながら簡潔に説明を始めた。「まず、田岡さんは事故死または病死で、太郎は本当の第一発見者です。そして太郎が勝手に他殺に見せかける偽装工作をして、部屋にも細工をしたのでしょう」 「いや、その意見は出ませんでした。ただ、今のお話で、詳しくは申し上げれないのですが、一つ不審な点があることの説明がつきます」 不審な点が何なのかは解らなかったけど、今の先生の説明からすると密室のことじゃなさそうだ。この人にとっても密室は不審な点でないのかもしれない。どうしてみんな目の前のトリックに無関心でいられるんだろう? 「しつこいようですが、素人のたわごとですので、こんなおとぎ話をしてた奴もいたって程度に捕らえていただくようお願いします」 先生は、もし自分の言ったとおりだとしても先生の功績にしないで欲しいと言いたいのだろう。 「ええ、面白かったですよ。どうもありがとうございました」 進藤さんもその辺はちゃんと解っているみたいだ。「ところで、どうしてそのようにお考えになったのか教えて願えませんか?」 「せっかくだから田岡さんを密室で死なせてやろうとしたんじゃないかなって思ったもので」 「それはミステリー好きな田岡氏に対する追悼のためですか?」 「いいえ、冗談だと思いますよ」 「結局、密室のトリックは解らなかったんですね?」 先生は帰りの目処がたってやっと機嫌が戻りつつあるが、今度は私が消化不良で不機嫌だ。 「まだそんな事言ってるの?殺人が起きたってのにそんなことを気にしてるのは数少ないミステリマニアのそれまたごく一部の君みたいな不謹慎なやつらだけだって。警察はそんなことに興味ないはずだし、そんなのは太郎に言わせるつもりだろう」 先生は私が社会に不適合な人間であると責めているようだ。 「そんなもんですかね。私は気になるんだけどなあ」 密室で人が死んでてトリックが気にならない人がいるなんて想像できない。 「君みたいな人がたくさん居ると思ったから、太郎もなめた真似をしたんだろう。今頃、証拠があるのかとかゴネてんだろうな」 ついに犯人と同類にされてしまった。 「実際、証拠があがらなかったらどうにもならないんじゃないですか?」 「あのね、連中をなめない方が良いよ。伊達に犬って呼ばれてないんだから。確実にやったっていう確信があれば、そんなのなんでも無いんだって」 どさくさに紛れてかなり失礼なことを言ってるような気がする。 「君ね、偽装工作をしたのが太郎だとして、田岡さんが別の人に殺害された可能性に関して進藤さん一言も言わなかったのに気づいた?」 もちろん気づいていた。だとしたら先生の仕業に決まってる。 「あのぉ、先生じゃないですよね?」 私がびびりながら尋ねると、先生は意地の悪い笑みを浮かべた。 「残念ながらハズレ。進藤さんの言ってた"不審な点"は死因だと思うよ。他殺ではない可能性が、既に見つかってたんだろう。俺がでしゃばらなくても犯人にたどり着いてたとだろう」 先生なら田岡さんを病死または事故死に見えるように始末することもできるような気がするけど、その点は怖くて訊けなかった。この人は怖くて訊けない事が多すぎる。 数時間後、犯人が捕まったらしく私達は無事解放された。進藤さんが一度こちらにやってきて缶コーヒーをくれたところを見るとどうやら先生の言ったとおりだったのだろう。滞在を一日伸ばしたり飛行機の予約を変更したりで出費が増えて先生はまた機嫌が悪くなったけど、これはいつものことなのであまり気にしないでおこう。私は私で最後まで密室のトリックが解らないので機嫌が悪いのだけど。
「じゃあちょっと行き詰ってるみたいだから、違った視点から質問しようと思うだけど良いかな?」
「はい、渡辺部長どうぞ」 「どうもありがとう。もし、的外れな質問だったらごめんね。僕の質問はこうだ 『歯ブラシは哺乳類だろうか?』 この点について考えていただきたい」 「……(アメリカンジョークだろうか?)」 「……(何を何に喩えてるんだろう?)」 「……(頭良い人ってこれだからなあ)」 「あれ?質問が突飛だったかな。では私の意見から言わせてもらうよ。歯ブラシは二足歩行をするから哺乳類だと思う」 「……(歯ブラシが二足歩行するかよ?)」 「……(二足歩行したら哺乳類って何だ?)」 「あのう。良いですか?」 「どうぞ」 「生物学的には哺乳類と呼べませんが、市場原理から言って哺乳類と呼べる可能性がないかは検討に値すると思います。例えば擬人化された歯ブラシと十二支のハイブリッドキャラクタなんか…」 「いや、そんなことを言ってるのではないよ。だいたい 『市場原理から言って哺乳類と呼べる』 というのはどう言う意味かな?哺乳類という言葉を生物学上の意味以外で使うことに何か意義があるとは僕には思えない」 「申し訳ありません」 「いや、皆が黙っている中、最初に意見を言ってくれた点は良かったよ。ちょっと厳しく言ったかもしれないけど気にしないで」 「……(生物学的って、歯ブラシはそもそも生物じゃないじゃん)」 「……(禅問答みたいだ)」 「反対意見なんですけど、私は哺乳類じゃないと思んですよね。だって哺乳類というからには卵で生まれなければいけませんよね。歯ブラシは卵から生まれないじゃないですか」 「田上君、何か別のものと勘違いしてないかな?哺乳類は卵生じゃないよ」 「でもカモノハシは卵を産むって動物奇想天外で見たことがありますよ。カモノハシってカモっていうくらいだから哺乳類ですよね」 「……(馬鹿。話をややこしくしやがって、三回転半くらい間違ってるし)」 「……(馬鹿な質問には馬鹿で返すという技か?)」 「では質問を変えよう『歯ブラシは哺乳類だろうか?それともカモノハシだろうか?』 これなら論理的に穴はないだろう」 「……(なんで二者択一になったんだ)」 「それなら、私は哺乳類だと思います。少なくともカモノハシではないことは明らかですから」 「……(沢田が切れた)」 「……(あきらかに投げやり)」 「私はさっきも言ったんですけど、カモノハシだと思うんですよね。だって歯ブラシの卵ってなんか気持ち悪いじゃないですか」 「……(お願いだから黙っててくれ)」 「田上君と沢田君以外に何か意見のある人はいないのかな?」 「……」 「……」 「それではこの件に関しては僕が預かろう。幸い最終決定は明日の午後だ。一度頭を冷やして明日もう一度、採決を取ろう」 「……(ていうかキャンペーンガールは結局どっちにするんだよ)」
「お兄さん、奴隷要りませんか?安くしておきますよ」
「奴隷って?あの奴隷ですか」 「あのって言われても困りますが奴隷です。英語で言えばスレイブね」 「いや、間に合ってますから」 「間に合ってるって、お兄さん奴隷持てるようには見えないなあ」 「そりゃ持ってませんて。奴隷を必要としてないって言ってるんです」 「でも、お兄さん奴隷がどんなもんだか知らないでしょう?知らないで間に合ってるってことも無いんじゃないですか?」 「じゃあ言い換えましょう。興味がないし知らないし知りたくもないし欲しくもない」 「花を入れる花瓶もないしイヤじゃないしカッコつかないし」 「僕、忙しいんですけど、もう良いですか?」 「ごめんなさい、調子に乗ってしまいました。もうちょっとだけ聞いてくださいよ」 「じゃあ、電車一本遅らせますからそれまでですよ」 「ありがとうございます。手短に説明しますと、奴隷はあなたの家に住んでいろいろな労働をします。バイトとか仕事をさせても良いです。その場合は給料をすべてあなたに差し出します」 「まさに奴隷なんですね」 「ただし、エッチなことはなしですよ。あくまでも労働力としてお使いください」 「あ、そうなんだ。でも禁止してても買った人がその約束を守らないってことはないんですか?」 「そういう事があった時はね、自決するよう暗示がかけられてるの」 「結構厳しいんですね。モラルの問題ですか?」 「いえいえ、モラルって奴隷に何を。そういう仕事させると奴隷販売の許可が下りないんですよ」 「あ、合法的な商売なんだ」 「もちろんです。ちゃんと認可を受けてます。だから奴隷は戸籍を抹消してありますし、酷使して弱ったとしてもあなたは罪に問われたりしません」 「てことは病院にも連れて行けないのかな?」 「あ、その点は心配なく。奴隷用の保険を用意してますので」 「保険とかはあるんだ。人道的配慮ってやつ?」 「いえいえ、人道的配慮って奴隷に何を。物損保険みたいなものです」 「シビアなんですね」 「で、気になるお値段ですが」 「いや気にしてないですから」 「そんなこと言わずに、ほら、見てくださいよこの写真。三十代働き盛り健康状態良好体力あり従順でおとなしい好青年奴隷がなんと150万円!一年で元が取れちゃいますよ。どうですお兄さん」 「買う気は更々ないけど随分と安いんですね。ていうか男なんですね。ややこしいこと言ってたけど」 「あ、興味律々ですね」 「興味ないですから。あと律々じゃなくて津々ですよ」 「もったいないなあ、こんな良い奴隷って滅多にないんだけどなあ。まさにお勧め!本日の目玉奴隷!」 「目玉奴隷ってのも何だか気持ち悪いなあ」 「そんなこと言わずにお願いしますよ、ここんとこ成績悪くって今月ノルマこなさないと私、営業から資材になっちゃうんです」 「配置換えですか?」 「ていうか営業担当から資材そのものになるんですけど」 「あ、奴隷になっちゃうんだ。社員から商品へのドラスティックな転身ですね」 「ええ。助けると思ってお願いしますって」 「うーん。そういわれてもなあ」 「今ならかわいいプチ奴隷もつけますよ」 「そういうの可哀想だからやめようね」 「マスコット人形なんですけど」 「ほっ」 「どうしても駄目?ちらっ」 「だからスカートめくらなくて良いですから」 「ねえ、お願い」 「お姉さんが奴隷になったら貯金おろしに行ってたかもしれないですけど」 「酷い、人がこんなに苦しんでるって言うのに。鬼!悪魔!人でなし!」 「奴隷商人に言われてもなあ…。もう電車が来ますので、じゃあ」 「ぐっすん」 - - - - - * - - - - - 「兄ちゃん、兄ちゃん」 「なんすか?」 「奴隷買わない?奴隷。ニ十代後半健康状態良好体力あり性格はちょっときついけど器量良しの新人が200万円。どう?」 「ひょっとして先月まで営業だった人?あの眼鏡の」 「あれ?知ってんだ、なら話は早い。どう?」 「うーん。どうしようかなあ。あの、ひとつお聞きしたいんですけど、彼女って一生奴隷のままなんですか?」 「そこはそれ、うちはなんせ公認奴隷販売業だから、ちゃんと人権再生の手続きってのもあるんよ」 「あ、あるんだ。ちなみにおいくら?」 「ずばり諸費用込みで100万円。良心的でしょ」 「うーん。高いなあ」 「何言ってんの。これでもほとんど実費なんだから。あと勘違いしてたら困るから言っておくけど、人権再生手続き完了時点で奴隷所有権は放棄されるので200万は帰って来ないからね」」 「でもなあ、300万は払えないなあ」 「ローンもあるよん。兄ちゃん、ちょっとは責任感じてんでしょ。だったらここはかっこいいとこ見せようよ」 「しょうがないなあ」 結局、僕は300万のローンを組んで彼女を解放することにしました。彼女に恩を着せようと言う下心があった事は否定しません。開放された彼女は感謝はしてくれましたが、すぐに元の奴隷販売の営業に戻っていきました。ローンには巧妙な仕掛けがしてあり、半年後には僕はローンが払えなくなってしまいました。で、いろいろあって今は彼女の手持在庫として出荷を待っているところです。
「だからさ、君の書くのはどれも理屈っぽくて、どうも読む気が失せんの。なんかこう感情が伝わってこないっていうかさ」
「感情的にわめかせたり、気持ちをストレートに描写するのってむしろ感情が伝わらないじゃないかと思うんですよ」 「だからって極端に省略することでより伝わると思ったら大間違いだよ」 「僕はこれでも書き過ぎてると思いますけど」 「うーん。じゃあさ、せめてもっとでたらめで不条理な世界を書くことはできない?」 「今でも、結構突拍子もない設定の話ばかりのような気がするんですけど、もっとありえない設定にするんですか?」 「そうじゃなくて、君の場合は設定は変わっててもその設定の中で整然と話が進むじゃない。もっとルールがぶっ壊れた世界があっても良いんじゃない?」 「そんなのいくらでも書けますけど、面白く無いですよ、きっと」 「書けるって言うんならひとつ書いてみてよ。それからもう一回考えてみよう」 - - - - - * - - - - - 月は僕の真下から10秒おきに水色のどろどろとした光を放っている。光に手をかざすと生ぬるいジェルがべっとりと付着する。ラードの匂いがする。僕の恋人は相変わらず僕の帽子の中で寝ている。彼女はラードが好きだ。中華料理も好きだ。ジェルを帽子の内側に少し塗りつけてやると彼女の寝息が赤く染まる。もう春も終わりだろうかそんなことを考えながら僕は歩道橋をまたひとつ撤去した。 「熱心な仕事っぷりだね」 社長が僕に声をかけた。「あ、起きたんだね」 彼女は僕の社長でもある。「君は中々見所があるよ。あとタンメン三杯ね」 どうやら寝言のようだ。顧問弁護士が現れ「今のは三波社長の寝言に間違いありません」 と念を押しに来た。もう春も終わりだろうか。 そんなある日、僕の鞄をノックする人が4人も現れた。「トントンあるよ」 いずれもインド人だ。カレーなら間に合っている。僕がそう伝えるとインド人たちは激怒した。「インド人をなめたら怖いで」 面倒なのであとは執事に任せて僕はバイトに出かけることにした。彼女はまだ帽子の中で寝ている。ラードは酸化が進み蝋の匂いへと変わるだろう。「サイレント・ナイト、ホーリー・ナイト」 彼女の寝言はいつもシュールだ。もう春も終わりだろうか。 - - - - - * - - - - - 「こんなのだったら、何百行でもかけますけど」 「ごめん、なんか違う。やっぱ好きなように書いた方が良いみたいだね」 「ご期待に添えなくてすいません。でも少しほっとしました」
「すいません。ちょっと失礼してカートリッジの交換を」 只野氏はそう言って鞄を探っている。言われてみると確かに彼のメットの中の空気が澄んでいて、話を始めたときよりも顔がはっきりと見えている。只野氏は胞子補給器を止め、大急ぎでカートリッジを交換して再度補給器のスイッチを入れた。メットの中は一瞬にして胞子で満たされる。きな粉を更に細かくしたような塵がメットの中で舞っている。何度見ても気分が悪くなる光景だ。
「話の腰を折ってすいませんねえ。カートリッジ交換が要らないタイプのも出てるんですけど、あれは高くて手が出ないのですよ」 只野氏はやっと楽になったらしく話し方も明るい。 「いえいえ。こちらこそ、いつもお越し頂くばかりで申し訳ございません」 「いやあ、私共の方に来て頂く訳に行かないのは、こちらさんとお取引をさせていただく以上当然のことですから」 もし行くとしたら宇宙服みたいな大げさな装備が要るだろう。 「それにしても大変そうですね。今回のように長期のご滞在だとカートリッジも沢山居るでしょう?」 「その点は大丈夫なんですよ。呼気から抽出してこちらで再生できますので、予備も入れて4本もあれば繰り返して使えるんです」 なるほど、鞄が大きいと思ったら再生装置が入っているのか。良く見るとメットから鞄へ管がつながっている。多分、交換の要らないタイプってのはメットだけで再生と供給が同時に出来るのだろう。 「そうでしたか。今回のお話がまとまれば、御社の技術担当の方が使う専用室をご用意いたしますので、その際は只野さんも装置なしにご滞在いただけると思います。それまではご不自由でしょうけどよろしくお願い致します」 専用室の用意にはかなりの出費を覚悟する必要があるが、彼らの持つ技術を独占契約できることに比べればどうってことない費用だ。 「ありがとうございます。そうしていただけるととても助かります。うちの技術担当も喜ぶでしょう」 胞子で曇って表情は良くわからないが、只野氏も嬉しそうだ。やはり装置での呼吸は面倒なのだろう。 「それでは、契約書の素案と仮契約の書類がこちらに入ってますので、ご検討をお願いし…」 只野氏の様子がおかしい。メットを押さえたまま動かない。「どうしました?大丈夫ですか?」 胞子で霞んだメット越しに顔を覗き込んだが、口から血を吐いている。脈もない。気の毒にも補給器の故障で亡くなってしまったのだろう。私は内線で総務部に連絡を取ろうとした。そのとき、只野氏の鞄で小さな破裂音がした補給器の外部装置が壊れたのだろう。鞄から黄色い微粒子が溢れ始めた、只野氏のメットの隙間からも吹き出している。今度は私が危ない、只野氏には悪いが、何もかも投げ出し大急ぎで会議室を飛び出した。外では部下が出口に簡易エアシャワーを直結して待機していたので被害は最小限にくい止めることができた。 エアシャワーから出ると、若い連中が会議室のドアを目張りしたり、胞子を除去するための薬剤を散布している。 「お疲れ様でした。とんだ災難でしたね」 「私は無事だったけど、只野さんは気の毒だったな。でも契約はほとんど成立していたわけだし彼らもドライな連中だ。仕事はこのまま進むだろう」 実際のところ私達より彼らの方がはるかにビジネスライクだ。すぐに代わりの担当者が飛んでくるだろう。 「この部屋の空調は完全封鎖して、窓も外から目張りをしているところですので他の部屋へは広がることはない筈です。しつこく事前に対策を検討しておいて正解でしたね」 「部長に礼言っとかないとな」 部長に先見の明があったのではなく、単に胞子を異常に怖がっていただけなのだが、結果として綿密な事前対策のおかげで私もこうして無事に生きてるわけだ。 「それにしても、会議室一つ駄目になっちゃいましたね」 すでに会議室は黄色い霧で満たされている。確かにすべて除去するのは諦めた方が賢明かもしれない。 「そうだ、例の専用室、ここにしよう」 かなり胞子の濃い部屋になりそうだ。先方の技術担当者も喜ぶだろう。
「解った、要求を聞こう」 拡声器から刑事の怒鳴り声が響き渡る。
「いいかあ、人質の命が惜しかったら、今すぐ百億万円持って来い」 警察と野次馬と人質の間に別の緊張感が流れた。相手は武器を山ほど持っている、笑ってはいけない。そう思うと余計笑いを堪えるのが難しくなる。人質の一人が緊張に耐え切れず笑い出した。「ぶはぁ、ひゃひゃ百億万円。ひーひー、駄目だ可笑しすぎ」 つられて周りの何人かも笑い出した。「幾らだっつーの」「小学生でも言わないっての」 「うるせー、どこがおかしいんだ!」 犯人は笑い転げる人質に銃を向ける。人質たちは我に帰り、笑いは嘘のように収まった。「おい、お前。俺のどこが間違ってるんだ。言って見ろ」 犯人は最初に笑った人質に命令した。「いや、だって、ひゃひゃ百億万円。ぶははは、もう駄目だ我慢で」 ズドン。 最初の犠牲者が出た。もう笑い事ではない。刑事の怒鳴り声がまた聞こえてきた。「おい、何があったんだ。人質に何かあったら只じゃおかないぞ」 「うるせー、生意気な奴を一人始末したぞ。これ以上死人を増やしたくなかったら今すぐ百億万円用意しろぉ」 再び人質に緊張が走る。笑ったら撃たれると思うと余計笑いたくなる、後ろ手に縛られているので口を押さえて堪えることもできない。 刑事は増幅する笑いと戦いつつ、ここで笑っては犠牲者が増えるだけだと何度も自分に言い聞かせながら説得を続けた。「わ、解った。要求を呑もう。ただ金額が大きいので少し時間がかかる。もうちょっと待ってくれ。なんせ、ひゃひゃ百億万、うわはははは」 ついに刑事も笑い出してしまった。犯人は外に向って手榴弾を投げつけた。野次馬や他の警察官をはじめ多くの人が巻き添えをくった。 結局その後、数多くの人質と警察関係者と報道陣が犠牲となった挙句、日本語が解らない外国人の手を借りてようやく犯人を捕らえることに成功した。取り調べも裁判もかつてない爆笑の中進められた、 五年後、犯人の死刑が執行される日が来た。 「何か言い残すことはありませんか?」 執行官が尋ねた。 「百億万円が欲しかった」 犯人は自嘲的につぶやいた。 「そのネタ飽きたよ」 誰も笑わなかった。
「サトラレって流行ったじゃないですか」
「ええ、そういう映画が作られてヒットしたようですね」 「あれのパロディで『サトラセ』って考えたんですけど、面白いと思いませんか?」 「タイトルだけでは面白いとは思えません」 「『サトラセ』は、Aさんの考えてることをBさんに解らせることができるのです」 「ということは、Aさんとして自分を設定したら『サトラレ』で、Bさんとして自分を設定したら『サトリ』に相当する訳ですね」 「えーと、それだと面倒だからAさんBさんは自分以外にするのです」 「機能上の制限としてそれほど不自然ではないので、それでも良いかと思います。もう三点、AさんとBさんとして同じ人をセットすることはできないことにしますか?また、二組以上同時にその能力を発揮できますか?最後に一対他もしくは他対一で同様のことが可能ですか?」 「それはどれも考えてなかったのです。最初のは、そんなことされたら頭がポーンって爆発しそうなので、できないことにします。次のもその次のも面倒なのでなしにします」 「まとめると『サトラセ』は自分以外の任意の異なる二名の間に思考過程をモニタするための一方通行のパイプのようなものを一本だけ自由に取り外しができる能力を持つということで良いですか?」 「多分それであってるんだと思います。どうでしょう、面白くないでしょか?」 「あ、もうひとつ気づいた。AさんとBさんの間に作られたパイプは『サトラセ』がはずさない限り永久に残りますか?続くとしたら『サトラセ』が死亡した場合や記憶喪失になった場合はどうなりますか?」 「うーん。それはどっちにした方が話が面白くなるかで決めるのです。先に決めた方がいいですか?」 「いや、後でも良いです。その場合、決めるまではどっちに転んでも良いように途中の話を作ることが大事です。あ、また疑問が。その『サトラセ』の能力は万能ですか?つまり誰にも防ぐことはできないか、防げるとしたらどんな人かを決めておいた方が良いです」 「むむう。どんどん複雑になってきたのです」 「そういえば、Aさんが英語圏の人でBさんが英語を理解できない場合はどうなるのか?そもそもAさんの考えてることは、どのような形式でBさんに伝わるのかも気になります。あと、Aさんの考えていることと言っても、表層の思考からAさん自身もはっきりと意識していない深層の心理まで広い範囲がありますがそのどこまでをサトラセることができるのでしょう?」 「うーん。何だか面倒になってきましたよ。それにしてもどうして、そう次々と疑問点を思いつくんですか?」 「モジュールテストの基本です。いやオブジェクトの設計の段階でこれくらいのことは想定しておくべきです。あとは『サトラセ』の効果はAさんとBさんの間の物理的な距離に依存するか、『サトラセ』状態にある場合に一方が死亡した場合に『サトラセ』は自動で停止するのか、それから…」 「もう、いいのです。別のお話を考えるのです」
いつもの朝食の香りで目が覚めた。「ごはんができましたよ」 妻の声がする。それにしても妻はいつでも楽しそうに働く。二人とも、もう老人と呼ばれてもおかしくない年齢になったが人里離れた奥地でこうして二人だけでなんとか暮らして行けるのも明るい性格の妻のおかげだ。
「今日は良い天気だな」「雨は降らなさそうね」 特に話題もないせいか食事のときはつい天気の話ばかりしてしまう。朝食を食べ終わり私たちはいつものように今日の予定を決めることにした。「食べ物はまだ充分にあるかな」 「ええ、あと4,5日はもちますよ」 「薪がそろそろ切れてきたんじゃないか?」 「薪はまだあるんですけど、細かいのがそろそろ無くなりそうですねえ」 「わかった拾いに行くとしよう」 「では私は洗い物が溜らない前に洗濯でもしましょうか」 珍しく二人揃って家を出て途中まで一緒に歩くことにした。「来週あたりから冬の支度も始めないと」 「いくらなんでも、まだ早くないか?」 「そういって毎年雪が降りそうなころに慌てるでしょう」 そんな他愛も無い話をしているうちに山道の入り口についた。「気をつけてくださいね」 「ああ、篭いっぱいに集めたら帰ってくることにするよ。お前も川に落ちないようにな」 「はいはい」 妻は山ほどの洗濯物を抱え軽快に川原へと向かって行った。私もこうしてはいられない。西の斜面はまだ地盤が緩そうなので、南側に回って小枝を集めて来ることにしよう。 ふと、昨夜納屋にしまってあった大きなまな板と包丁を取り出し、手入れをしたことを思い出した。特に使う当ても無いのだが、そうせずには居られなかったのだ。何故だろう。今日は不思議な事が起きそうな気がする。その不思議な出来事にまな板と包丁が役立つのだろうか?
「あなたは、人間ですか?」
上下がつながった銀色の服に身を包み、不思議な髪型をした男が私に尋ねた。明らかにおかしい奴だ。こいつは何を訊こうとしているのだろう?人間ですかって、そりゃ人間に決まっているだろうが。 いや、待て。私は自分が本当に人間であると証明できるであろうか?まず、外見から考えると少なくても人間に近い生き物であることは確かなようだ。話がややこしくなるので、私が見ている私の外見は正しいものとしよう。私の意識や感覚は夢や幻ではなくリアルに私が体験しているということを疑いだすと際限がない。だいいち、犬を眠らせて頭に電極をつなぎ、人間としての自分の記憶や体験を植えつけて何の意味がある? 話を戻そう。さっき、思わず「人間に近い生き物」と言ってしまったが、その前に生き物でないかもしれないということを疑うべきだった。私が作り物でないとはどうやって証明できるのだろう?一応生命活動はしていて新陳代謝もあるので生物ではあると思うが、それも含めて完璧に再現する事ができるようになったら、自分自身では区別がつかないのではないだろうか。これも疑いだしたら際限がない。ここもとりあえずそんなことは無いと思っておこう。さっきからどうも荒唐無稽な考えばかりが頭に浮かぶ。この男の外見に毒されているのかもしれない。 さて、私が作り物でないとして果たして本当に人間であるのだろうか?極端な話をすれば、別の星のまったく異なる種類の生き物が人間の形をしてるということだって…。ああ、また馬鹿らしい事を考えてしまった。そこまで極端なことを言わなくても、例えばまだ発見されていない未知の生き物である可能性もあるわけだ。生物学的に検証してみたら人間に非常に近いものの別の種類の生き物であるという結論に達してしまったら、私は人間ではないということになるのだ。 いや、待て。生物学的に別の生き物だからと言ってそれがすなわち人間で無いと言っても良いのだろうか?人間として生まれ育って社会の中で暮らしているにもかかわらず、生物学上の特徴だけで安易に人間としての権利を剥奪するような事は極めて危険なのではないだろうか?いやいや、それはまた別の問題か。もし、極めて人間に近い別の生物であることが判明した場合には、その生き物が人間であるかという問いと人間としての権利を有するかという問いは別々に考えるべきだろう。 あれこれ考えては見たが結論は出ない。おかしな格好をしているが、なかなか考えさせられる問いかけをしてくる奴だ。只者ではないのかもしれない。 男は再び私に問いかけた。「あなたは、人間ですか?」 仕方がないので正直に答えることにした。「私は自分の経験から自分が人間であると確信している。少なくても人間と呼ばれる権利は持っているつもりだ。ただ、生物学的に人間であるかを検証したことも無いし、証明する手立てもない」 私の答えに満足したのか男は大きくうなずいた。「そうですか。それではあなたは人参ですか?」 やっぱ、ただの馬鹿じゃないか。
乗り換えの駅のホームで僕は電車を待っている。いつもと同じ時間、いつもの5番乗車口、そして左斜め前にはいつものように3組の吉田さんが文庫本を読んでいる。相変わらずちょっと不機嫌そうな顔をしているが、これは本を読むときの癖らしい。今日こそは好きだと言おうと思い続けて、既に678時間が経つがまだ言えないでいる。
電車がやってきた。意を決して今日は吉田さんのすぐ隣に立つことにした。彼女は僕に気付き軽く挨拶をするとまた文庫本に目を落としている。「吉田さん、ちょっといいかな?」 「いいよ」 本を読んだまま答えた。「あの、何て言うか、ええと。好きです」 かなりみっともないが何とか言えた。吉田さんは何て返事をして良いのか困っているようだ。 そのとき後ろから声がした。「立花、ちょっと待てよ」 田中だ。「俺も吉田さんが好きだ」 こいつどさくさに紛れて便乗しやがった。「だったら言うけど、私は田中君が好き」 いつの間にか井上さんまで話に加わってきた。「ちょっと何言ってるの、私なんか一年の頃から田中君が好きだったんだから」 誰だか解らない女も絡む。どうでも良いけど田中大人気だ。「ついでで悪いんだけど私は立花君が好き」 と今度は英語の佐野先生。車内にどよめきが起きる。まじっすか先生。「5組の木村でーす。佐野先生考え直してくださーい」 「鈴木です。井上さんが好きです」 「この速さなら言える。俺も田中が好きだ」 「吉田さんの眼鏡になりたい」 「私はベッカム様が…」 「僕はあややが…」 「俺にも言わせろ」 電車は進む。
「集合!全員揃っているか?我々は就寝中に何者かに拉致されここに閉じ込められたようだ。誰かここに来るまでの事を覚えていないか?」
「覚えていません」 「気が付けばここに居ました」 「私もです…」 「居ないようだな。それでは手分けをして状況を把握すること。何か不振なものを発見したものは速やかに報告すること。良いな」 「はい」 「隊長!爆弾らしきものが見つかりました」 「田中と佐藤は、爆弾の調査に回ってくれ。他の者は引き続き調査を続行すること」 - - - - - * - - - - - 「集合!では、状況の復習だ。立花、現在の状況を20秒以内で話せ」 「はい。この爆弾は30分以内に爆発します。爆発した場合には、我々全員が確実に死亡する規模の爆弾です。この場からの脱出は既に4時間以上試みていますが、成功していません。爆弾解体作業の結果、ここにある赤と青の線のどちらか一本を切ると停止する状態にまでこぎつけました」 「よし。この場合我々が確認しなければいけないことは何だ」 「ひとつは情報の精度の確認です。赤と青のどちらかを切れば確実に止まると言うのは信じて良いのか、爆弾の規模の見積は正確か、30分より早く爆発する可能性はないのか」 「その点に関しては、鈴木と佐藤の知識と経験を信じることにしよう。他に判断材料がない。他に確認すべきことは?」 「この爆弾以外に我々にとって危険なものは存在しないか調べる必要があります」 「よし。それでは、我々は何をしたら良いか言って見ろ」 「はい。一つは赤と青の線のどちらを切れば良いのか知る手段が無いか検討することです。これは引き続き鈴木さん佐藤さんにお任せ致します。残りのものは他の危険性の排除に努めます」 「良いだろう。それではタイムリミットを20分後とする。ただしその時点まで何らかのアクシデントがあったら誰でも良いから召集をかけること。何か質問は?」 「20分後にどちらを切って良いかわからなかった場合はどうしますか?」 「助かる確率は1/2以下だ。俺が切ろう」 - - - - - * - - - - - 「申し訳ありません。結局どちらか解りませんでした」 「仕方が無い、俺が切ることにしよう。恨みっこなしだぞ」 パチン 「ふう、助かったようだな。ん?何だこの音は」 「うわっ煙がっ!」 「前が見えない」 「ゲホゲホ」 - - - - - * - - - - - 「集合!全員揃っているか?我々は就寝中に何者かに拉致されここに閉じ込められたようだ。ここに来るまでの…」
あっどうもどうも。いやー嬉しいですねえ、こんなにご声援をいただけるなんて。改めまして皆様こんにちは、21世紀最初の奇跡、ジーニアス・天才でございます。今日は「本格英才教育援助基金のためのチャリティライブ」ということでこんなに多くの皆様にお集まり頂いて本当にありがとうございます。まずはトップバッターをあたしが務めさせて頂くこととなりました。なんか噂では年齢で順番きめたんじゃないかって言われてますけど。あとは、背の低い順ね。だったら、どっちにしてもしばらくはあたしがトップでござんすね。それはともかく、皆様どうか最後まで楽しんで行ってください。
あたしもこーんな小さいころから、あ、すいませんここ笑うとこですよ、こーんな小さいころから、あっどうもどうも、今日は良いお客さんばかりだなあ。この前なんか中学校に営業にいったら、やれ全員の名前を覚えろとか、暗算やれとか、しまいには宿題を手伝ってくれとか、そりゃもう大変。えーと何でしたっけ、そうそう、こーんな小さいころから天才やってますんで、解るんですけど天才は天才でなかなか大変な苦労があるんですよ。本当は奨学金とか貰って大学とか行きたいんですけど、なかなかこの年だと出してくれないんでねえ。どうなってんでしょうこの国はとか管巻いたりしちゃってね。ジュース飲みながらですけど。あたしの場合運良く親切な方が大学に行かしてくれたんですけども、いろんな事情でせっかくの才能を使う機会の無い子が大勢いるってんで、ちょっとでもお役に立てたらなあと思ってこうやってお声がかかれば、つたない芸をご披露して基金のためのご寄付を頂いてるってわけです。 今日は皆様にあたしの十八番「人間メモ用紙」を見ていただきましょう。ま、あたしがお見せできる芸ったら「暗算ネタ」と「記憶ネタ」しかないんですけどね。いま、当事務所の優秀なスタッフが皆様にボードをお配りしますので、しばらくお待ちください。スタッフってあたしの母ちゃんなんですけど、母ちゃん苦労かけるね、息子は今稼いでるところですよ。今日のお客さんはついてますね。見れませんよ普通、母親にバニーの格好でアシスタントさせてる芸人なんて。あたしもマジックショーじゃないんだからやめなよって言ってんですけどね。お前の為だよとか言ってるけど、ありゃ絶対着たくて着てますね。あ、配り終わりましたか?それでは皆さん、今日は皆さんの好きな車の名前を書いてください。あんまり長いのはなしですよ。「日産スカイライン ゴールデンロイヤルサルーンデラックス 30周年特別仕様車」とか書いてもこっから読めませんからね。あれ、おばあちゃん車の名前知らない?おなじみの霊柩車でもなんでも良いんですよ。はい、よござんすか?では、あたしは10秒で100枚のボードに書かれた車の名前を全部覚えます。皆さんあたしが「はい」っていったら上げてくださいね。ここに時計がありますから、皆さん大きな声でカウントをお願いします。せーの、はいっ。 いやあ、今日のはさすがのあたしも難しかったですね。いつもはここで3分くらいおしゃべりしてから皆さんの書いた名前を思い出して見せるんですけど、ほら、ちょっと早口でしょ。なんか忘れそうで。えーと、今日は何の話をしましょう。そうそう、この前メールなんか頂いたんですよ。それがなかなか厳しい方で「お前のやってるのは、記憶力自慢だ。何が天才だ、ただのビックリ人間じゃないか」って書いてるんですよ。そりゃね、記憶力があるとか暗算ができるってのは天才でもなんでもないよってのはごもっともな意見なんですけど、あたしもね普段からちっこい体で大学行って、こんなことばかりやってるんじゃないんですよ。情報工学って言うコンピュータの勉強と中世のドイツ文学と分子生物学ってやつを研究してんの。名前だけ聞くと、なんだか大変そうでしょ。それがね、ほんと大変なの。特にあたしの場合は成りがこんなだから、学部から学部への移動が大変でって、それだけかい。ははは、今のは情報工学の専門用語で「ひとり乗り突っ込み」て言います。リピート アフタ ミー「ひとり乗り突っ込み」。いやあ、今日のお客さんは本当に良い人たちだ。で、あたしもこんな妙ちくりんな芸名つけちゃった手前、天才ですよってところをご披露したいんですけど、コンピュータでプログラム書いて見せたって、お客さん、面白くないでしょ。え?母ちゃんどうしたの?そろそろ時間だって?あららら、まずいね。さっきの車の名前覚えてるかな。おまけに袖から片桐師匠がこっちを睨んでますよ。それではさっさと終わらせちゃいますか。では左上の男前のお客さんから行きますよ。あたしね、記憶力は良いけど目は悪いの。さてと「ポルシェ」「消防車」「フィアットチンクチェント」「自転車」… …「ホンダシティ」あれ、次のお客さんは席入れ替わりましたね。騙そうったってそうは行きませんよ。こちらさんが「ミニカー」でこちらさんが「ミニカ」。そんでもって「クラウン」「霊柩車」で最後こちらのお姉さんが「フローリアン」と。あっどうもどうも、どもどもども。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、皆様「本格英才教育援助基金」をどうぞよろしくお願い致します。期間限定一年限りの三歳児、来年は早くも四歳!ジーニアス・天才でした。
資産家の老人が自宅で殺害された。
捜査が進むにつれて二人の容疑者が浮かび上がった。 両者ともアリバイがなく、犯行が可能で、充分な動機を持っていた。 最大の問題点は、両者とも売り出し中の人気モデルであることだった。 両者はともに容疑を否認し、また決定的な証拠もなく捜査は難航した。 捜査に行き詰った蟹丸警部は家に帰り息子に事件の事を話した。 (推理作家だか何だか知らないけど、事件の捜査過程を一般人に話して良いのかという疑問は忘れて欲しい) 「解りました、父さん。その二人と腕相撲をさせてください」 「そんなことで犯人が解るのか?」 「ええ、多分大丈夫です」 翌日、蟹丸警部の息子は二人の容疑者それぞれと腕相撲をした。 「それで犯人はわかったのか?」 「もちろんです。犯人は私に勝った方です」 蟹丸警部は根拠を求めた。息子は笑いながら答えた。 「彼女にナイフの握り方に特徴があるのですぐに解ったと伝えてください。多少誇張しても構いません」 脅しならお手の物だと蟹丸警部は息子の言うとおりにした。 容疑者は泣きながら自分が犯人であることを認めた。 「そろそろ種明かしをしてくれても良いだろう?」蟹丸警部は息子に尋ねた。 「死体の刺し傷には特に特徴的なナイフの使い方の痕跡はなかったじゃないか」 「まあ良いじゃないですか。事件は解決したのですから」 息子は、その根拠を語ろうとはしなかった。 もちろん息子は、最初から腕相撲をするのが目的だった。美人モデルの手を握ってみたかったのだ。自分に勝った方のモデルの態度が気に入らなかったので腹いせに犯人だと断定したのだった。
「記憶が残らないとか失われていくという話は数多くあるけど、逆にどんどん記憶が増えていくという話はどうだろう?」
「他人の記憶が流入するんですか?」 「まさか、そこまで荒唐無稽な話にする気はない」 「そう言えば記憶が残らないというのも実話がベースでしたね」 「私が言ってるのは、実際に体験したかのような想像ができるという人の話なんだ」 「想像力が強すぎて妄想がリアルなんですね」 「そう。例えば、今日始めて会った人に去年友達と3人で遊園地に行った話をしたとする。その際に『今度一緒に行きましょう』と言われた瞬間に、4人で遊園地に行くことを想像するんだけど、その人の場合は去年の記憶とその人の外見情報から4人で遊園地に行く体験を頭の中で作り出して記憶してしまうわけ」 「それが、想像なのかリアルな記憶なのか判別できないわけですね」 「判別できないというか、それはもうすべてリアルな記憶な訳だね。リアルと想像との区別を最初からしてないわけだから」 「区別してないというのは?」 「本人は小さいことからそれが当たり前になっているので、リアルな情報と自分の頭の中で作った情報とを区別する習慣が無いってこと」 「やっかいな子供ですね」 「もう少し、オプションを増やそう。さっきのケースだとその人の想像力が他の人より優れているのは、情報を合成する能力と再生する能力においてだったわけだよね」 「遊園地に行った記憶と今日会った人の外見情報から新しい情報を高精度で合成して頭のなかで再生したということですね」 「そう。更に、視点の変換の能力も図抜けているとしたらどうなる?」 「視点を変換するということはどういうことですか?」 「自分が今見てる光景を自分以外の誰かの目線に変える事ができることなんだけど。例えばさっきの例で言うと一緒に行ったのは自分ではなく、さっき初めて会った人だったという想像をすることができるというわけ」 「それは無理があるんじゃないですか?例えば身長が極端に違ったらどうします?一方の視点では確実に見えない部分がありますよ」 「さっき情報を合成する能力が高いって言ったよね。だから見えない部分は別の記憶から補うことは簡単に出来る筈。その点に関しては心配ないと思う」 「あ、そうか。見えない部分を本物で補う必要は無いわけですからね」 「そういうこと。便宜上『視点』と言ったけど聴覚や重力の感覚も変換できるという設定の方がより強力だな」 「つまりまったく別人としての記憶を体験することができるわけか」 「うん。これがエスカレートすると例えば、一緒に言った別の人の視点で記憶を再生することもできる。この場合、想像上の自分の中に本物の自分が登場するわけだけど」 「それって、自分が誰だか解らなくなるってことですね」 「それはちょっと違うと思う。区別してないのは『記憶』と『想像』であって、現在リアルタイムでインプットされ続けている情報とは明確に区別が付いているということにしたい。そうでないとかなり危ない人になってしまう」 「そうでなくても充分危ない人だと思いますよ」 「行動に現れないだけ安全だと思う」 「ということは、その人は『他人の記憶』を持っていて、なおかつそれは『自分の記憶』ではないということをはっきりと意識してるわけですよね。その事をどうやって自分に納得させているのでしょう?」 「そこが難しいんだけど、多分『自分と言うのは一人じゃない』そして『世界は一つじゃない』と思ってるのではないかな」 「多重人格ってやつでしょうか」 「もっと性質が悪いような気がする。他人もいつのまにか自分だと思うんだから」 「この人が事件の目撃者になって裁判で証言するとしたら大変ですね」 「あ、それはエピソードとして面白いかもしれない」 - - - - - * - - - - - 「只野先生、立花さんがさっきからなんかぶつぶつ言ってますよ」 「あ、あれはね立花君と大島先生が会話してるの。大丈夫、すぐ帰って来るから」 「大島先生って、あの大島先生ですか?」 「そう、最近取り込んだみたい。気に入ったんだろうね。大島先生を取り込んでから会話の幅が広がったよ。そのうち河原さんも取り込まれるかもしれないよ」 「私がですか。それよりも取り込むってどう言う事ですか?全然、意味解らないんですけど」 - - - - - * - - - - - 「すごいな。立花君は観測者まで取り込んでしまったぞ」 「まったくだ。しかも複雑な構造で同時に何人もの人間を演じてる」 「今だって、『立花君自身のことをフィクションとして分析する大島先生』と『聞き手としての立花君』、そして『その二人を演じる立花君』がいて、更に『それを別室で観測する只野先生』と『新人助手の河原さん』、が同時に演じられてる」 「そう言ってる私達の存在だって怪しいものだな」
今日もヤスを誘って丘に登る。水筒にコーヒーを入れて、姉さんが作ってくれたサンドイッチを持って。30分かけてゆっくりと登る。馬鹿話しながら、女の子の話をしながら。
丘に登ってもすることがない。いつもと変わらない話をして、サンドイッチを食べて、キャッチボールをして、昼寝して、日焼けして、やっぱり馬鹿話をして。丘の上の馬鹿が無駄な時間を過ごす。魔物を待ちながら。 夕日がまぶしくて目を覚ました。また寝てたようだ。あたりには誰も居ない。ヤスは帰ったのか、それとも魔物に喰われたのか。いや、どちらでもない。木の上で寝ていたようだ。 「来ないな、今日も」「そろそろだって言ってたけどな」「案外どうってこと事ないもんだな」「来たら来たで逃げ出すんだろうけどな」「絶対捕まるのにな」 また同じ話だ。 「生贄てのはもっとおどろおどろしいもんだと思ってたけどそうでもないんだな」「いや、ここだけじゃないの?こんな呑気に待つ生贄なんて」 これも同じ話。 そろそろ暗くなってきた。今日あたり来ると思ったんだけどまだみたいだ、帰るか。そう言ってヤスのほうを見るとヤスの後ろに魔物が立っていた。振り返る間もなくヤスは一口で喰われた。自分が喰われたことも解んなかっただろうな。などと呑気なことを考えていたら、逃げるのを忘れてた。腰が抜けて立てなかった。 そのままじゃ食べにくいのか、ものすごい力で掴まれ持ち上げられた。体中が痛い。もう少し丁寧に扱って欲しいところだけど、所詮生贄なんで文句は言えない。牙にヤスのシャツが引っかかっているのが見えた。あんまり良い終わり方じゃなかったけど、なかなか楽しい夏休みだったよ。 俺、旨いのかなあ。
「まだ信じてないでしょ?」 当たり前だ、最後まで信じるつもりはない。「解ってくれるまで何度でも繰り返して言うからね。とにかく疑ったら駄目なの。私だって自分でもものすごくおかしな事を言ってるって解ってるよ。その上で無条件で信じて欲しいって言ってるの」
「だから信じてるって。どうして疑ってると思うんだ?」 僕には同じ嘘をつくことしかできない。マキは怒っている。「あのねえ、君は私に何回嘘をついたか忘れたの?私だって馬鹿じゃないんだから、少しは学ぶよ。そんなことは寝てたって解るよ」 馬鹿じゃないどころか多分半径1000km以内の誰よりも出来の良い頭を持っているはずだ。それだけにどうしてこんなことを言い出したのか見当がつかない。 「お願い。悲壮な覚悟なんかいらないから、とにかく二人とも絶対に死なないって無条件で信じて。バンジージャンプなんかより遥かに安全だと保障するから」 マキの表情は普段とまったく変わらない。目つきが行っちゃってた方が、僕もよっぽど気が楽なのだが。 「これがさ、私と一緒に死んでって言われたのなら、恐怖に震えながらも言うことを聞いたかもしれないよ。でも、絶対飛べる疑うなって言われて、はいそうですかとは行かないよ。せめて悲壮な覚悟くらいはさせて欲しいな」 「要は命までは投げ出すけど、気持ちや考え方までは投げ出せないということだね」 そう言うことだ。 「悪いけどそれも頂戴。命だけなんてケチな事言わないで、今までの経験も記憶も嗜好も全部私に差し出して」 命を預けると言ってるのにケチと言われたのは僕が初めてかもしれない。よし、腹は括った。まず自分を騙そう、そうすればマキも騙せるだろう。「そう言われてやっと解ったよ。どうやったら信じることができるか解らなかったんだ。今の言葉でそれがようやく解った。もう大丈夫だ」 マキの表情が少し緩む「やっと信じてもらえたみたいだね」 旨く騙せたのか結局は僕が騙されたのか解らない。そんなことはどうでも良いことに思えてきた。 「じゃあ、行こうか」 50メートル下に飛び込むために、もう一度二人でフェンスを乗り越えた。大丈夫飛べる。お、いつのまにか自分も完全に騙せてるぞ。「もったいぶるのは嫌だから、カウントなしでせーので行こう」 マキはそう言いながら笑った。決断して良かった。 「せーの」 二人揃って飛び降りる。落下速度は思っていたより速くない、いや落ちていない。どうやら飛んでいるようだ。そうか、飛べるんだ。マキの言うことは正しかった、半分だけだけど。僕はもう自由に空を飛べる。凄く良い気持ちだ、風が心地よい、太陽も暖かい、僕だけの空はどこまでも青い。そして地面には真っ赤なトマトがひとつ。
南太平洋の小さな島で世界一高い建造物を発見した。先端が見えないので正確な高さは解らないが、キロ単位の高さはありそうだ。ただ、その建造物は極端に細い形状をしていて縦横がそれぞれ2メートル程しかない。そのため数キロ離れると肉眼では見えなくなってしまう。今まで発見されていなかったのはそのためだろう。
この建造物の高さを知るにはヘリで上空に昇ってみるくらいしかできないだろうと思ったのだが、幸いにも表面の金属が磁石に吸着することが解ったので、CCDカメラと無線装置を取り付けた簡単なロボットを組んで上の様子を見ることにした。ロボットの移動距離で高さも解るだろう。 目視で予想したとおり、ロボットが1キロ以上上昇しても映像は途切れることが無かった。最初は気付かなかったのだが、これだけの距離を登っても送られてくる映像がほとんどぶれることは無かった。とてつもない剛性を持っているか、揺れを打ち消すよような制御が成されているのだろう。 そろそろ1.5キロを超えようとしている。登るだけならまだ充分な電力が残っているが貴重な機材を無駄にするわけには行かないので戻りの分を残しておく必要がある。もっと先を見たかったが、この辺でロボットを引き返させることにした。下降の最中、画面左側に壁面とは微妙に異なるものが一定間隔で映っている事に気が付いた。どうやら窓のようだ。昇っているときには見逃していたのだろう、着色され質感も壁と似せてはいるが確かに直径30センチほどの丸い窓のようだ。バッテリーの残量が気になるが一度下降を止めて窓のあたりでカメラの角度を変えて窓の中をじっくりと観察してみた。 窓から馬のような生き物がこちらを見ている。馬はロボットに気付くと窓から身を隠した。と同時に窓は壁と同化して中が見えなくなってしまった。窓の大きさと比較すると馬の高さはせいぜい10センチ以下といったところだろうか。馬にしては小さすぎるが、でも確かに馬のような姿をしていた。この不思議な生き物をもう少し観察したかったが、いよいよバッテリーが危うくなってきたので再び下降することにした。下降途中も目を凝らして画面を見ていたが、全ての窓が壁と同化したらしく、それ以降窓を発見することはできなかった。 とりあえず今考えられる仮説は次の2つだ。ひとつは「この針のような塔には小さな馬が住んでいる」、もうひとつは「私の頭がおかしくなった」。どちらも喜ばしい結論ではないと思うが。
道に迷ってしまった。山あいの温泉宿に来ていたのだが、ふらふらと散歩をしているうちに宿を見失い、いつの間にか森に入り込んでしまったようだ。そうこうしているうちに、辺りは暗くなろうとしている。さてどちらに向かおうと決めかねていると背後からいきなり「どうしたの?」と声をかけられた。「うわぁあああ」 道に迷い不安だったことに加えて、何の気配もなく唐突に声をかけたれたため私は取り乱し情けない声をあげてしまった。落ち着いてよく見てみると小学生くらいの子供が二人けたけたと笑っている。私のうろたえ方がよっぽどおかしかったのだろう。子供たちは私をじろじろと見つめてから「ねえ、人間だよね?」 と奇妙な質問をしてきた。ここら辺の子供たちの間ではやっているの質問なのだろうか?「ん?そうだよ。人間に見えない?」 私は子供と会話する事が苦手なので冗談で返してみた。「うわ、やっぱり」「言ったとおりだろ」「初めて見た」「そうだと思ったんだ」 何か引っ掛け問題の類いだろうと思っていたら予想外の反応を見せてくれた。仕方が無いのでもう少し付き合うことにしよう。「そんなこと言ったって君たちだって人間に見えるけど」 すると彼らは嬉しそうに笑い出した。「うわあ、じいちゃんの言ってたとおりだ」「人間って必ずそう言い返すんだね」 妙に盛り上がっている。そんなことより宿への道を早く教えてくれないだろうか。「ねえ、人間。じいちゃんのところに行けば帰り道が解るよ」「そうだよ人間。じいちゃんは何でも知ってるんだよ」「すぐ近くだからおいでよ。人間」「こっちだよ。人間」 こんな風に人間と呼ばれたのは初めてかもしれない。とりあえず大人の居る場所には連れて行ってもらえそうなので、私は後をついて行くことにした。
子供たちに連れられて森の奥に入って行くと、10分ほどで小さな小屋にたどり着いた。「じいちゃん、人間を連れてきたよ」「困っているみたいだから助けてあげてよ」子供たちは口々に勝手なことを言っている。「どれどれ、人間とは珍しいのう」そう言いながらやはりどう見ても人間としか思えない老人が奥から出てきた。老人は私の姿を見るなり、すまなそうな顔をして「申し訳ございませんのう。あやつらはまだ何も解っとりゃせんのですわ」 と謝った。「いいえ、可愛いじゃないですか」 私が笑うと老人は少し安心したようだった。「あなたは私たちが何者であるか、解っているようですな」「それが全然解らないのです。ただ人間でないことは匂いで解りましたよ」 私がそう答えると老人は愉快そうに笑った「そう言えばそうですな。うっかりしておりました」 幸い老人は宿への戻り道を知っていた。もう少し話をしたかったが、暗くなる前にこの場を後にすることにした。「人間じゃなかったんだね」「ごめんね」 さっきの子供達が見送りにきた。「どうかお気をつけて」 老人は頭をなでてくれた。「どうもありがとう。おかげでご主人様のところに帰れます。じゃあね」私は尻尾を振って答えた。
私、実は人間にとても近いんですけど、ちょっとだけ違う生き物なんです。あ、今笑ったでしょう。冗談だと思ってくれても全然OKですよ。ただ覚えておいてくださいね、あなたの周りに何の苦労をすることもなく簡単に何でもできちゃう人がいたら右手の中指と薬指の間を見てみてください。私と同じようにホクロがあるはずです。
右手の中指と薬指の間にホクロがあるという症状(通称ソニア)は病気ではありません。したがって健康上の心配はまったくありません。 昨年5月に悲運の死を遂げたシンガー ソニア の遺体は生前のインタビューで本人が希望していたとおり右手のみ保存されることとなった。 厚生労働省は、10代から30代後半にまで幅広く伝わる都市伝説が原因とされる、右手の中指と薬指の間にホクロがある人(通称ソニア)に対する差別を問題視し、具体的な対策を講じることを決定した。 緊急提言、ソニアも僕たちと同じ人間だ。 ソニアの右手の処置について、現在右手を保存している東京大学医学部は頭を悩ませている。より厳重に保存すべきであるという意見と、ソニア差別に関する諸悪の根源であるから廃棄すべきだと言う二つの意見が真っ向から対立しているのだ。 文部科学省は急増する「ソニアの子と同じ学級に入れるのはやめて欲しい」という親に対する啓蒙を行うためのガイドラインを設けることを決定した。 だからさ、みんながペンでホクロを書いちゃえばいいんだってーの(笑)。わかったか、くだらない理由を見つけては差別したがる負け犬ども、ジャンジャン。 当医院では30分程度の簡単な手術を行うだけで翌日からソニアの方も人間の社会で普通に暮らすことができます。 ソニア、ソニアってそう言う言い方はソニアの方に失礼だと思わないんですか! 「何度も言いますが、DNAの分析結果として種としての違いは、まったくと言っていいほど見当たらないんですよ」「でも同じ方法で分析してスピッツとマルチーズの間でも違いはほとんど見当たらないってご存知でしたか?」 ソニアと人間の間に産まれた子供の95%以上は人間であることが確認されている。ただし、ソニアの方が圧倒的に少数であることと、自らソニアであることを認める者が少ないため、この数字を鵜呑みにするのは危険である。ただ人間同士からはソニアは産まれず、ソニア同士からは人間は産まれないと言うことはほぼ確実でないかと思われる。 むしろ優れていることを誇るべきではないのか?人間は私たちが怖いんだろう。 人間てどうしてああやってヒステリックなんでしょう?気の毒だから指導してあげたほうが良いんじゃないかな。少し劣っているとは言え私たちの仲間なんだし。 大荒れの結果に終わった先の衆議院議員選挙で当選した議員のうち、いわゆるソニアが総議席数の約57%を占めることが当社の独自調査で明らかになりました。当選した議員のほとんどは自分がソニアであると告げていないことを問題視する意見も非ソニア議員より出されましたが、ソニアでないとも言っていないこと、そもそも公職選挙法にそのような規定が無いこと、仮にソニア全員が結託したとしても有権者数に占める割合がわずかであることを理由に問題視する必要はないと言う意見が多く…。 表に立つことを嫌っていた私たちの存在が明らかになり注目されたのは、一人のお調子者の軽はずみな言動がきっかけでした。皮肉なことに結果として私たちは人間を効率良く使用することができるようになり、人間も無駄な自治から解放され私たちの下でより正しい日々を送ることができるようになったのです。
しばらくお休みを頂くことに致します。休止の理由は「アイディアが思いつかなくなったから」に尽きます。思えば、始めた頃は毎日でもアイディアが浮かんだものでした。ちょっと考えればすぐにでも思いつきました。自分は天才じゃないかと思ったくらいです。「うはは、これは良い、最高だ。俺って凄い、足りないのは表現力だけだ。そんなのそのうち嫌でも身に付く。そうなりゃ怖いものなしだ」と思ったものでした。
それがどうでしょう、もう大丈夫だと一息ついたらまったく何もアイディアが思い浮かばなくなってしまいました。毎日あれこれと考えをひねり回した挙句、週に1つ発表するのが精々です。これが何年も続けた上でのことなら解りますが、私の場合は始めてから半年も経っていないのです。お前のアイディアはほんの数ヶ月で在庫切れか?ブーム絶頂時のたまごっちか?と自分を叱責したい気持ちで一杯です。古今東西あらゆる敗者が何度も口にしてきた台詞を私も言いましょう。 「こんなはずではなかった」 そうです。こんなはずでは無かったのです。私は思いつくアイディアを次々と形にして多くの人に見て頂くつもりで居たのです。それほど大それた願望であるとは思いません。どちらかと言えばささやかな希望と言っても良いでしょう。しかしながら現実は散々たるものでした。 とは言えここで投げ出す訳には行きません。元のペースを取り戻すことは無理かもしれませんが、定期的な発表ができるよう、ここで充電期間を頂くことに致します。再開の時期は未定ですが、皆様に忘れられないうちに何とか再開できるようにしたいと考えております。我儘なお願いとは存じますがどうかご容赦の程お願い申し上げます。 - - - - - * - - - - - …以上が、広域無差別連続殺人事件の犯人通称 "キルオール"と思われる人物から警視庁に宛てられた手紙の全文であります。
僕は生まれながらの難病にかかっている。クラスのみんなと違ってあと約3000回しか死ねない。だから体育の時間も見学ばかりだし、修学旅行にも連れて行ってもらえないみたいだ。クラスのみんなは50万回以上残っている命を贅沢に使っていろんな無茶をしている。とても楽しそうだ。理科の実験のときはそれぞれが薬品を飲んだり塗ったりして、人体にどんな影響があるのか身をもって学んでいるし、家庭科の時間は校内に生えている植物をいろいろと食べて味の違いを楽しんでいる。でも僕はみんなが安全を確認したものしか試すことができない。
昨日、僕のクラスの木村君が本当に死んだ。木村君は僕より重い病気にかかっていたらしい。木村君の両親はそのことを知っていたのだけど、誰よりも冒険好きな木村君のことを思って普通に育てたのだと言っている。木村君も何となく気付いていたのだろう、人一倍派手に何度も死んでいた。僕のように気をつけながら暮らしていれば、あと5年は長生きできたかもしれない。でも木村君はそうはしなかった。正確に数えたわけじゃないけど1000回くらいの短い命だったようだ。安心して死ねないことの怖さを木村君はどうやって克服したのだろう。 他の人より慎重に暮らしているとは言えそれでも年に何度かは死んでしまう。どんなに頑張っても一度も死なないで暮らすことなどできないのだ。僕にできることと言えば、それが人より少なくなるように気をつけることくらいだ。ある日病院の先生が大昔の人の暮らしについて教えてくれた。先生が言うには大昔人間は犬や猫のように1度死んでしまうと二度と生き返ることができなかったらしい。多分僕を励ますために話を大げさにしてるんだと思うけど、僕は黙って聞いていた。先生は大昔の人よりましだと言いたかったんだろうか、それとも大昔の人のように一度だけの命だと思って慎重に暮らせと言いたかったんだろうか。 中学を卒業するころ僕の命はあと1000回も残っていなかった。ある日、先生が新しい治療方法を試してみないかと薦めてくれた。海外ではこの治療法で僕と同じ病気にかかっている子が命を十倍に増やすことに成功しているという。僕はそんなうまい話があるはず無いと疑っていたのだけど、両親はそんなのやって見なければ解らないだろうと言ってその治療を受けることに乗り気だ。先生も両親もまだ10万回は楽に命が残っている。何度も死ねる人はこれだから困る。 結局僕はその治療を受けなかった。先生も両親も僕がなぜ受けたがらないのか最後まで解ってくれなかった。実は僕も良く解っていないのだから仕方がないか。今、僕は17歳だけど多分あと10回くらいしか命は残っていない。木村君のように豪快に生きることも、昔の人のように細心の注意を払って生きることもできない中途半端な性格が悔やまれるけど仕方がないか。たった1万回くらいの少ない命をちびちびと使ってきた17年間だったけどそれなりに楽しかったと思う。
「あれ?立花じゃん。どしたのこんなとこで」
「あ、佐藤さん。お久しぶりです。どうしたんですか?こんなところで」 「2年ぶりだっけ?いや3年だったかな」 「いや、シアトルのあんとき以来だから5年は経ってますよ」 「5年かあ、元気だった?」 「ええ、おかげ様でなんとか」 「なんだよ、おかげ様って。そういう挨拶もできるようになったんだ」 「そう言われるとちょっと照れますけど、一応それなりに年とってますので」 「俺も人の事は言えないけど、年とったよなあ」 「佐藤さんあんまり変わってませんよ」 「あれ、自分がちょっと落ち着いたもんだからってそんなこと言うんだ」 「いや、そうじゃなくて、相変わらずなんて言うかエネルギッシュで」 「相変わらず、良く解らない褒め方だな。で今何やってるの?」 「まあ、何て言うか前と同じで探し物を…。佐藤さんも同じですよね?」 「訊くだけ野暮か」 「これで違ったら大笑いですけどね」 「『たまたま旅行で来たんです』て答えても信じないって」 「『道に迷っちゃって』とか」 「あはははは、何だよ道って」 「しまった、そう言えばよかったな」 「ところでさ、立花、あんまり期待しないで訊くけどさ」 「水ならありませんよ」 「あ、やっぱり」 「僕が欲しいくらいです」 「あ、そうなんだ。大丈夫?」 「ええ、なんとか。佐藤さんは?」 「ああ、なんとか。何がなんとかだか解んないけど」 「何だかんだ言ってなんとかなるもんですよね」 「まあな。じゃ、またどっかで」 「ええ、今度はもう少し涼しいところで」 「そうだな、砂のないところで」 「できれば、ラクダ抜きで」 「あははは、ラクダ抜きで」
資産家の老人が自宅で殺害された。
老人は人気シリーズを数多くもつミステリ作家の大御所だった。 ミステリ作家に相応しくといっては不謹慎だが、老人は鑑識課員が赤面するくらいに非の打ち所がない密室で死んでいた。 殺害現場には、原稿が残されていた。 大方の予想通り、捜査員が赤面するくらい殺害状況にそっくりな長編ミステリだった。 そしてこれもまた予想通り、密室のトリックと犯人が書かれた部分は犯人によって持ち去られていた。 捜査に行き詰った蟹丸警部は家に帰り息子に事件の事を話した。 (推理作家だか何だか知らないけど、事件の捜査過程を一般人に話して良いのかという疑問は忘れて欲しい) 「解りました、父さん。私にその遺作を読ませてください」 「そんなことで犯人が解るのか?」 「ええ、多分大丈夫です」 翌日、蟹丸警部の息子は警察に保管されていた遺作をじっくりと読んだ。 「それで犯人はわかったのか?」 「もちろんです。犯人は担当の編集者です」 「それはないだろう。彼女には完璧なアリバイがある」 「でも彼女が犯人です」 蟹丸警部は根拠を求めた。息子は多くを語らなかった。 「私が遺作を読んだことを告げてください、そして私が『すべて解った』と言ってたと伝えてください」 脅しならお手の物だと蟹丸警部は息子の言うとおりにした。 息子の担当だったこともある編集者は諦めて密室とアリバイのトリックを洗いざらい白状した。 「そろそろ種明かしをしてくれても良いだろう?」蟹丸警部は息子に尋ねた。 「お前が、あの遺作をみてトリックを見破ったことは解るが、作品に書かれていた犯人と編集者との間に共通性は無かったじゃないか」 「まあ良いじゃないですか。事件は解決したのですから」 息子は、その根拠を語ろうとはしなかった。 もちろん息子は、最初から遺作を読むことを目的としていた。このあと確実に出るであろうと思われる大御所の追悼特集やあわよくば長編の欠落部分を自分が書いて、名前を売りたかったのだ。その為に、最も邪魔になりそうな編集者を少しでも仕事から遠ざけるために犯人だと断定したのだった。 バスストップ
次のバスまであと74分、これだから田舎は嫌なんだ。誰もいない待合室で俺は論理哲学論考を読んで時間をつぶすことにした。論理哲学論考は田舎でバスを待つのに最も相応しい本だ。ウィトゲンシュタイン自らがそう言っていた(もちろん嘘だ)。
しばらくすると誰かが入ってきた。何か独り言を言っている。声からすると婆さんのようだ。 「雨ばかりで嫌になるねえ」 婆さんが話しかけてきた。ヘッドフォンをして本を読んでいる人に話しかけてくるという神経が理解できない。俺は聞こえないふりをして本を読み続けた。 「本当に、嫌になるよ」 多分独り言のようなものなのだろう。他者と意思の疎通を行うことと、自分の考えを伝えることの境界が曖昧になるのは、老人に限らずそれほど珍しいことではない。俺のように他者とのコミュニケーションを極端に避ける人間は問題があるのかもしれないが、この婆さんみたいな誰とコミュニケーションしてるのか無自覚な人間だって、決して褒められたものではない。 「そうだろ。そこのお兄さん」 畜生、そうまでして俺に同意を求めるのか。俺が「ああ、そうですね」とか「洗濯物が乾かなくて大変ですよ」とか言ったところで、この婆さんに何の得があるというのだ。いや、損得の話じゃないことは解っている。ちょっとしたコミュニケーションが生活の潤滑剤になる場合があるって事は認めよう。ただ、それはお互いがハッピーになるからこそ成立する考えじゃないのか?俺が今本を読んでいることは解るだろう。あんたと会話しようと思ったらウォークマンを止めてヘッドフォンを外さなければいけないことは解るだろう。どれだけ、一方的な満足を追求する気だ?それが人情ってやつか?他人の好意を無条件で貰い放題で何が人情だ、この乞食め。 「でも、まったく雨が降らない年もあったさねえ。あんときは大変だった。あれを思えばこんな雨なんか我慢しないとねえ。そうだろ、お兄さん」 俺は完全に無視を決め込んだ。ばばあ、てめえとなんか話す気はないぞ。俺は必要以上に本にのめり込んでいるポーズを取り、音楽に合わせて軽くリズムを取る。 「こんだけ降ると、あの山に埋めた物がどうなっているか不安になるだろう?」 聞こえない。聞こえない。ていうか、死ねばばあ。 「青いビニールシートが見えてるかもねえ。中のあの娘が不憫だねえ。寒い寒いって泣いてるだろうねえ」 うるせえ、しるか、死んだ女が泣くか馬鹿、ていうかてめえも殺すぞ。 「こんなことなら、もっと深く掘っておいた方がよかったさねえ」 畜生、この婆さんどこまで知ってるんだ?それ以前に、なぜ俺に話しかける?警察関係者とは思えないし、そもそも事実を知っているなら俺に話しかける理由など無いじゃないか。黙って警察に知らせれば、より確実に俺を捕まえられるだろう。 「お兄さん。あんた、まだ気付かないのかい?」 俺はヘッドフォンを外し、ゆっくりと顔を上げた。 「ほら、川野商店の」 思い出した、スコップとビニールシートを買った雑貨屋の婆さんだ。すべてを見られていたに違いない。やばい、この婆さんも始末するか、いや、ここじゃ無謀だ。やばい、やばい、やばい、やばい。 「あんた、お釣りを忘れたよ」 |
|
| (C)2003 T-BYPRO. All rights reserved. |