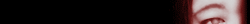
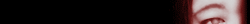 |
 |
GUZZLING All good children go to heaven. |
次のバスまであと74分、これだから田舎は嫌なんだ。誰もいない待合室で俺は論理哲学論考を読んで時間をつぶすことにした。論理哲学論考は田舎でバスを待つのに最も相応しい本だ。ウィトゲンシュタイン自らがそう言っていた(もちろん嘘だ)。
しばらくすると誰かが入ってきた。何か独り言を言っている。声からすると婆さんのようだ。 「雨ばかりで嫌になるねえ」 婆さんが話しかけてきた。ヘッドフォンをして本を読んでいる人に話しかけてくるという神経が理解できない。俺は聞こえないふりをして本を読み続けた。 「本当に、嫌になるよ」 多分独り言のようなものなのだろう。他者と意思の疎通を行うことと、自分の考えを伝えることの境界が曖昧になるのは、老人に限らずそれほど珍しいことではない。俺のように他者とのコミュニケーションを極端に避ける人間は問題があるのかもしれないが、この婆さんみたいな誰とコミュニケーションしてるのか無自覚な人間だって、決して褒められたものではない。 「そうだろ。そこのお兄さん」 畜生、そうまでして俺に同意を求めるのか。俺が「ああ、そうですね」とか「洗濯物が乾かなくて大変ですよ」とか言ったところで、この婆さんに何の得があるというのだ。いや、損得の話じゃないことは解っている。ちょっとしたコミュニケーションが生活の潤滑剤になる場合があるって事は認めよう。ただ、それはお互いがハッピーになるからこそ成立する考えじゃないのか?俺が今本を読んでいることは解るだろう。あんたと会話しようと思ったらウォークマンを止めてヘッドフォンを外さなければいけないことは解るだろう。どれだけ、一方的な満足を追求する気だ?それが人情ってやつか?他人の好意を無条件で貰い放題で何が人情だ、この乞食め。 「でも、まったく雨が降らない年もあったさねえ。あんときは大変だった。あれを思えばこんな雨なんか我慢しないとねえ。そうだろ、お兄さん」 俺は完全に無視を決め込んだ。ばばあ、てめえとなんか話す気はないぞ。俺は必要以上に本にのめり込んでいるポーズを取り、音楽に合わせて軽くリズムを取る。 「こんだけ降ると、あの山に埋めた物がどうなっているか不安になるだろう?」 聞こえない。聞こえない。ていうか、死ねばばあ。 「青いビニールシートが見えてるかもねえ。中のあの娘が不憫だねえ。寒い寒いって泣いてるだろうねえ」 うるせえ、しるか、死んだ女が泣くか馬鹿、ていうかてめえも殺すぞ。 「こんなことなら、もっと深く掘っておいた方がよかったさねえ」 畜生、この婆さんどこまで知ってるんだ?それ以前に、なぜ俺に話しかける?警察関係者とは思えないし、そもそも事実を知っているなら俺に話しかける理由など無いじゃないか。黙って警察に知らせれば、より確実に俺を捕まえられるだろう。 「お兄さん。あんた、まだ気付かないのかい?」 俺はヘッドフォンを外し、ゆっくりと顔を上げた。 「ほら、川野商店の」 思い出した、スコップとビニールシートを買った雑貨屋の婆さんだ。すべてを見られていたに違いない。やばい、この婆さんも始末するか、いや、ここじゃ無謀だ。やばい、やばい、やばい、やばい。 「あんた、お釣りを忘れたよ」
資産家の老人が自宅で殺害された。
老人は人気シリーズを数多くもつミステリ作家の大御所だった。 ミステリ作家に相応しくといっては不謹慎だが、老人は鑑識課員が赤面するくらいに非の打ち所がない密室で死んでいた。 殺害現場には、原稿が残されていた。 大方の予想通り、捜査員が赤面するくらい殺害状況にそっくりな長編ミステリだった。 そしてこれもまた予想通り、密室のトリックと犯人が書かれた部分は犯人によって持ち去られていた。 捜査に行き詰った蟹丸警部は家に帰り息子に事件の事を話した。 (推理作家だか何だか知らないけど、事件の捜査過程を一般人に話して良いのかという疑問は忘れて欲しい) 「解りました、父さん。私にその遺作を読ませてください」 「そんなことで犯人が解るのか?」 「ええ、多分大丈夫です」 翌日、蟹丸警部の息子は警察に保管されていた遺作をじっくりと読んだ。 「それで犯人はわかったのか?」 「もちろんです。犯人は担当の編集者です」 「それはないだろう。彼女には完璧なアリバイがある」 「でも彼女が犯人です」 蟹丸警部は根拠を求めた。息子は多くを語らなかった。 「私が遺作を読んだことを告げてください、そして私が『すべて解った』と言ってたと伝えてください」 脅しならお手の物だと蟹丸警部は息子の言うとおりにした。 息子の担当だったこともある編集者は諦めて密室とアリバイのトリックを洗いざらい白状した。 「そろそろ種明かしをしてくれても良いだろう?」蟹丸警部は息子に尋ねた。 「お前が、あの遺作をみてトリックを見破ったことは解るが、作品に書かれていた犯人と編集者との間に共通性は無かったじゃないか」 「まあ良いじゃないですか。事件は解決したのですから」 息子は、その根拠を語ろうとはしなかった。 もちろん息子は、最初から遺作を読むことを目的としていた。このあと確実に出るであろうと思われる大御所の追悼特集やあわよくば長編の欠落部分を自分が書いて、名前を売りたかったのだ。その為に、最も邪魔になりそうな編集者を少しでも仕事から遠ざけるために犯人だと断定したのだった。
「あれ?立花じゃん。どしたのこんなとこで」
「あ、佐藤さん。お久しぶりです。どうしたんですか?こんなところで」 「2年ぶりだっけ?いや3年だったかな」 「いや、シアトルのあんとき以来だから5年は経ってますよ」 「5年かあ、元気だった?」 「ええ、おかげ様でなんとか」 「なんだよ、おかげ様って。そういう挨拶もできるようになったんだ」 「そう言われるとちょっと照れますけど、一応それなりに年とってますので」 「俺も人の事は言えないけど、年とったよなあ」 「佐藤さんあんまり変わってませんよ」 「あれ、自分がちょっと落ち着いたもんだからってそんなこと言うんだ」 「いや、そうじゃなくて、相変わらずなんて言うかエネルギッシュで」 「相変わらず、良く解らない褒め方だな。で今何やってるの?」 「まあ、何て言うか前と同じで探し物を…。佐藤さんも同じですよね?」 「訊くだけ野暮か」 「これで違ったら大笑いですけどね」 「『たまたま旅行で来たんです』て答えても信じないって」 「『道に迷っちゃって』とか」 「あはははは、何だよ道って」 「しまった、そう言えばよかったな」 「ところでさ、立花、あんまり期待しないで訊くけどさ」 「水ならありませんよ」 「あ、やっぱり」 「僕が欲しいくらいです」 「あ、そうなんだ。大丈夫?」 「ええ、なんとか。佐藤さんは?」 「ああ、なんとか。何がなんとかだか解んないけど」 「何だかんだ言ってなんとかなるもんですよね」 「まあな。じゃ、またどっかで」 「ええ、今度はもう少し涼しいところで」 「そうだな、砂のないところで」 「できれば、ラクダ抜きで」 「あははは、ラクダ抜きで」
僕は生まれながらの難病にかかっている。クラスのみんなと違ってあと約3000回しか死ねない。だから体育の時間も見学ばかりだし、修学旅行にも連れて行ってもらえないみたいだ。クラスのみんなは50万回以上残っている命を贅沢に使っていろんな無茶をしている。とても楽しそうだ。理科の実験のときはそれぞれが薬品を飲んだり塗ったりして、人体にどんな影響があるのか身をもって学んでいるし、家庭科の時間は校内に生えている植物をいろいろと食べて味の違いを楽しんでいる。でも僕はみんなが安全を確認したものしか試すことができない。
昨日、僕のクラスの木村君が本当に死んだ。木村君は僕より重い病気にかかっていたらしい。木村君の両親はそのことを知っていたのだけど、誰よりも冒険好きな木村君のことを思って普通に育てたのだと言っている。木村君も何となく気付いていたのだろう、人一倍派手に何度も死んでいた。僕のように気をつけながら暮らしていれば、あと5年は長生きできたかもしれない。でも木村君はそうはしなかった。正確に数えたわけじゃないけど1000回くらいの短い命だったようだ。安心して死ねないことの怖さを木村君はどうやって克服したのだろう。 他の人より慎重に暮らしているとは言えそれでも年に何度かは死んでしまう。どんなに頑張っても一度も死なないで暮らすことなどできないのだ。僕にできることと言えば、それが人より少なくなるように気をつけることくらいだ。ある日病院の先生が大昔の人の暮らしについて教えてくれた。先生が言うには大昔人間は犬や猫のように1度死んでしまうと二度と生き返ることができなかったらしい。多分僕を励ますために話を大げさにしてるんだと思うけど、僕は黙って聞いていた。先生は大昔の人よりましだと言いたかったんだろうか、それとも大昔の人のように一度だけの命だと思って慎重に暮らせと言いたかったんだろうか。 中学を卒業するころ僕の命はあと1000回も残っていなかった。ある日、先生が新しい治療方法を試してみないかと薦めてくれた。海外ではこの治療法で僕と同じ病気にかかっている子が命を十倍に増やすことに成功しているという。僕はそんなうまい話があるはず無いと疑っていたのだけど、両親はそんなのやって見なければ解らないだろうと言ってその治療を受けることに乗り気だ。先生も両親もまだ10万回は楽に命が残っている。何度も死ねる人はこれだから困る。 結局僕はその治療を受けなかった。先生も両親も僕がなぜ受けたがらないのか最後まで解ってくれなかった。実は僕も良く解っていないのだから仕方がないか。今、僕は17歳だけど多分あと10回くらいしか命は残っていない。木村君のように豪快に生きることも、昔の人のように細心の注意を払って生きることもできない中途半端な性格が悔やまれるけど仕方がないか。たった1万回くらいの少ない命をちびちびと使ってきた17年間だったけどそれなりに楽しかったと思う。 しばらくお休み致します
しばらくお休みを頂くことに致します。休止の理由は「アイディアが思いつかなくなったから」に尽きます。思えば、始めた頃は毎日でもアイディアが浮かんだものでした。ちょっと考えればすぐにでも思いつきました。自分は天才じゃないかと思ったくらいです。「うはは、これは良い、最高だ。俺って凄い、足りないのは表現力だけだ。そんなのそのうち嫌でも身に付く。そうなりゃ怖いものなしだ」と思ったものでした。
それがどうでしょう、もう大丈夫だと一息ついたらまったく何もアイディアが思い浮かばなくなってしまいました。毎日あれこれと考えをひねり回した挙句、週に1つ発表するのが精々です。これが何年も続けた上でのことなら解りますが、私の場合は始めてから半年も経っていないのです。お前のアイディアはほんの数ヶ月で在庫切れか?ブーム絶頂時のたまごっちか?と自分を叱責したい気持ちで一杯です。古今東西あらゆる敗者が何度も口にしてきた台詞を私も言いましょう。 「こんなはずではなかった」 そうです。こんなはずでは無かったのです。私は思いつくアイディアを次々と形にして多くの人に見て頂くつもりで居たのです。それほど大それた願望であるとは思いません。どちらかと言えばささやかな希望と言っても良いでしょう。しかしながら現実は散々たるものでした。 とは言えここで投げ出す訳には行きません。元のペースを取り戻すことは無理かもしれませんが、定期的な発表ができるよう、ここで充電期間を頂くことに致します。再開の時期は未定ですが、皆様に忘れられないうちに何とか再開できるようにしたいと考えております。我儘なお願いとは存じますがどうかご容赦の程お願い申し上げます。 - - - - - * - - - - - …以上が、広域無差別連続殺人事件の犯人通称 "キルオール"と思われる人物から警視庁に宛てられた手紙の全文であります。 |
|
| (C)2003 T-BYPRO. All rights reserved. |