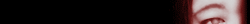
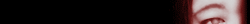 |
 |
GUZZLING All good children go to heaven. |
「四人がかりとは、ずいぶんと私の力を高く評価してくれましたね」
「あんたにゃ、これでも少ないくらいだ」 少なすぎだ馬鹿、と思ったが黙ってることにした。「私も怪我をしたくないので何とか話し合いで解決させてもらえませんか?」 「珍しいな。だが俺の腹の虫は話し合いなんかじゃ収まりそうもないんだ。それに怪我で済むと思ってるってのも気に食わねえな」 お前ら相手に怪我なんかするかタコ、と思ったがやっぱり黙ってることにした。「そう言わずに、私だって問題は起こしたくないんですよ…」 そろそろかかってくる頃だな。可哀想だけどちょっとだけ相手をしてあげるかと思ったとき背後から子供の大声が聞こえてきた。 「お姉ちゃん!お姉ちゃん!あそこ、弱そうなお兄ちゃんがバカな顔した四人組にからまれてるよ。ねえいいでしょ、こんなときはやっちゃっても。いいことだから、やっつけてもいいんだよね」 振り返ると小学校低学年と思われる男の子が、早く遊びたくてたまらないって顔で喚いていた。その後ろには妙に落ち着いた女の子が立っている。こちらは小学校の高学年か中学生といったところだろう。 「ケンちゃん。そのお兄ちゃんは弱そうだけど、そいつらが相手なら十人くらいまでは全然大丈夫なんだから邪魔しないの」 まあ的確な見積だ。もっとも、この子だったら何人まで相手にできるか私には全然見積れないので大きなことは言えないけど。 「えーずるいそんなの。このお兄ちゃんめんどくさいからやだって言ってるよ。だから僕が手伝ってあげてもいいでしょ」 当たってるけど嘘はいけないぞケンちゃん。女の子はケンちゃんを無視して、私に謝った。 「すいません。甘やかされて育ったので、わがままばかり言って」 身近なところに子供が居ないので比べようがないけど、子供はたいていこんなもんだろう。それよりも、この女の子が妙に世慣れてて大人びた話し方をする事の方が不思議だ。 「いやいや、元気があってなにより。ケンちゃん、じゃあこっちの半分あげるからね。その代わり大きな怪我をさせちゃ駄目だよ」 「お兄ちゃんありがとう!全治2ヶ月以内だったら良いよね」 「ケンちゃん!1ヶ月以内にしなさい」 甘やかしてると言ってる割には厳しく躾けてるじゃないか。 「はーい。じゃあ、お兄ちゃん。よーいどんで競争しようね」 私は甘かったようだ。ケンちゃんは私に負けまいと夢中になり言いつけを守ることが出来なかったのだ。お姉さんにこっぴどく怒られたケンちゃんと馬鹿四人組には悪いことした。いや故人に馬鹿は失礼か。
海底に人間一人がなんとか生活できる住居を10個用意しました。この住居は海底地震があったり鮫に襲われてもびくともしない丈夫な建物です。住居と外とをつなぐのは緊急連絡と定期的な生存確認のための専用線だけで外部との連絡はシャットアウトされています。住居は互い距離を置いて設置されますので、他の住居を見ることもできません。また水、食料、空気は充分に用意されています。
ただし、この住居の壁には一つ小さなスイッチが付いています。このスイッチを押すと住居の扉が開き、内部は海水で満たされてしまいます。もちろん中の人は助かりません。スイッチは直径3cmほどのボタン型スイッチでカバーはなく、入居者が簡単に手の届く高さに取り付けられます。 この住居の中で20代から40代の男女10名にそれぞれ2週間生活してもらうという実験を行います。2週間の実験期間を通じて何人の被験者がスイッチを押してしまうでしょう? - - - - - * - - - - - 高額な報酬に釣られて妙な実験に参加してしまった。今日で開始から一週間になるが、あと7日間耐えられる自信がない。ボタンを押してみたくてたまらない。いまここで選択可能な道は3つある。一つはあと7日間ボタンを押さずに耐え切ること、二つめはリタイアすること、最後はボタンを押すことだ。一つめに関してはもう自信がない。どうしてこんなただのプラスティックの赤いボタンがこんなにも押してみたいのだろう。しかも押したら確実に死ぬというのに。いやだからこそ試しに押してみたいのかもしれない。 あと、5日だ。今日中に決めよう、リタイアするかボタンを押すかだ。リタイアするなら、ホットラインで係の人を呼び出してリタイアしますと言うだけで完了だ。とても簡単じゃないか。報酬はもちろん貰えないが、このままだと気が変になりそうだ。とは言えボタンを押すことも魅力的だ。係の人は「押したら1秒以内に扉が開き、次の瞬間確実にぺしゃんこになります」と言っていた。自分には自殺願望など無いと思っていたし今でも無いと思っている。にも関わらずボタンを押せば1秒後に苦しむ間もなく死んでしまうという強力なスリルにどうしようもなく惹かれてしまう。 それにしても死亡者が出るかもしれない実験なんてものが出来るだろうか?それにこの住居だってボタンを押せば確実に使い物にならなくなるわけだ。損失は被験者に払われる報酬の比じゃ無いだろう。実はボタンを押しても何も起きないのではないだろうか?扉は開かないでホットラインに連絡が入ってリタイアとなるのかもしれない。本当に人が死ぬような実験をやってることがばれたらまずいだろうし。 今日決めようと思い続けることで何とか生き延びている。あと3日だ。そういえばここに入るときに誓約書とか書かなかったな。あれば地上に戻ったときに危険な実験をしていたという証拠になったのに。逆に地上に戻れなかった場合も危険な実験をしていたという証拠はないのか、事故だった言えば済むって訳だ。それどころか実験を終えて帰宅したはずだともみ消すことも出来るわけだ。やはりボタンは本物かな。いや、だとしたら馬鹿みたいに費用をかけてこの実験をする理由が解らない。ボタンを押したら解るだろうか…。 この馬鹿げた実験も明日の正午で終わりだ。結局、ボタンを押すことに魅力を感じるとか言いながらもそれほど破滅志向がある訳でもないことが良くわかった。やはり死ぬのは怖い、無事に地上に戻って報酬をいただくとしよう。 実験は終わった。海底に沈められた住居がゆっくりと引き上げられ2週間ぶりに地上に出ることができた。今朝の定期連絡で「引き上げ終わってから外に出るまでの間にボタンを押したらそのまま海中に戻す」と言われた。そんなことするつもりは元から無かったんだけど、いろんな可能性を考えてあるんだなと感心した。 帰り際に高額の報酬と共に記念品を渡された。家に帰って開けてみると例のボタンのレプリカだった。「このボタンは押しても何も起きません、気の済むまで押してください(笑)」とメモが添えられている。馬鹿馬鹿しい何が「気の済むまで」だと、ボタンを押そうとした。…押せない、確実に安全だと解っているのに怖ろしくて押せないのだ。こんなもの捨ててしまおうと思うのだが、誰かが押すかもしれないと思うと捨てることも出来ない、誰も押さなかったとしてもゴミ処理場でボタンが押されてしまう可能性は0ではない。そう思うと怖ろしくて捨てられない。 以来、そのボタンから離れるのが怖くなった。どんなきっかけで押されないとも限らないので、家の中では常に近くに置くようにしている。外出するときはボタンを常に持ち歩いている。家に置いてたら泥棒が押すかも知れないからだ。一生このボタンから離れられそうもない。
「社長、これ絶対行けますって」
「君がそう言って持ってきた話がものになったことが一度でもあるかね?」 「そんな人聞きの悪い。まあ、ひとまず話だけでも聞いてくださいよ」 「どうせ断っても話すんだろう」 「そうこなくっちゃ。今回のご提案は、長期滞在リゾート型テーマパークその名も『ありがちランド』です。どうです?」 「どうですって言われても解らないなあ。とにかく名前はどうにかしなきゃいけないとは思うけど。それでどんなテーマパークなの?」 「それがですね社長、このテーマパークでは、お客様が数日間ある街に滞在していただくわけですけど…」 「ちょっと待って、リゾートと言っておきながら、街で過ごすのかい?」 「そこが、このテーマパークの新しいところなんですよ。お客様はその街の住民として過ごすわけなんです。そしてその街では、マンガやドラマの中でありがちな事が次々と起きるという趣向になってるんですよ」 「ミステリーツアー見たいなものかね?」 「似てなくもないですが、ちょっと違います。ミステリーツアーと違って決められたストーリーはありませんし、お客様はその世界の住民としてしっかりと参加していただくことになります」 「なんだか解ったような解らないような…。それでそのありがちな事というのは?」 「まず、お客様が朝家を出ると隣の家の女の子がトーストをくわえて『遅刻遅刻』といいながら走ってきます」 「ありがちだな」 「そう、そこがポイントなんです。ありがちランドはお客様が『フィクションでおなじみの光景』をいつもご覧いただけるのです」 「そうか、街の住民はスタッフとか役者なのだな」 「そうです。ただ、一人のお客様をあまり大勢のスタッフでお相手するのは限界がありますから、何名かのお客様が同時に滞在することになりますが」 「なるほど、なんとなく解って来たぞ。他にはどんなありがちなイベントがあるのかね?」 「例えばお客様が学校に行けば転校生が来て隣の席に座りますし、その転校生は数年ぶりにこちらに戻ってきた幼なじみだったりします」 「恥ずかしくなるくらいありがちだな」 「会社に出勤したらしたで、屋上でバレーボールをしたり、破天荒な新人が入ってきたり、帰りには屋台で一杯飲んでから帰ったりします」 「学生だったり社会人だったり忙しいな」 「一方さっきの幼なじみは隣の家に引っ越してきます。幼なじみとは二階の部屋が向かい合ってて屋根伝いにやってきて窓から入ってきます」 「それまた古典的な話だ」 「他にも拳銃で撃たれたけど胸ポケットのコインに当たって助かるといったイベントもオプションでお付けすることができます」 「あれはないのかね?雪山で遭難して体を冷やさないように、なんと言うかそのあれだ」 「さすが社長。それいただきですよ。雪山を用意するのは難しいので街中で何か適当な理由をつけることにしましょう」 「いや、私は特に興味はないのだけどお客様が喜ぶかと思ってな」 「そりゃもう解ってますって。他にもですね…」 ありがちランドの話はまだまだ続いている。この男は私と昔から付き合いがあるらしいがどうも記憶が曖昧で思い出せない。私はどうやら社長らしいが何の会社の社長なんだろう?いや、それ以前に私が誰なのかも良く解らなくなってきた。まあどうでも良いことだ。それにしても社長のところに直に胡散臭い話を持ってくるC調の企画屋とそいつに簡単に騙されつつある社長というパターンというのもフィクションの中ではありがちな光景だ。私もこの男も既にありがちランドの住民なのだろう。
ある自動車メーカーのイメージキャラクター発表のニュースを見て驚いた。半年前、僕は大きな鎌を持った小さな子供の絵を描きそれに皆殺しちゃんという名前をつけて自分のホームページのキャラクターにしたのだが、その落書きのようなイラストが勝手に使われているのだ。自動車メーカーのイメージキャラクターとの違いは大鎌が魔法使いのホウキになっている点と名前がエンジェルちゃんになっている点だけだ。他は全く同じ、これは誰が見ても盗作だと認めてくれるだろう。思うに、この自動車メーカーのキャラクターは公募で選ばれたのだろう。そして誰かがまさか選ばれると思わずに、僕のサイトの絵を持っていったに違いない。僕はそう推理した。何か詳しい情報が判るかもしれないと思ってメーカーのサイトを見てみたら、僕の予想に反してキャラクターデザイナーとして有名なイラストレーターの名前が記されていた。出鱈目にも程がある。そのイラストレーターは細かい線で描かれた緻密な絵が特徴の筈だ。僕はその自動車メーカーに抗議のメールを送った。幸い僕は有料のファイルバックアップサービスに入会していて自分のホームページのファイル一式を保存している。そこに保存されているファイルのタイムスタンプを見れば僕の方が先に描いたことは明らかだろう。
自動車メーカーは僕の抗議を黙殺した。エンジェルちゃんは何故か人気者になり、関連グッズが売り出されている。エンジェルちゃんのファンと称する人たちからは「大人気ないパロディーだ」「子供の夢を壊すようなみっともない真似は止めた方が良い」といった抗議のメールが届き始めた。僕が作った皆殺しちゃんなのに酷い言われようだ。多分メーカーはこのまま黙殺を続けるか、下手したらプロバイダーに削除依頼を出すだろう。出るところに出れば勝ち目はあるのかもしれないが、僕はこういうときは泣き寝入りをすることに決めている。僕に入ったかもしれない使用料のことを考えながら悪酔いするのが似合っている。名残惜しいけど皆殺しちゃんもそのうち消してしまおう。 そう思っていたらメーカーとイラストレーターは盗作を認める発表をしてしまった。しかも彼らは「国民的アイドルとなる素材が発案者の手によって過酷な扱いを受けているので発案者の持つ著作権を侵害してでも救い出したかった」という理由を前面に押し出してきた。あまりに馬鹿げている、こんな世間を馬鹿にした理由が通用するわけないだろう。とにかく厄介なことが起きるのは確実だ何か対策をしなければ。 何より最初に野次馬の攻撃を避けなければいけない。会見からまだ1時間と経っていないと言うのにもうメールが30通ほど届いてる。僕はまず、脱会の届けを出してサイトのファイルを削除をしようとした。ところがファイルの削除権限は停止されていて、何度試してもファイルを消すことができない。改めてメールを見てみるとプロバイダーから「お客様のサイトにファイル固定依頼が来ていて特別処置として受理しました」との案内が届いていた。世間はエンジェルちゃんを可愛がるあまり、僕の想像以上に馬鹿になってるのかもしれない。メーカーは法律以外の部分で僕と徹底的に戦うつもりなのだろう。泣き寝入りもさせてもらえないようだ。 知らないうちに僕はメーカーに対して著作権侵害の訴えを出すことにされていた。メーカーは喜んで受けて立ち、そして喜んで敗訴し、敗訴が決まると同時に皆殺しちゃんに関するあらゆる権利を故意に高価な金額で僕から買い取った。その代償として、僕のサイト、バックアップサービス、僕の所有するパソコンから皆殺しちゃんのデータを削除したという宣誓文を書かされた。告訴から判決までマスコミは常にメーカーの味方に立った報道をした。盗作したイラストレーターと自動車メーカーの企画担当はちょっとしたヒーローとしてもてはやされている。あるニュースキャスターは「メーカーは確かに著作権違反という罪を犯しましたが、その罪は充分過ぎるくらい償いました。そればかりか子供達の夢を卑劣でわがままな守銭奴から守ったのです」とまで言った。僕と皆殺しちゃんに味方は一人もいない。 判決から一ヶ月が経過したある日、皆殺しちゃんが現れてイラストレーターとメーカーの企画担当の首を刎ねた。今ちょうどテレビ局に向っている姿が生中継されている。多分あのニュースキャスターの首を刎ねるのだろう。誰も皆殺しちゃんを止めることは出来ない。あはは、止めようとした奴の首が次々と刎ねられている。「遅かったじゃない、皆殺しちゃん」ブラウン管に向って僕がつぶやくと、皆殺しちゃんはカメラのほうをちょっとだけ見て「悪りぃ」と言った。愉快な奴だ。 大橋さん
職場で大きな仕事が終わり、久しぶりに打ち上げの飲み会が開かれた。一次会もそろそろ終わろうとする頃、僕がトイレに行こうとすると大橋さんが後ろから僕を追い越し、ポケットにメモをねじ込んで行った。僕はトイレの個室でどきどきしながらメモを見た。嘘だ 「次、ばっくれて二人で飲みに行こう」 と書いてある。2年先輩の大橋さんは口は悪いけどさっぱりした性格にすっきりとした容姿で密かにファンが多い。僕もその一人だ。その大橋さんが僕を誘ってる?落ち着け何かの間違いじゃないか、どこかに「これを田中に渡せ」って書いて無いか?僕はメモの裏表を何十回も見直した。大丈夫だ、メモにはさっきのお誘いの言葉とショットバーの名前しか書いてない。こんなことがあって良いのだろうか。
打ち上げの一次会が終わり二次会に引っ張られそうになるのを振り切って、僕はいそいそとご指定のショットバーに向った。僕とほとんど同時に大橋さんも到着、ちょっといたずらっぽい目つきに心臓が高鳴る。でも幸せはここまでだった。ショッキングな一言はモスコミュールとジンライムで乾杯した直後に飛び出した。 「ごめん。実は立花君に教えて欲しいことがあって呼んだんだ」 うわ、大橋さんそりゃないですよ、なんか耳の奥がジーンと鳴っている。何も期待してなかった振りをしようか、とも思ったけど、すぐ表情に出てしまうのは目に見えてる。諦めて正直に話すことにした。「ちょっと待ってください。正直すごくショックなんで、まずこれ空けちゃいますね」僕はジンライムに手を伸ばした。「駄目」 僕のジンライムを速攻で脇に追いやられた。厳しい人だ。「悪いけど、やけ酒は話が済んでからにして」 騙して誘い出したという自覚はあるみたいだ。よく考えてみるとひどい目にあってないか僕は?不満を言おうと思ったけど大橋さんはちょっと怖い目で僕の顔を覗き込む。白旗だ。「解りました。僕が知ってることで良ければ何でも話します」 「ありがとう。じゃあ遠慮なく聞くよ。立花君て田中君と仲良いよね」 結局そういうオチでしたか。田中の情報を聞き出すために僕を利用したってことですね。がっかりする僕とは対照的に大橋さんは冷静を装いつつも照れたような顔をしている。羨ましさと悔しさで頭がおかしくなりそうだ。「ええ、そりゃもう」 せめてもの抵抗として僕と田中の間に濃厚な関係があるような雰囲気を匂わせてみた。「一応確認しておくけど、そっち方面じゃないよね?」 大橋さんの目が険しい、抵抗した甲斐があったというものだ。僕はもう少し抵抗したほうが良いのかちょっと考えてみた。「言っとくけど、こっちは真剣なんだからね。茶化したり騙そうとしたら殴るよ」 とても僕を騙して誘い出した人の言葉とは思えない。「解りました。ちゃんと答えます。そういう関係はありません」 あっても困る。「OK。じゃあ協力して」大橋さんはその後2時間かけて水とジンジャーエールとウーロン茶しか飲ませてもらえない哀れな僕から田中に関するあらゆる情報を聞き出した。 「ありがとう。とても参考になった。そのうちなんかお礼するよ」 「では、早速で悪いんですけど教えてください。誰なんですか?」 「何が?」 大橋さんは何を聞いてるのか解らないって顔をしている。僕がどこまで気付いたかを探っているのかもしれない。 「田中のことを知りたがってるのは大橋さんじゃありませんね。いくら大好きな大橋さんでも2時間も話をすれば、いろんな事が見えます。僕を素面にしたのは失敗でしたね」 さりげなく告白したつもりだが声がうわずってしまった。みっともない。 「何のことかわからないけど、いろいろ見えたってのがどんなことか教えて欲しいな」 僕がちょっと押したくらいでは大橋さんのポーカーフェイスは崩れない。告白も無視された。 「まず質問が整理されすぎてました。誰かと協力して質問をリストアップして効率良く聞きだせるよう整理されているかのようです」 「私は興味の幅が広くて、質問も予め綿密に準備をしたのかもしれないよ。現にこうやって立花君を騙して誘い出したことから解るように、とても計画的に物事を進めるタイプだと思わない?」 やはり役者が上か、次のが効かなかったら僕には打つ手はない。 「それにもう一つ、僕の回答の内容にはあまり興味が無さそうでしたね。ひとつの答えから次の質問に発展することもほとんどありませんでした。好きな人のことを聞きだしてるというよりは、調査を楽しんでいるかのような印象です」 さあ、どうだ?大橋さんの表情からはどちらとも読み取ることができない。 「うーん。確かに今言った事は全部当たってるけど、大事なポイントを見落としてるから、65点ってとこかな」 厳しい採点だ。大橋さんは続けた。「どうして田中君に直接聞かなかったんだろうって思わなかった?」 もちろんその答は解っている。大橋さんも僕がわざと言わなかった事に気付いているに違いない。 「もうお分りですね。田中君は大橋がお気に入りの後輩を誘い出す口実に利用されただけだったんですねえ」 大橋さんはそう言って今日始めて笑った。 |
|
| (C)2003 T-BYPRO. All rights reserved. |