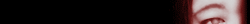
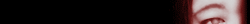 |
 |
GUZZLING All good children go to heaven. |
「いやあ、暑いな。頭が焦げそうだ」
「お疲れ様です。麦茶でいいですか?」 「お、ありがと。田中は昨日から来てたの?」 「ええ、昨日です。立花さんバスで?」 「うんバス。あれだろ?あのお婆さん」 「あ、やっぱり見ましたか。私も昨日見ました」 「悪い人じゃないんだろうけどやっぱり気になるよな」 「上品そうなところがかえって怖いんですよね」 「これで4年連続ですか?」 「いやいや、そんなもんじゃないぞ。去年差し入れ持っ来た木ノ内さん、俺の5代前の、あの人も見てるって言うから最低でも10年前からああやっているらしい」 「うわっ。余計怖くなりました」 「多分何かショックなことがあったんだと思うぞ」 「お年寄りなんで解りにくいのかもしれませんが毎年全然変わってないですよね」 「ああ、木ノ内さんは10年間まったく年取ってないみたいだって言ってた」 「いつも和服をびしっと着こなしてますし」 「高そうな着物だったから、そこそこのお金持ちじゃないのかな」 「いつも横に綺麗な風呂敷包みを置いてますよね」 「うん。そしていつも可愛い赤ちゃんを抱えて…」 「あっ」
うかつだった。子供だと思ってなめてたが、トモちゃんと私ではレベルが違いすぎて相手にならない。
「気付くのが遅すぎます」 私をもっと手ごたえのある奴だと期待していたのだろうか?理不尽にも私の鈍さに対して怒っているようだ。 「私が負けを全面的に認めて命乞いをしたら助けてくれるかな?」 子供相手の交渉としてはあまり良くなかったかもと思いつつ相手の腹を探ってみた。 「交換条件というのはすべて嘘だと習いました。だから聞く気はありません」 実に正しい教えだ。そんな正しいことをこんな凄い子供に教えるのはもう少し待ってほしかった。 「これは交換条件じゃないよ。泣きながら命だけは助けてくださいって情に訴えようと思ってるんだけど、だめかな?」 これは、まったく本当。お望みとあらばこの場で大泣きしても構わない。 「情に流されることは詐欺に会うことと同じだとも教えられています」 誰だか知らないけど、そんな先生がいたら私も少しは違った一生を送ってたかもしれない。 泣くのは次の機会までとっておくことにして、もう少し交渉を続けて見ることにしよう。「私が助かる方法は何かないのかな?」 「あなたのお話は全然面白くありません。私も忙しいのでそろそろ終りにしたいのですが」 交渉の余地はなさそうだ。「あ、それから何か勘違いしてるようですけど、私それほど物騒なことするつもりありませんから。あなたが人並みだったら多分死んだりはしないでしょう」 ありがたい御指摘だが全然気が楽にならない。 トモちゃんは無表情で軽く握った両手を低く構える。右手の人差し指が小さく動いた。と同時に鋭い音が聞こえコートの裾に軽い衝撃を感じた。穴が空いている。 「珍しいな、指弾を使うんだ」必死に動揺を隠しながら私は続けた「でもこの状況にふさわしい方法じゃないと思うけどな」 他に攻撃方法を知らないという可能性を探ってみる。あり得ないとは思うが。 「…」 トモちゃんは声を出さずにため息をついた。「あなたがそこまで未熟な人だとは知りませんでした。正直言ってこのまま帰りたい気分です」 「そうしていただけると、二人ともハッピーに丸く収まるんだけど。どう?」 トモちゃんはそれには答えず「あなたは、これが指弾だと思ったのですか?」 と言って右手を少し上げた。また空気を切り裂く音。帽子が前に飛ぶ。…前に? 「普通はコートに当たった段階でどちらから飛んできたか解るはずですし、方向がわかればこれが何であるかなど簡単に解るはずなのですが…。まだ解らないのなら次は胴に当てますよ」 トモちゃんは本気で怒っているようだ。何故、私が怒られなければいけないんだ? 「答えが無いのは解らないからだと判断しますが」 もう答えは解った。帽子が飛ぶまでまったく思いつきもしなかったのは恥ずかしい限りだが、そんなマイナーな物を知らなかったからって怒ることは無いと思うのだが。 トモちゃんの左手が動きかけた。「解った、答える。答えますって。だから手を下げて。君が使ったのは虫弾だね」 話には聞いていたけど虫弾を使う人が実際に居るとは知らなかった。通常は、虫弾が劇的に好むフェロモンを相手に塗布するか、虫弾を仕込んだ場所からの経路上に相手が来るよう虫弾フェロモンを置くという方法が一般的だが、外した場合に次の攻撃ができないというデメリットがあるため、トモちゃんの場合は特定種にだけ作用するフェロモン何種類か用意して何度も攻撃できるようにしているようだ。この方法の場合、どこにどのフェロモンに反応する虫弾を仕込んで置いたかを覚えていないと使えないし、自分に当たらないようにするには相当の訓練が必要だ。 「そもそも、私がこれを覚えさせられたのはあなたに原因があるのですよ」 「何でも他人のせいにするのは良くないよ。私のどこに原因があるの?」 「あなたが調子に乗って私の弟にあんなことをさせたせいで、私は家に帰って、監督不行き届きだと怒られました。そして罰としてこんな使い道の無いおもちゃを覚えることになったのです」 罰ゲームで覚えるような技じゃないと思うのだが。それよりあれから3ヶ月しか経ってないというのに虫弾をマスターしてることに驚いた。 「その件については君にもケンちゃんにも何度も謝ってるじゃないか。だいたいトモちゃんだってあんとき見てるだけで止めなかったじゃん」 「確かにあなたの実力を見誤ったのはミスでした。危なくなったら止めることができる人だと思ったものですから。こんなに未熟な人だと知ってたら最初から止めさせてました」 「そんなに未熟かな?」 「ええ。最初の評価は50点でしたが、今は15点くらいだと見ています」 とても恐ろしくて採点基準は訊けない。 「それはかなり大きなミスだね。だったら、少しは折れてくれてもいいんじゃない?そんな危ないもの持ち出さないでさ」 未熟でも何でも良い、ここは何とか口先で逃げ切らなければ。虫弾なんかを当てられることを思えば何だってできる。 「では、こうしましょう。神経毒の作用を抑える内服薬をここに置きます。弾は腿に当てますから這って来ればなんとかなるでしょう」 そう言ってトモちゃんはつま先で地面を掘り、小瓶を置いて上から土をかけた。微妙に意地悪だ。瓶を埋める動作に少し隙が見えた。私はやけくそでトモちゃんに飛びつき押さえ込んだ。「せめてもの抵抗をさせてもらおう。さあどうする?」 「最低ですね。子供に対する性的嫌がらせですか」 いや、そうじゃなくて。 「その話はまた5年後にでも。それより、このまま虫弾が私の足を貫いたら確実にトモちゃんにも当たるよ」 「一つ間違いを訂正させてください、さっきの15点は誤りでした。あなたはせいぜい5点と言ったところです」 私の評価は3ヶ月で10分の1に大暴落したようだ。「何のプロテクトもなしで、こんなおもちゃを使うと思いますか?」 と言い終わる前に左足の腿に激痛が走った。トモちゃんのジーンズの上で私の左腿を貫いた虫が潰れている。だが痛さにのた打ち回っている暇はない。1分以内にさっきの小瓶を掘り出さないと大変なことになる。 「私を押し倒したときに瓶が割れてないと良いですね」 トモちゃんはつまらなそうにそう言って哀れな5点男を残し去って行った。
「なっちゃんは誰にも渡さん」
「うるさい。勝手なこと言うな。俺だって誰にも渡さないぞ」 「なんだと。なっちゃんは俺のものだ」 「いや俺のものだ」 コーヒースタンドで遅い昼食を取っていたら、奥の席からふた昔前の青春ドラマのような言い争いが聞こえてきた。ただ、ふた昔前と違って言い争っている二人からは体育会系の空気が全く感じられない。いや、最大の違いはこの場になっちゃんらしき女性がいないことかもしれない。 「だいいち、お前は後からやって来たんじゃないか」 「それがどうした。お前は俺が出てくるまでほとんど黙っていたようなものだろう」 「そんなことが理由になるか。黙っていたか積極的に話してたかなんてのは客観的に判断できるものでもないだろう」 「じゃあ、俺が出てこなかったらどうするつもりだったんだ?俺が出てきたから、なっちゃんに執着するようになったくせに」 「推測で勝手なことを言うな」 「事実だからそうむきになっているんだろう」 喧嘩のパターンというのは昔からあまり変わってないようだ。ふた昔前ならここで何か勝負を始めるところだが、この二人はどうするのだろう。 「これ以上争っても埒が明かない。コイントスで決めないか」 「釈然としないが、仕方ないだろう」 「じゃあ、俺が投げるから当ててくれ」 「裏」 「くそ、負けたか」 「約束どおり、なっちゃんは俺のものだ」 「しかたがない。俺は別のハンドル名を使うことにする」 この国は一度滅んだほうが良いと思った。
じゃりじゃりと音を立てて道を歩く。柔らかい貝殻が潰れる感触と中身を踏みつける感触とを同時に味わいながら。この靴もそろそろ駄目だな。ナイキから貝路でも歩きやすい靴が出たらしいがあれは効くのだろうか。道が歩きにくくてやたらと喉が渇く。コイン投入口とボタンに貼り付いた貝を百円玉で払い除けてコーラを買う。ゴトンという音にすら貝が潰れる音が混じる。赤い缶を急いで取り出し青い貝を取り除く。つり銭はあきらめた。飲み口のところだけ丁寧に拭いてからリングプルを開けて慎重に飲む。やっと生き返った。だが、立ち止まっては居られない。すでに5匹ほどズボンにまで登ってきた。慌てて振り払いながら再び歩き始めた。本当は走り出したいところだが、道がぬるぬると滑るのでそれもままならない。自転車で走れた頃が懐かしい。
去年までは10分で帰って来れた道を30分かけてやっと帰宅。じゃりじゃりと音を立ててドアを開け家に入り靴とズボンとコートとメットと鞄についた貝を落としに風呂場へ向う。今日は31匹。すべて落とし終えてから風呂場に殺貝剤を撒き、室内のチェックをするのが日課になっている。子貝が小さな隙間から入ってくると後で苦労するので慎重に探す。貝センサが出たおかげでチェックはかなり楽になった。通気口に3匹、トイレに1匹、殺貝剤で念入りに退治して貝除けを塗っておく。 これでやっと休むことができる。通勤時に体力を使うし、屋内に入るたびに貝を落とさなければいけないのでとにかく疲れる。自分の部屋にいても常に貝の進入に気をつけなければいけないので、なかなか疲労も回復しない。気温が上がってくれると貝も半分以上いなくなるので少しは気が楽になるだろう。予報では明日は久しぶりに晴れそうだと言っていたが窓ガラスにびっしりと貼り付いた貝のせいで外は見えない。 もうつまらない意地を張るのはやめて貝になってしまおう。今月に入ってからそのことばかり考えている。酒をたくさん飲んでぶっ倒れる直前にドアを開けるのが一番楽な方法らしい。明日も雨だったらそうしようか。 陳腐な夢
「立花子さん結婚してください」
僕はやっとの思いでプロポーズした。いや待てこの変な名前の女性は誰だ?そもそも何で僕は知らない人にプロポーズしてるんだ?混乱する僕とはまったく無関係に事態は展開して行く。変わった名前の立花子さんは一瞬驚いたような表情を見せてから、小さく微笑み返事をしようとしたその瞬間 「ハイ、カットぉ」 の声が響く。どうやらドラマか映画の撮影のようだ。僕は役者なのかもしれない。今のが今日最後のシーンだったらしくスタッフはセットを撤収し始めた。それにしても随分と大胆に片付けていくものだ。店の内部から始まってついには建物まで片付けてしまった。こんなに片付けたら明日からの撮影が面倒なんじゃないだろうか?と呑気に構えてたら、建物だけじゃなくて街も国も地球も撤収されてしまった。 「…という恥ずかしい夢を見たんです」 「うーん。かなり陳腐だなあ。唯一オリジナリティがあるとしたら立花子さんという名前くらいかな」 「実は、立花子さんは前原さんにそっくりだったんですよ」 「私?立花君たらもしかして、あららら」 「ええ、実はずっと前原さんのことが…」 「ハイ、カットぉ」 |
|
| (C)2003 T-BYPRO. All rights reserved. |