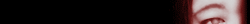
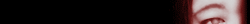 |
 |
GUZZLING All good children go to heaven. |
「あなたは、人間ですか?」
上下がつながった銀色の服に身を包み、不思議な髪型をした男が私に尋ねた。明らかにおかしい奴だ。こいつは何を訊こうとしているのだろう?人間ですかって、そりゃ人間に決まっているだろうが。 いや、待て。私は自分が本当に人間であると証明できるであろうか?まず、外見から考えると少なくても人間に近い生き物であることは確かなようだ。話がややこしくなるので、私が見ている私の外見は正しいものとしよう。私の意識や感覚は夢や幻ではなくリアルに私が体験しているということを疑いだすと際限がない。だいいち、犬を眠らせて頭に電極をつなぎ、人間としての自分の記憶や体験を植えつけて何の意味がある? 話を戻そう。さっき、思わず「人間に近い生き物」と言ってしまったが、その前に生き物でないかもしれないということを疑うべきだった。私が作り物でないとはどうやって証明できるのだろう?一応生命活動はしていて新陳代謝もあるので生物ではあると思うが、それも含めて完璧に再現する事ができるようになったら、自分自身では区別がつかないのではないだろうか。これも疑いだしたら際限がない。ここもとりあえずそんなことは無いと思っておこう。さっきからどうも荒唐無稽な考えばかりが頭に浮かぶ。この男の外見に毒されているのかもしれない。 さて、私が作り物でないとして果たして本当に人間であるのだろうか?極端な話をすれば、別の星のまったく異なる種類の生き物が人間の形をしてるということだって…。ああ、また馬鹿らしい事を考えてしまった。そこまで極端なことを言わなくても、例えばまだ発見されていない未知の生き物である可能性もあるわけだ。生物学的に検証してみたら人間に非常に近いものの別の種類の生き物であるという結論に達してしまったら、私は人間ではないということになるのだ。 いや、待て。生物学的に別の生き物だからと言ってそれがすなわち人間で無いと言っても良いのだろうか?人間として生まれ育って社会の中で暮らしているにもかかわらず、生物学上の特徴だけで安易に人間としての権利を剥奪するような事は極めて危険なのではないだろうか?いやいや、それはまた別の問題か。もし、極めて人間に近い別の生物であることが判明した場合には、その生き物が人間であるかという問いと人間としての権利を有するかという問いは別々に考えるべきだろう。 あれこれ考えては見たが結論は出ない。おかしな格好をしているが、なかなか考えさせられる問いかけをしてくる奴だ。只者ではないのかもしれない。 男は再び私に問いかけた。「あなたは、人間ですか?」 仕方がないので正直に答えることにした。「私は自分の経験から自分が人間であると確信している。少なくても人間と呼ばれる権利は持っているつもりだ。ただ、生物学的に人間であるかを検証したことも無いし、証明する手立てもない」 私の答えに満足したのか男は大きくうなずいた。「そうですか。それではあなたは人参ですか?」 やっぱ、ただの馬鹿じゃないか。
いつもの朝食の香りで目が覚めた。「ごはんができましたよ」 妻の声がする。それにしても妻はいつでも楽しそうに働く。二人とも、もう老人と呼ばれてもおかしくない年齢になったが人里離れた奥地でこうして二人だけでなんとか暮らして行けるのも明るい性格の妻のおかげだ。
「今日は良い天気だな」「雨は降らなさそうね」 特に話題もないせいか食事のときはつい天気の話ばかりしてしまう。朝食を食べ終わり私たちはいつものように今日の予定を決めることにした。「食べ物はまだ充分にあるかな」 「ええ、あと4,5日はもちますよ」 「薪がそろそろ切れてきたんじゃないか?」 「薪はまだあるんですけど、細かいのがそろそろ無くなりそうですねえ」 「わかった拾いに行くとしよう」 「では私は洗い物が溜らない前に洗濯でもしましょうか」 珍しく二人揃って家を出て途中まで一緒に歩くことにした。「来週あたりから冬の支度も始めないと」 「いくらなんでも、まだ早くないか?」 「そういって毎年雪が降りそうなころに慌てるでしょう」 そんな他愛も無い話をしているうちに山道の入り口についた。「気をつけてくださいね」 「ああ、篭いっぱいに集めたら帰ってくることにするよ。お前も川に落ちないようにな」 「はいはい」 妻は山ほどの洗濯物を抱え軽快に川原へと向かって行った。私もこうしてはいられない。西の斜面はまだ地盤が緩そうなので、南側に回って小枝を集めて来ることにしよう。 ふと、昨夜納屋にしまってあった大きなまな板と包丁を取り出し、手入れをしたことを思い出した。特に使う当ても無いのだが、そうせずには居られなかったのだ。何故だろう。今日は不思議な事が起きそうな気がする。その不思議な出来事にまな板と包丁が役立つのだろうか?
「サトラレって流行ったじゃないですか」
「ええ、そういう映画が作られてヒットしたようですね」 「あれのパロディで『サトラセ』って考えたんですけど、面白いと思いませんか?」 「タイトルだけでは面白いとは思えません」 「『サトラセ』は、Aさんの考えてることをBさんに解らせることができるのです」 「ということは、Aさんとして自分を設定したら『サトラレ』で、Bさんとして自分を設定したら『サトリ』に相当する訳ですね」 「えーと、それだと面倒だからAさんBさんは自分以外にするのです」 「機能上の制限としてそれほど不自然ではないので、それでも良いかと思います。もう三点、AさんとBさんとして同じ人をセットすることはできないことにしますか?また、二組以上同時にその能力を発揮できますか?最後に一対他もしくは他対一で同様のことが可能ですか?」 「それはどれも考えてなかったのです。最初のは、そんなことされたら頭がポーンって爆発しそうなので、できないことにします。次のもその次のも面倒なのでなしにします」 「まとめると『サトラセ』は自分以外の任意の異なる二名の間に思考過程をモニタするための一方通行のパイプのようなものを一本だけ自由に取り外しができる能力を持つということで良いですか?」 「多分それであってるんだと思います。どうでしょう、面白くないでしょか?」 「あ、もうひとつ気づいた。AさんとBさんの間に作られたパイプは『サトラセ』がはずさない限り永久に残りますか?続くとしたら『サトラセ』が死亡した場合や記憶喪失になった場合はどうなりますか?」 「うーん。それはどっちにした方が話が面白くなるかで決めるのです。先に決めた方がいいですか?」 「いや、後でも良いです。その場合、決めるまではどっちに転んでも良いように途中の話を作ることが大事です。あ、また疑問が。その『サトラセ』の能力は万能ですか?つまり誰にも防ぐことはできないか、防げるとしたらどんな人かを決めておいた方が良いです」 「むむう。どんどん複雑になってきたのです」 「そういえば、Aさんが英語圏の人でBさんが英語を理解できない場合はどうなるのか?そもそもAさんの考えてることは、どのような形式でBさんに伝わるのかも気になります。あと、Aさんの考えていることと言っても、表層の思考からAさん自身もはっきりと意識していない深層の心理まで広い範囲がありますがそのどこまでをサトラセることができるのでしょう?」 「うーん。何だか面倒になってきましたよ。それにしてもどうして、そう次々と疑問点を思いつくんですか?」 「モジュールテストの基本です。いやオブジェクトの設計の段階でこれくらいのことは想定しておくべきです。あとは『サトラセ』の効果はAさんとBさんの間の物理的な距離に依存するか、『サトラセ』状態にある場合に一方が死亡した場合に『サトラセ』は自動で停止するのか、それから…」 「もう、いいのです。別のお話を考えるのです」
「解った、要求を聞こう」 拡声器から刑事の怒鳴り声が響き渡る。
「いいかあ、人質の命が惜しかったら、今すぐ百億万円持って来い」 警察と野次馬と人質の間に別の緊張感が流れた。相手は武器を山ほど持っている、笑ってはいけない。そう思うと余計笑いを堪えるのが難しくなる。人質の一人が緊張に耐え切れず笑い出した。「ぶはぁ、ひゃひゃ百億万円。ひーひー、駄目だ可笑しすぎ」 つられて周りの何人かも笑い出した。「幾らだっつーの」「小学生でも言わないっての」 「うるせー、どこがおかしいんだ!」 犯人は笑い転げる人質に銃を向ける。人質たちは我に帰り、笑いは嘘のように収まった。「おい、お前。俺のどこが間違ってるんだ。言って見ろ」 犯人は最初に笑った人質に命令した。「いや、だって、ひゃひゃ百億万円。ぶははは、もう駄目だ我慢で」 ズドン。 最初の犠牲者が出た。もう笑い事ではない。刑事の怒鳴り声がまた聞こえてきた。「おい、何があったんだ。人質に何かあったら只じゃおかないぞ」 「うるせー、生意気な奴を一人始末したぞ。これ以上死人を増やしたくなかったら今すぐ百億万円用意しろぉ」 再び人質に緊張が走る。笑ったら撃たれると思うと余計笑いたくなる、後ろ手に縛られているので口を押さえて堪えることもできない。 刑事は増幅する笑いと戦いつつ、ここで笑っては犠牲者が増えるだけだと何度も自分に言い聞かせながら説得を続けた。「わ、解った。要求を呑もう。ただ金額が大きいので少し時間がかかる。もうちょっと待ってくれ。なんせ、ひゃひゃ百億万、うわはははは」 ついに刑事も笑い出してしまった。犯人は外に向って手榴弾を投げつけた。野次馬や他の警察官をはじめ多くの人が巻き添えをくった。 結局その後、数多くの人質と警察関係者と報道陣が犠牲となった挙句、日本語が解らない外国人の手を借りてようやく犯人を捕らえることに成功した。取り調べも裁判もかつてない爆笑の中進められた、 五年後、犯人の死刑が執行される日が来た。 「何か言い残すことはありませんか?」 執行官が尋ねた。 「百億万円が欲しかった」 犯人は自嘲的につぶやいた。 「そのネタ飽きたよ」 誰も笑わなかった。 胞子の人
「すいません。ちょっと失礼してカートリッジの交換を」 只野氏はそう言って鞄を探っている。言われてみると確かに彼のメットの中の空気が澄んでいて、話を始めたときよりも顔がはっきりと見えている。只野氏は胞子補給器を止め、大急ぎでカートリッジを交換して再度補給器のスイッチを入れた。メットの中は一瞬にして胞子で満たされる。きな粉を更に細かくしたような塵がメットの中で舞っている。何度見ても気分が悪くなる光景だ。
「話の腰を折ってすいませんねえ。カートリッジ交換が要らないタイプのも出てるんですけど、あれは高くて手が出ないのですよ」 只野氏はやっと楽になったらしく話し方も明るい。 「いえいえ。こちらこそ、いつもお越し頂くばかりで申し訳ございません」 「いやあ、私共の方に来て頂く訳に行かないのは、こちらさんとお取引をさせていただく以上当然のことですから」 もし行くとしたら宇宙服みたいな大げさな装備が要るだろう。 「それにしても大変そうですね。今回のように長期のご滞在だとカートリッジも沢山居るでしょう?」 「その点は大丈夫なんですよ。呼気から抽出してこちらで再生できますので、予備も入れて4本もあれば繰り返して使えるんです」 なるほど、鞄が大きいと思ったら再生装置が入っているのか。良く見るとメットから鞄へ管がつながっている。多分、交換の要らないタイプってのはメットだけで再生と供給が同時に出来るのだろう。 「そうでしたか。今回のお話がまとまれば、御社の技術担当の方が使う専用室をご用意いたしますので、その際は只野さんも装置なしにご滞在いただけると思います。それまではご不自由でしょうけどよろしくお願い致します」 専用室の用意にはかなりの出費を覚悟する必要があるが、彼らの持つ技術を独占契約できることに比べればどうってことない費用だ。 「ありがとうございます。そうしていただけるととても助かります。うちの技術担当も喜ぶでしょう」 胞子で曇って表情は良くわからないが、只野氏も嬉しそうだ。やはり装置での呼吸は面倒なのだろう。 「それでは、契約書の素案と仮契約の書類がこちらに入ってますので、ご検討をお願いし…」 只野氏の様子がおかしい。メットを押さえたまま動かない。「どうしました?大丈夫ですか?」 胞子で霞んだメット越しに顔を覗き込んだが、口から血を吐いている。脈もない。気の毒にも補給器の故障で亡くなってしまったのだろう。私は内線で総務部に連絡を取ろうとした。そのとき、只野氏の鞄で小さな破裂音がした補給器の外部装置が壊れたのだろう。鞄から黄色い微粒子が溢れ始めた、只野氏のメットの隙間からも吹き出している。今度は私が危ない、只野氏には悪いが、何もかも投げ出し大急ぎで会議室を飛び出した。外では部下が出口に簡易エアシャワーを直結して待機していたので被害は最小限にくい止めることができた。 エアシャワーから出ると、若い連中が会議室のドアを目張りしたり、胞子を除去するための薬剤を散布している。 「お疲れ様でした。とんだ災難でしたね」 「私は無事だったけど、只野さんは気の毒だったな。でも契約はほとんど成立していたわけだし彼らもドライな連中だ。仕事はこのまま進むだろう」 実際のところ私達より彼らの方がはるかにビジネスライクだ。すぐに代わりの担当者が飛んでくるだろう。 「この部屋の空調は完全封鎖して、窓も外から目張りをしているところですので他の部屋へは広がることはない筈です。しつこく事前に対策を検討しておいて正解でしたね」 「部長に礼言っとかないとな」 部長に先見の明があったのではなく、単に胞子を異常に怖がっていただけなのだが、結果として綿密な事前対策のおかげで私もこうして無事に生きてるわけだ。 「それにしても、会議室一つ駄目になっちゃいましたね」 すでに会議室は黄色い霧で満たされている。確かにすべて除去するのは諦めた方が賢明かもしれない。 「そうだ、例の専用室、ここにしよう」 かなり胞子の濃い部屋になりそうだ。先方の技術担当者も喜ぶだろう。 |
|
| (C)2003 T-BYPRO. All rights reserved. |