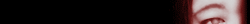
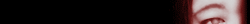 |
 |
GUZZLING All good children go to heaven. |
私、実は人間にとても近いんですけど、ちょっとだけ違う生き物なんです。あ、今笑ったでしょう。冗談だと思ってくれても全然OKですよ。ただ覚えておいてくださいね、あなたの周りに何の苦労をすることもなく簡単に何でもできちゃう人がいたら右手の中指と薬指の間を見てみてください。私と同じようにホクロがあるはずです。
右手の中指と薬指の間にホクロがあるという症状(通称ソニア)は病気ではありません。したがって健康上の心配はまったくありません。 昨年5月に悲運の死を遂げたシンガー ソニア の遺体は生前のインタビューで本人が希望していたとおり右手のみ保存されることとなった。 厚生労働省は、10代から30代後半にまで幅広く伝わる都市伝説が原因とされる、右手の中指と薬指の間にホクロがある人(通称ソニア)に対する差別を問題視し、具体的な対策を講じることを決定した。 緊急提言、ソニアも僕たちと同じ人間だ。 ソニアの右手の処置について、現在右手を保存している東京大学医学部は頭を悩ませている。より厳重に保存すべきであるという意見と、ソニア差別に関する諸悪の根源であるから廃棄すべきだと言う二つの意見が真っ向から対立しているのだ。 文部科学省は急増する「ソニアの子と同じ学級に入れるのはやめて欲しい」という親に対する啓蒙を行うためのガイドラインを設けることを決定した。 だからさ、みんながペンでホクロを書いちゃえばいいんだってーの(笑)。わかったか、くだらない理由を見つけては差別したがる負け犬ども、ジャンジャン。 当医院では30分程度の簡単な手術を行うだけで翌日からソニアの方も人間の社会で普通に暮らすことができます。 ソニア、ソニアってそう言う言い方はソニアの方に失礼だと思わないんですか! 「何度も言いますが、DNAの分析結果として種としての違いは、まったくと言っていいほど見当たらないんですよ」「でも同じ方法で分析してスピッツとマルチーズの間でも違いはほとんど見当たらないってご存知でしたか?」 ソニアと人間の間に産まれた子供の95%以上は人間であることが確認されている。ただし、ソニアの方が圧倒的に少数であることと、自らソニアであることを認める者が少ないため、この数字を鵜呑みにするのは危険である。ただ人間同士からはソニアは産まれず、ソニア同士からは人間は産まれないと言うことはほぼ確実でないかと思われる。 むしろ優れていることを誇るべきではないのか?人間は私たちが怖いんだろう。 人間てどうしてああやってヒステリックなんでしょう?気の毒だから指導してあげたほうが良いんじゃないかな。少し劣っているとは言え私たちの仲間なんだし。 大荒れの結果に終わった先の衆議院議員選挙で当選した議員のうち、いわゆるソニアが総議席数の約57%を占めることが当社の独自調査で明らかになりました。当選した議員のほとんどは自分がソニアであると告げていないことを問題視する意見も非ソニア議員より出されましたが、ソニアでないとも言っていないこと、そもそも公職選挙法にそのような規定が無いこと、仮にソニア全員が結託したとしても有権者数に占める割合がわずかであることを理由に問題視する必要はないと言う意見が多く…。 表に立つことを嫌っていた私たちの存在が明らかになり注目されたのは、一人のお調子者の軽はずみな言動がきっかけでした。皮肉なことに結果として私たちは人間を効率良く使用することができるようになり、人間も無駄な自治から解放され私たちの下でより正しい日々を送ることができるようになったのです。
道に迷ってしまった。山あいの温泉宿に来ていたのだが、ふらふらと散歩をしているうちに宿を見失い、いつの間にか森に入り込んでしまったようだ。そうこうしているうちに、辺りは暗くなろうとしている。さてどちらに向かおうと決めかねていると背後からいきなり「どうしたの?」と声をかけられた。「うわぁあああ」 道に迷い不安だったことに加えて、何の気配もなく唐突に声をかけたれたため私は取り乱し情けない声をあげてしまった。落ち着いてよく見てみると小学生くらいの子供が二人けたけたと笑っている。私のうろたえ方がよっぽどおかしかったのだろう。子供たちは私をじろじろと見つめてから「ねえ、人間だよね?」 と奇妙な質問をしてきた。ここら辺の子供たちの間ではやっているの質問なのだろうか?「ん?そうだよ。人間に見えない?」 私は子供と会話する事が苦手なので冗談で返してみた。「うわ、やっぱり」「言ったとおりだろ」「初めて見た」「そうだと思ったんだ」 何か引っ掛け問題の類いだろうと思っていたら予想外の反応を見せてくれた。仕方が無いのでもう少し付き合うことにしよう。「そんなこと言ったって君たちだって人間に見えるけど」 すると彼らは嬉しそうに笑い出した。「うわあ、じいちゃんの言ってたとおりだ」「人間って必ずそう言い返すんだね」 妙に盛り上がっている。そんなことより宿への道を早く教えてくれないだろうか。「ねえ、人間。じいちゃんのところに行けば帰り道が解るよ」「そうだよ人間。じいちゃんは何でも知ってるんだよ」「すぐ近くだからおいでよ。人間」「こっちだよ。人間」 こんな風に人間と呼ばれたのは初めてかもしれない。とりあえず大人の居る場所には連れて行ってもらえそうなので、私は後をついて行くことにした。
子供たちに連れられて森の奥に入って行くと、10分ほどで小さな小屋にたどり着いた。「じいちゃん、人間を連れてきたよ」「困っているみたいだから助けてあげてよ」子供たちは口々に勝手なことを言っている。「どれどれ、人間とは珍しいのう」そう言いながらやはりどう見ても人間としか思えない老人が奥から出てきた。老人は私の姿を見るなり、すまなそうな顔をして「申し訳ございませんのう。あやつらはまだ何も解っとりゃせんのですわ」 と謝った。「いいえ、可愛いじゃないですか」 私が笑うと老人は少し安心したようだった。「あなたは私たちが何者であるか、解っているようですな」「それが全然解らないのです。ただ人間でないことは匂いで解りましたよ」 私がそう答えると老人は愉快そうに笑った「そう言えばそうですな。うっかりしておりました」 幸い老人は宿への戻り道を知っていた。もう少し話をしたかったが、暗くなる前にこの場を後にすることにした。「人間じゃなかったんだね」「ごめんね」 さっきの子供達が見送りにきた。「どうかお気をつけて」 老人は頭をなでてくれた。「どうもありがとう。おかげでご主人様のところに帰れます。じゃあね」私は尻尾を振って答えた。
南太平洋の小さな島で世界一高い建造物を発見した。先端が見えないので正確な高さは解らないが、キロ単位の高さはありそうだ。ただ、その建造物は極端に細い形状をしていて縦横がそれぞれ2メートル程しかない。そのため数キロ離れると肉眼では見えなくなってしまう。今まで発見されていなかったのはそのためだろう。
この建造物の高さを知るにはヘリで上空に昇ってみるくらいしかできないだろうと思ったのだが、幸いにも表面の金属が磁石に吸着することが解ったので、CCDカメラと無線装置を取り付けた簡単なロボットを組んで上の様子を見ることにした。ロボットの移動距離で高さも解るだろう。 目視で予想したとおり、ロボットが1キロ以上上昇しても映像は途切れることが無かった。最初は気付かなかったのだが、これだけの距離を登っても送られてくる映像がほとんどぶれることは無かった。とてつもない剛性を持っているか、揺れを打ち消すよような制御が成されているのだろう。 そろそろ1.5キロを超えようとしている。登るだけならまだ充分な電力が残っているが貴重な機材を無駄にするわけには行かないので戻りの分を残しておく必要がある。もっと先を見たかったが、この辺でロボットを引き返させることにした。下降の最中、画面左側に壁面とは微妙に異なるものが一定間隔で映っている事に気が付いた。どうやら窓のようだ。昇っているときには見逃していたのだろう、着色され質感も壁と似せてはいるが確かに直径30センチほどの丸い窓のようだ。バッテリーの残量が気になるが一度下降を止めて窓のあたりでカメラの角度を変えて窓の中をじっくりと観察してみた。 窓から馬のような生き物がこちらを見ている。馬はロボットに気付くと窓から身を隠した。と同時に窓は壁と同化して中が見えなくなってしまった。窓の大きさと比較すると馬の高さはせいぜい10センチ以下といったところだろうか。馬にしては小さすぎるが、でも確かに馬のような姿をしていた。この不思議な生き物をもう少し観察したかったが、いよいよバッテリーが危うくなってきたので再び下降することにした。下降途中も目を凝らして画面を見ていたが、全ての窓が壁と同化したらしく、それ以降窓を発見することはできなかった。 とりあえず今考えられる仮説は次の2つだ。ひとつは「この針のような塔には小さな馬が住んでいる」、もうひとつは「私の頭がおかしくなった」。どちらも喜ばしい結論ではないと思うが。
「まだ信じてないでしょ?」 当たり前だ、最後まで信じるつもりはない。「解ってくれるまで何度でも繰り返して言うからね。とにかく疑ったら駄目なの。私だって自分でもものすごくおかしな事を言ってるって解ってるよ。その上で無条件で信じて欲しいって言ってるの」
「だから信じてるって。どうして疑ってると思うんだ?」 僕には同じ嘘をつくことしかできない。マキは怒っている。「あのねえ、君は私に何回嘘をついたか忘れたの?私だって馬鹿じゃないんだから、少しは学ぶよ。そんなことは寝てたって解るよ」 馬鹿じゃないどころか多分半径1000km以内の誰よりも出来の良い頭を持っているはずだ。それだけにどうしてこんなことを言い出したのか見当がつかない。 「お願い。悲壮な覚悟なんかいらないから、とにかく二人とも絶対に死なないって無条件で信じて。バンジージャンプなんかより遥かに安全だと保障するから」 マキの表情は普段とまったく変わらない。目つきが行っちゃってた方が、僕もよっぽど気が楽なのだが。 「これがさ、私と一緒に死んでって言われたのなら、恐怖に震えながらも言うことを聞いたかもしれないよ。でも、絶対飛べる疑うなって言われて、はいそうですかとは行かないよ。せめて悲壮な覚悟くらいはさせて欲しいな」 「要は命までは投げ出すけど、気持ちや考え方までは投げ出せないということだね」 そう言うことだ。 「悪いけどそれも頂戴。命だけなんてケチな事言わないで、今までの経験も記憶も嗜好も全部私に差し出して」 命を預けると言ってるのにケチと言われたのは僕が初めてかもしれない。よし、腹は括った。まず自分を騙そう、そうすればマキも騙せるだろう。「そう言われてやっと解ったよ。どうやったら信じることができるか解らなかったんだ。今の言葉でそれがようやく解った。もう大丈夫だ」 マキの表情が少し緩む「やっと信じてもらえたみたいだね」 旨く騙せたのか結局は僕が騙されたのか解らない。そんなことはどうでも良いことに思えてきた。 「じゃあ、行こうか」 50メートル下に飛び込むために、もう一度二人でフェンスを乗り越えた。大丈夫飛べる。お、いつのまにか自分も完全に騙せてるぞ。「もったいぶるのは嫌だから、カウントなしでせーので行こう」 マキはそう言いながら笑った。決断して良かった。 「せーの」 二人揃って飛び降りる。落下速度は思っていたより速くない、いや落ちていない。どうやら飛んでいるようだ。そうか、飛べるんだ。マキの言うことは正しかった、半分だけだけど。僕はもう自由に空を飛べる。凄く良い気持ちだ、風が心地よい、太陽も暖かい、僕だけの空はどこまでも青い。そして地面には真っ赤なトマトがひとつ。 夏の魔物
今日もヤスを誘って丘に登る。水筒にコーヒーを入れて、姉さんが作ってくれたサンドイッチを持って。30分かけてゆっくりと登る。馬鹿話しながら、女の子の話をしながら。
丘に登ってもすることがない。いつもと変わらない話をして、サンドイッチを食べて、キャッチボールをして、昼寝して、日焼けして、やっぱり馬鹿話をして。丘の上の馬鹿が無駄な時間を過ごす。魔物を待ちながら。 夕日がまぶしくて目を覚ました。また寝てたようだ。あたりには誰も居ない。ヤスは帰ったのか、それとも魔物に喰われたのか。いや、どちらでもない。木の上で寝ていたようだ。 「来ないな、今日も」「そろそろだって言ってたけどな」「案外どうってこと事ないもんだな」「来たら来たで逃げ出すんだろうけどな」「絶対捕まるのにな」 また同じ話だ。 「生贄てのはもっとおどろおどろしいもんだと思ってたけどそうでもないんだな」「いや、ここだけじゃないの?こんな呑気に待つ生贄なんて」 これも同じ話。 そろそろ暗くなってきた。今日あたり来ると思ったんだけどまだみたいだ、帰るか。そう言ってヤスのほうを見るとヤスの後ろに魔物が立っていた。振り返る間もなくヤスは一口で喰われた。自分が喰われたことも解んなかっただろうな。などと呑気なことを考えていたら、逃げるのを忘れてた。腰が抜けて立てなかった。 そのままじゃ食べにくいのか、ものすごい力で掴まれ持ち上げられた。体中が痛い。もう少し丁寧に扱って欲しいところだけど、所詮生贄なんで文句は言えない。牙にヤスのシャツが引っかかっているのが見えた。あんまり良い終わり方じゃなかったけど、なかなか楽しい夏休みだったよ。 俺、旨いのかなあ。 |
|
| (C)2003 T-BYPRO. All rights reserved. |